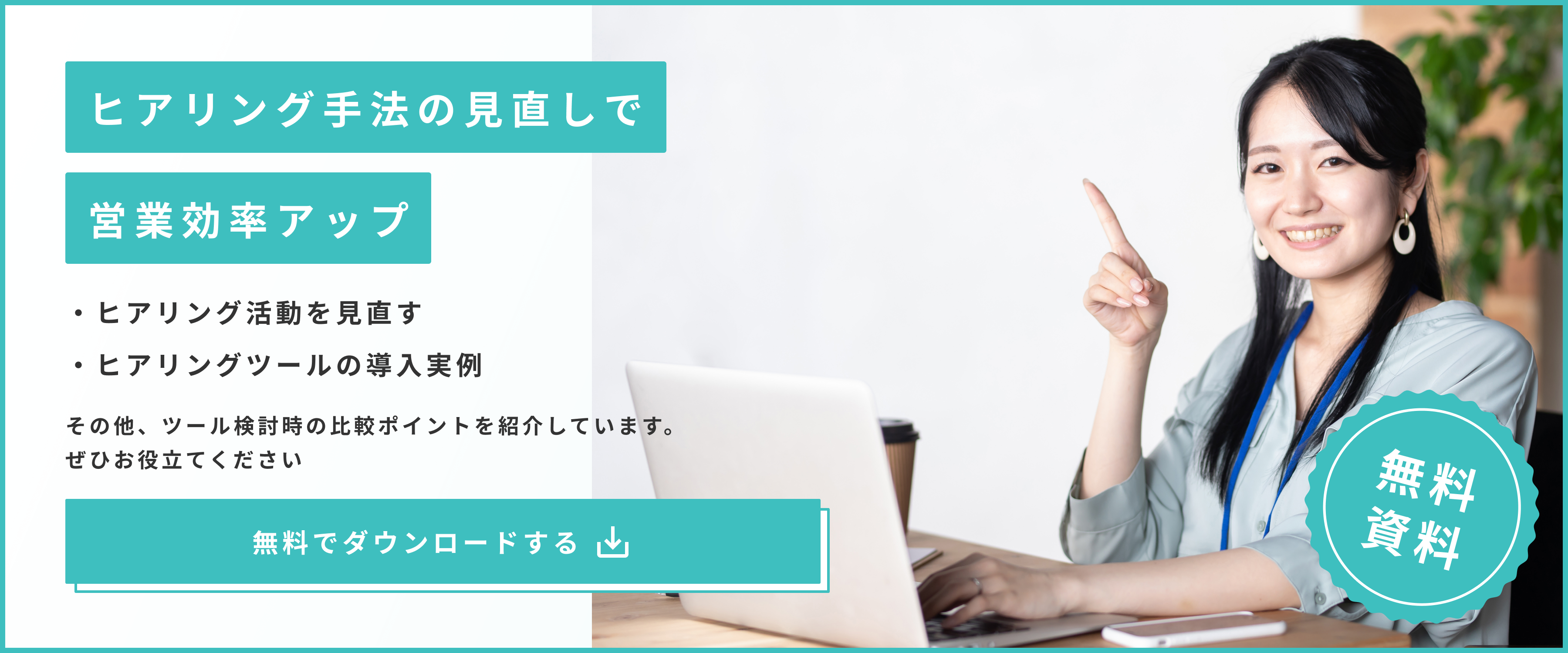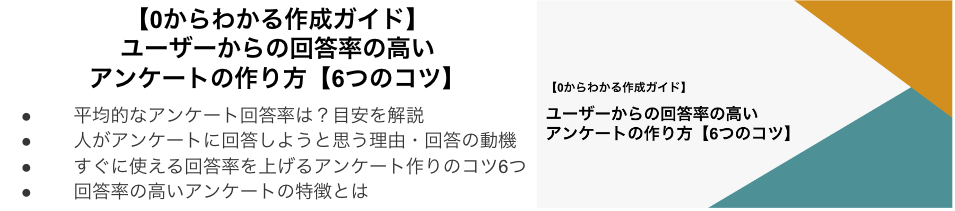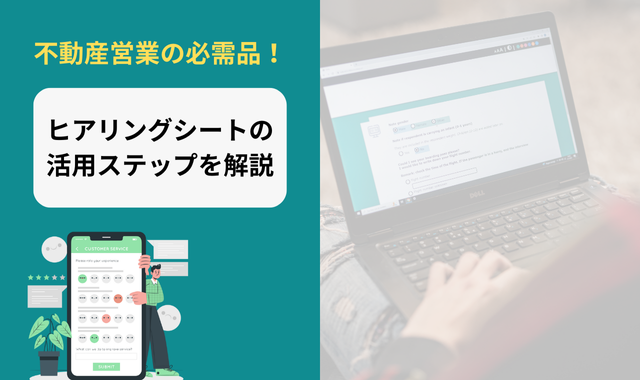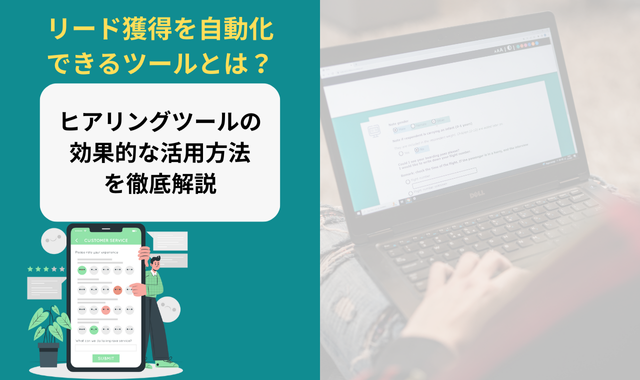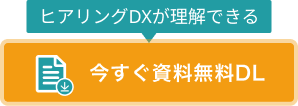アンケート調査に影響するバイアス6つと回答精度を高める質問設計の方法を解説
- 2024/09/16
- 2025/06/21
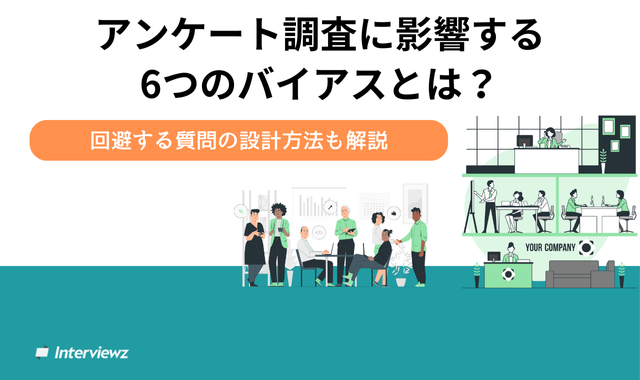
目次
アンケート調査は、顧客理解や商品開発に欠かせない手法ですが、設問や集計の過程でバイアスが入りやすいという課題があります。もし、このバイアスを見逃すと、得られたデータの信頼性や施策の効果が大きく損なわれてしまいます。
正確な意思決定のためには、バイアスの種類を知り、適切な質問設計を行うことが重要です。
そこで今回は、アンケート調査に影響するバイアス6つと、アンケートの回答精度を高める質問設計の方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
アンケート調査におけるバイアスとは?基礎知識を解説

アンケート調査でバイアスが生じる理由
バイアスとは、アンケート調査などで回答者の心理や質問の設計、調査の状況によって生じる「偏り」や「歪み」のことを指します。
例えば、質問の仕方が誘導的だったり、回答者が社会的に望ましい答えを選んだりすることで、本来の意見と異なる結果が出てしまう現象です。バイアスが入ると、調査結果の信頼性が低下し、正確な顧客インサイトや意思決定が難しくなります。
バイアスを理解し回避することは、質の高いアンケート調査を行う上で非常に重要です。
アンケート調査でバイアスが生じる主な理由は、質問文の表現や選択肢の設定、調査の状況など多様な要因が複雑に絡み合うためです。
例えば、質問が誘導的であったり、選択肢が網羅的でなかったりすると、回答者は本来の意図とは異なる回答を選びやすくなります。また、社会的に望ましいとされる回答を選ぶ「社会適応性バイアス」や、yes/noで答えやすい「同意バイアス」など、心理的な偏りも発生します。
さらに、サンプリングの方法や回答者の属性によっても偏りが生じやすく、調査設計や運用の工夫が不可欠です。
バイアスが調査結果に与える影響
バイアスがアンケート調査に入り込むと、得られるデータが現実の姿から大きく歪められてしまいます。
例えば、社会的に良いとされる回答が多くなれば、実際の行動や意識との乖離が生じ、マーケティングや商品開発などの意思決定に誤った方向性をもたらします。また、サンプリングバイアスがあると、特定の属性の意見ばかりが集まり、ターゲット全体の実態を正しく反映できません。
このようなバイアスの影響で、調査結果の信頼性や活用価値が低下し、ビジネスの成果にも悪影響を及ぼすリスクがあります。
バイアスを理解する重要性
バイアスを正しく理解することは、調査の精度と信頼性を高めるうえで不可欠です。バイアスの種類や発生要因を把握し、設問設計やサンプリング方法を工夫することで、意図しない偏りを最小限に抑えることができます。
また、調査結果を解釈する際にも、どのようなバイアスが入り得るかを意識することで、データの限界や活用の際の注意点を把握できます。
バイアスへの理解と対策は、正確な顧客インサイトや意思決定につながり、調査の価値を最大化するために欠かせません。
アンケート調査に影響する主なバイアス6つとその影響

バイアスとは、データや結果が特定の方向に偏ることを指します。アンケート調査においては、質問の設計や回答の収集方法などにより、回答が意図せずに歪められることがあります。
アンケート調査における主なバイアス6つ
アンケート調査における主なバイアスには、次の6つが挙げられます。
- タイトルバイアス
- 同意バイアス
- 社会適応性バイアス
- アンカリングバイアス
- テレスコーピング
- 名声バイアス
それぞれ解説します。
1.タイトルバイアス
タイトルバイアスとは、アンケートのタイトルが回答者の意識に影響を与え、その後の回答に偏りが生じやすいバイアスです。
例えば、「環境にやさしい企業活動についてのアンケート」と題されたアンケートの場合、回答者は環境問題に配慮する答えを選びやすくなります。
2.同意バイアス
同意バイアスとは、回答者が質問に対して無意識に同意しやすくなるバイアスのことです。
例えば、「この製品は素晴らしいと思いますか?」という質問に対して、回答者は「はい」と答えやすくなります。
3.社会適応性バイアス
社会適応バイアスとは、回答者が社会的に望ましいとされる回答を選びがちになるバイアスのことです。
例えば、「あなたはリサイクルをしていますか?」という質問に対して、実際にはしていなくても「はい」と答えやすくなる傾向があります。
4.アンカリングバイアス
アンカリングバイアスとは、最初に提示された情報が、その後の回答に影響を与えるバイアスです。
例えば 最初に高い価格を提示された後に他の価格を提示されると、最初の価格が基準となり、他の価格が相対的に安く感じられることがあります。具体的には、「商品Aは5,000円でしたが、商品Bは3,000円です。この商品Bは安いと感じますか?」といった質問です。
5.テレスコーピング
テレスコーピングとは、回答者が過去の出来事を実際よりも最近のこととして記憶する現象です。
例えば、「過去1年間に何回映画を見ましたか?」という質問に対して、実際には2年前の出来事も含めて回答してしまうといったケースです。
6.名声バイアス
名声バイアスとは、回答者が自分の社会的地位や名声を高く見せようとするバイアスです。
例えば、「あなたの収入はどれくらいですか?」という質問に対して、実際よりも高い金額を答える傾向があります。
上記のようなバイアスを理解し、アンケート設計に注意を払うことで、より正確なデータを収集しやすくなります。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
バイアスを回避する質問の設計方法6つ

アンケート調査でバイアスを回避するためには、いくつかの工夫が必要です。以下に、具体的な方法をいくつか紹介します。
- 中立的な質問を設計する
- 回答者の匿名性を確保する
- 質問や選択肢の順序をランダムにする
- 中立の選択肢を設けない
- 事前テストを実施する
- 回答者の多様性を確保する
それぞれ解説します。
1.中立的な質問を設計する
「この製品が好きですか?」という質問は、回答者に「好き」と答えることを促す可能性があります。代わりに、「この製品についてどう思いますか?」と尋ねることで、回答者が自由に意見を述べやすくなります。
また、質問の文言が曖昧でないことも重要です。例えば、「サービスの質はどうですか?」ではなく、「サービスの迅速さについてどう思いますか?」と具体的に尋ねると良いでしょう。
2.回答者の匿名性を確保する
アンケートの回答が匿名であることを明示し、個人情報を収集しないように設定します。
例えば、オンラインアンケートでは、IPアドレスを記録しない設定にすることで、回答者が自分の意見が特定されることを恐れずに回答できます。
3.質問や選択肢の順序をランダムにする
アンケートツールを使用することで、各回答者に対して、質問や選択肢の順序をランダムに表示することが可能です。これにより、特定の順序が回答に影響を与えることを防ぎます。
例えば、質問1と質問2の順序をランダムに入れ替えることで、どちらの質問が先に来ても回答の質が変わらないようにします。
4.中立の選択肢を設けない
「どちらでもない」や「わからない」といった選択肢を排除し、回答者に具体的な意見を求めます。例えば、「この製品をどの程度満足していますか?」という質問に対して、「非常に満足」「満足」「不満」「非常に不満」といった選択肢を提供し、中立的な選択肢を避けます。
ただし、質問の内容によっては中立的な選択肢が必要な場合もあるため、慎重な判断が必要です。
5.事前テストを実施する
アンケートを実施する前に、小規模なグループでテストし、質問の理解度や回答の偏りを確認することが重要です。例えば、10人程度のテストグループにアンケートを実施し、フィードバックを収集します。このフィードバックを基に、質問の文言や選択肢を修正し、より明確でバイアスの少ないアンケートを作成しましょう。
6.回答者の多様性を確保する
回答者の背景や属性が多様であることを確認することが大切です。例えば、年齢、性別、職業、地域などの属性を考慮し、幅広い層から回答を集めましょう。これにより、特定のグループに偏らないデータを収集することが可能です。また、アンケートの配布方法も多様化し、オンラインや郵送、対面などの複数の方法を組み合わせるのがおすすめです。
上記のような方法を実践することで、アンケート調査のバイアスを効果的に回避し、より信頼性の高いデータを収集できるでしょう。
▼下記からは、ユーザーからの回答率の高いアンケートの作り方のコツを無料でダウンロードできます。
このサービスを活用することで、平均的なアンケートの回収率や、答えたくなるアンケートの作り方のコツなどを詳しく理解することが可能です。
自社のアンケート内容を効果的に改善したいとお考えの方は、ぜひご参照ください。
バイアスを最小限に抑えるためのチェックポイント5つ

アンケート調査でバイアスを最小限に抑えるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 質問文が具体的で簡潔か
- 選択肢の網羅性と中立性が保たれているか
- 質問の順序が工夫されているか
- 調査の目的が明確化されているか
- プリテストを実施したか
それぞれ解説します。
1.質問文が具体的で簡潔か
質問は具体的であるべきです。例えば、「あなたの好きな食べ物は何ですか?」よりも「あなたが最も頻繁に食べる果物は何ですか?」の方が具体的です。
また、長い質問文は避け、簡潔にまとめましょう。複雑な質問は回答者を混乱させる可能性があるため、シンプルな言葉で表現することが大切です。
2.選択肢の網羅性と中立性が保たれているか
すべての可能な回答をカバーする選択肢を提供することが重要です。例えば、年齢を尋ねる場合、「18-24歳」「25-34歳」「35-44歳」など、幅広い年齢層をカバーする選択肢を用意しましょう。
また、選択肢は中立的でなければなりません。特定の回答を誘導するような表現は避け、「はい」「いいえ」「わからない」などの中立的な選択肢を含めましょう。
3.質問の順序が工夫されているか
前の質問が後の質問に影響を与えないように、順序を工夫することも重要な要素です。例えば、感情に関する質問は最後に配置するなどの工夫が必要です。
また、関連する質問をまとめて配置し、回答者が一貫した思考プロセスで回答できるようにしましょう。
4.調査の目的が明確化されているか
調査の冒頭で、調査の目的やデータの利用方法を明確に伝えましょう。これにより、回答者の協力意欲が高まります。
また、調査のタイトルやテーマを明確にし、回答者が何に答えているのかを理解できるようにすることも重要です。
5.プリテストを実施したか
本番の調査を行う前に、少人数を対象としたプリテストを実施しましょう。これにより、質問文の理解度や回答のしやすさ、所要時間などを確認できます。
また、プリテストの結果を基に質問文や選択肢を修正し、より良い調査票へと改善することが大切です。
上記のポイントを踏まえたアンケートの調査票を作成することで、回答バイアスを最小限に抑え、より正確なデータを取得することが可能です。
▼以下の資料では、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較しています。
ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。
類似サービスの比較を行いたい方は、1分で比較できる以下の表を是非ご参考ください。
アンケートの回答精度を高めるための実践方法

回答率向上のための工夫
アンケートの回答率を高めるには、回答者の負担を減らし、モチベーションを高める工夫が不可欠です。具体的には、アンケートの目的や趣旨を冒頭で明確に伝え、回答者が「なぜ協力すべきか」を理解できるようにしましょう。
設問数は必要最低限に絞り、簡潔な文章と選択式中心の設計で回答の手間を減らします。また、「3分で完了」など所要時間を明記し、モバイル対応やインセンティブの提供も有効です。回答しやすい導線や、アンケート専用の回答時間を設けることも、離脱防止につながります。
データ収集・分析時の注意点
データ収集・分析では、設問の順序や表現に注意し、回答者が無理なく答えられる流れを意識することが重要です。専門用語や曖昧な表現は避け、1問1内容の明確な質問にしましょう。
また、サンプリングバイアスを防ぐため、対象者の属性や回収方法を工夫し、できるだけ多様な意見を集めましょう。分析時は、未回答や極端な値の扱いに注意し、必要に応じてデータクリーニングを実施します。仮説を立てて設問を設計し、結果と照らし合わせて施策に活かす視点も大切です。
結果解釈の際のバイアス認識
アンケート結果を解釈する際は、バイアスの影響を常に意識することが不可欠です。社会的望ましさや同意バイアス、サンプリングバイアスなど、調査設計や回答者心理による偏りがデータに含まれている可能性を前提に分析を進めましょう。
得られた結果を鵜呑みにせず、設問や回収方法に起因する歪みを検証し、必要に応じて他の調査データや現場の声と突き合わせることが重要です。バイアスを認識しながら多角的に解釈することで、より信頼性の高い意思決定につながります。
▼Interviewz(インタビューズ)では、ヒアリング体験をDX化し、質の高い情報をスピーディーに収集、顧客・ユーザー理解を深め、サービスのあらゆるKPIの改善を可能にします。
テキストタイピングを最小化した簡単かつわかりやすいUI/UXと、収集した声をノーコードで様々なシステムに連携し、ユーザーの声を様々なビジネスプロセスで活用することで、よりビジネスを加速させることが可能です。
以下の資料ではそんなInterviewz(インタビューズ)のより詳しいサービスの概要を3分で理解いただけます。Interviewzについてより詳しく知りたい方は、以下の資料をご参照ください。
アンケート調査のバイアス対策には、インタビューズのヒアリングツールがおすすめ
インタビューズのヒアリングツールは、アンケートや診断コンテンツを簡単に作成し、ユーザーからのフィードバックを効率的に収集するためのノーコードSaaSツールです。
インタビューズのヒアリングツールがアンケート調査のバイアス対策におすすめな理由を、以下で紹介します。
1.質問を最適化できるから
インタビューズのヒアリングツールは、質問の分岐や選択肢のカスタマイズが容易です。これにより、回答者にとって最適な質問を表示し、無駄な質問を省くことができます。これは、バイアスを減らす一因として有効です。
2.ユーザーフレンドリーなインターフェースだから
インタビューズのヒアリングツールは、タップ操作で簡単に回答できるインターフェースを提供しており、回答者の負担を軽減します。これにより、回答者がストレスなく回答できるため、回答の質が向上し、バイアスの影響を最小限に抑えることが可能です。
3.リアルタイムなデータ収集と分析ができるから
インタビューズのヒアリングツールには、リアルタイムでデータを収集し、分析する機能が備わっています。これにより、調査の進行中に問題点を発見し、迅速に対応することが可能です。例えば、特定の質問で回答者が離脱する場合、その質問を修正することでバイアスを減らすことが可能です。
4.外部ツールとの連携が容易だから
インタビューズのヒアリングツールは、Google AnalyticsやSlack、Salesforceなどの外部ツールと連携できるため、収集したデータを他の分析ツールと組み合わせて活用することが可能です。これにより、データの一貫性を保ち、バイアスの影響をさらに減らすことができます。
5.プリテストの実施が容易
インタビューズのヒアリングツールを使えば、プリテストを簡単に実施できます。プリテストを通じて質問文や選択肢の適切性を確認し、必要に応じて修正することで、バイアスを最小限に抑えた調査票を作成することが可能です。
上記のように、インタビューズのヒアリングツールは、アンケート調査のバイアス対策に非常に有効なツールとしておすすめです。そこで、ぜひこの機会に30日間の無料トライアルをお試しください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。