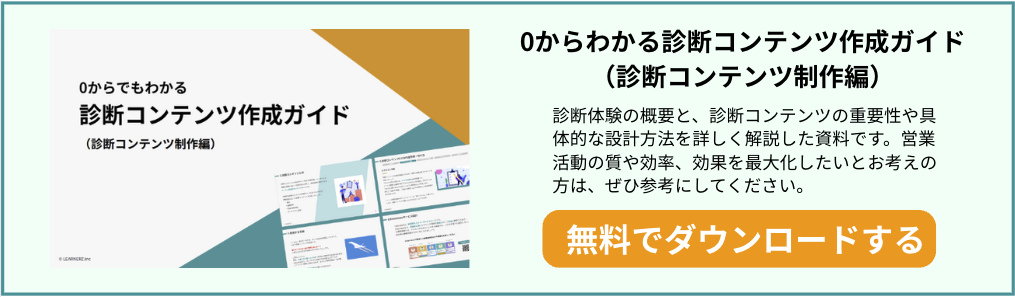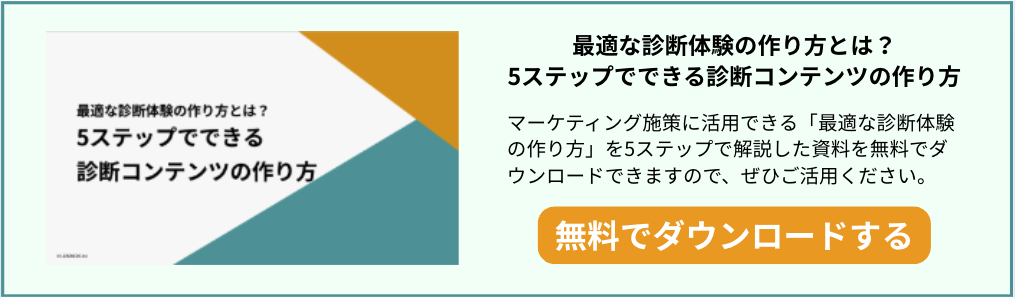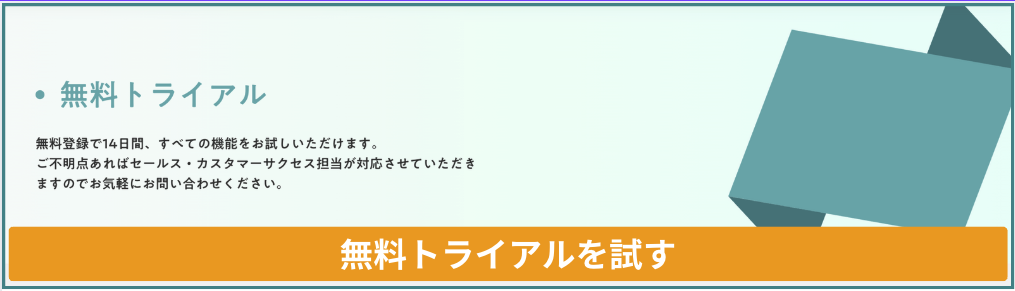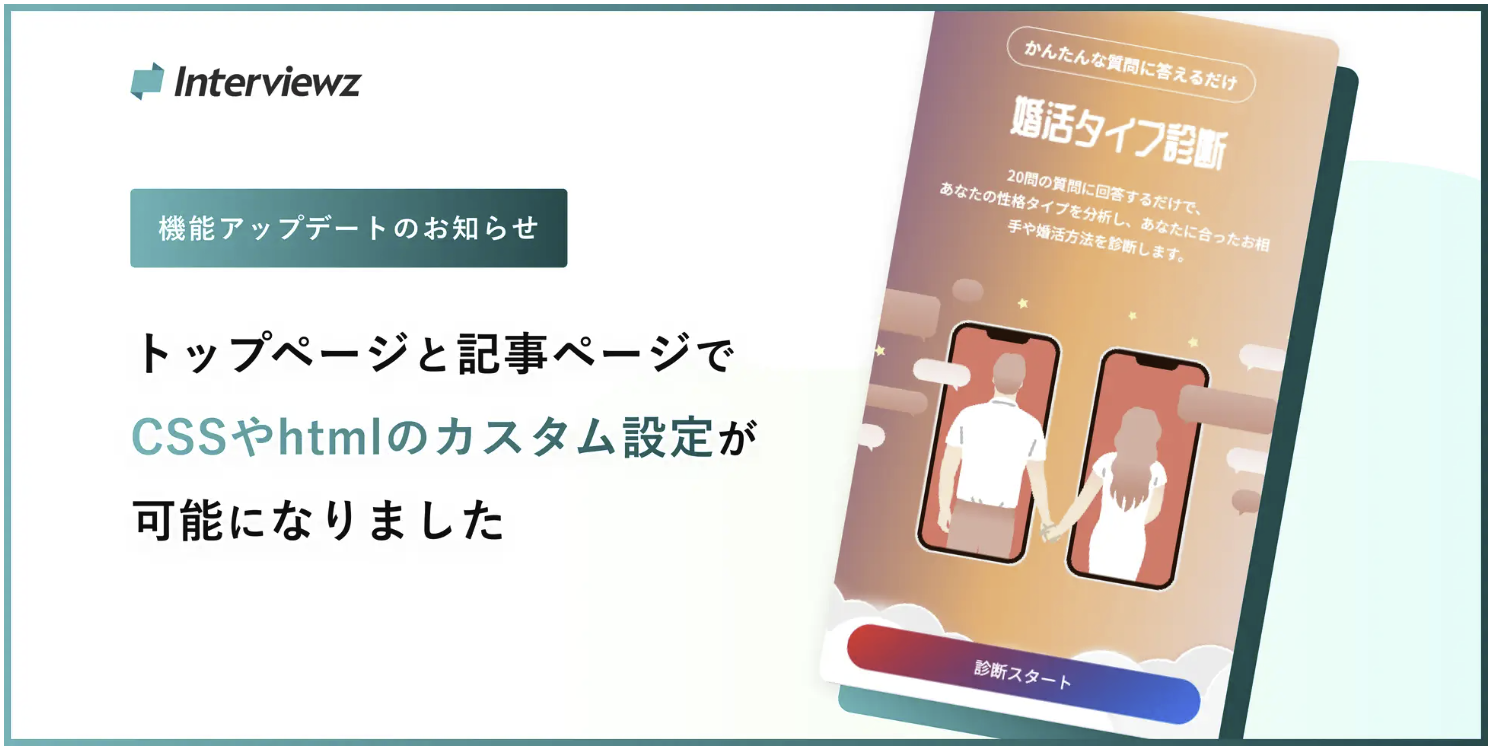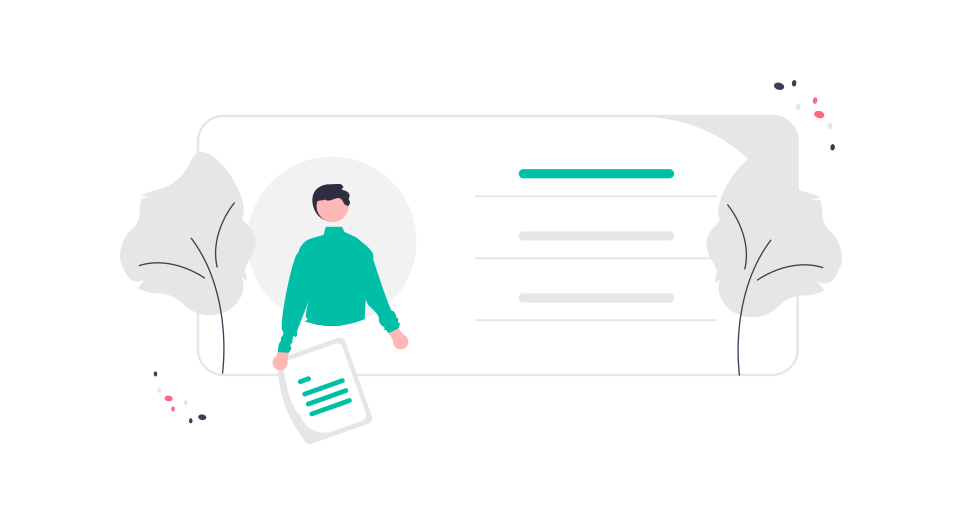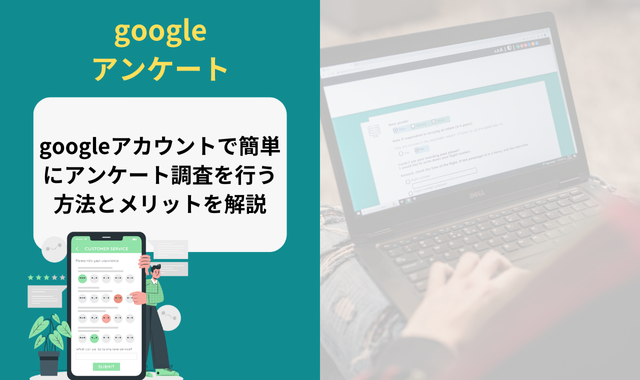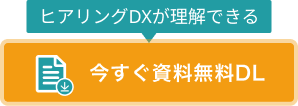診断コンテンツの効果的な使い方と活用事例|作り方やおすすめツールも解説
- 2023/03/19
- 2025/12/26

目次
マーケティングにおいて、診断コンテンツはただの情報提供ではなく、ユーザーと双方向のコミュニケーションを生み出す強力なツールです。
なぜなら、企業のサービスや商品を自然に提案できるだけでなく、ユーザーの関心を引きつけ、エンゲージメントの向上につながるからです。
しかし、ただ診断を導入するだけでは十分な効果が得られません。活用方法次第でその価値は大きく変わります。具体的な成功事例や効果的な使い方を知ることで、診断コンテンツのポテンシャルを最大限に引き出せるでしょう。
そこで今回は、診断コンテンツの効果的な使い方と活用事例だけでなく、作り方やおすすめツールも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
診断コンテンツの基本と効果的な活用方法

診断コンテンツの特徴と仕組み
診断コンテンツとは、ユーザーが複数の質問に回答し、その回答内容に基づき最適な結果やアドバイスを自動表示する双方向型のWebコンテンツです。
回答パターンに応じて結果が導かれ、ユーザーはゲーム感覚で楽しみながら自身に合った情報を得られます。
形式は「一問一答形式」「チェックシート形式」「ステップ形式」などがあり、それぞれユーザーの操作感や診断の精度に応じて使い分けられます。
ロジックには「フローチャート形式」(回答によって質問や結果が分岐)と「得点形式」(回答に点数を付けて合計点で診断結果を決める)があり、目的に応じて適した種類を選ぶことが可能です。
多くの診断コンテンツはSNSでのシェアを促し、拡散や認知度向上に貢献します。
マーケティングにおける診断コンテンツの役割
診断コンテンツは、顧客の興味・関心に合わせたパーソナライズ提案を可能にし、リード獲得・購買促進に直結する重要な役割を果たします。
質問を通じてユーザーのニーズを可視化し、それにマッチした商品やサービスを提案できるため、コンバージョン率の向上が期待されます。
また、ユーザーが楽しみながら参加する形式のためエンゲージメントが高まり、ブランド認知や顧客ロイヤルティの向上にも寄与するでしょう。
さらに、収集したデータはマーケティング施策の改善や新商品開発に活用可能です。
ユーザーエンゲージメントを高める設計ポイント
ユーザーの参加を促すためには、質問数の適度な設定や直感的なインターフェース設計が重要です。
一問一答形式は操作がシンプルで離脱が少ない一方、複数の質問を一画面にまとめるチェックシート形式は回答負担を減らします。
更にステップ形式は回答によって質問内容が変わり、繰り返し利用を促すゲーム性を高めます。診断結果はポジティブでユニークなものにし、SNSでのシェアを促す設計が効果的です。
結果画面から関連商品の詳細へスムーズに遷移させることも、エンゲージメント向上に繋がります。
SEO効果を最大化するための活用法
診断コンテンツはユーザーが自発的にシェアすることで拡散力が高いため、SEOの観点においても効果的です。
コンテンツの質を高めるために、検索ユーザーの悩みや興味にマッチした診断テーマ設定とキーワードの最適化が必要です。
また、コンテンツ更新や診断結果の改善を継続し、ユーザーの満足度を高めながら滞在時間や再訪問率を増やすことが重要です。
モバイルファーストの設計を実施し、多様なデバイスで快適に利用できることもSEO評価を上げるポイントとなります。
モバイル対応と操作性の最適化
モバイル利用者の増加に伴い、診断コンテンツはスマートフォンでの操作性が必須です。
レスポンシブデザインを取り入れ、画面サイズに合わせて見やすく操作しやすい設計を行います。ボタンや選択肢はタップしやすい大きさにし、読み込み速度の最適化も重要です。
また、操作が複雑なと離脱率が高まるため、シンプルでわかりやすいナビゲーションを心がけ、途中離脱を防止します。
さらに、チャット形式の対話型診断など新しいUXも注目されています。
以上が「診断コンテンツの基本と効果的な活用方法」に関する代表的なポイントです。これらを押さえることで、マーケティングに効果的な診断コンテンツを構築できます。
診断コンテンツが注目されている背景

診断コンテンツが注目される背景には、以下の要因があります。
・個別対応の重要性の高まり
ユーザーは、一般的な広告よりも自分に合った情報を求めています。診断コンテンツは、ユーザーの興味や課題に合わせた情報提供ができるため、パーソナライズされた体験を実現できます。
・エンゲージメントの向上
通常の静的なコンテンツとは異なり、診断コンテンツはユーザーが積極的に関わる形式であるため、サイトの滞在時間の増加やコンバージョン率向上につながります。
・SNSとの親和性
診断結果をシェアすることで、ユーザー自身のパーソナリティを表現できるため、拡散力が高まりやすいです。「あなたのタイプは?」などの診断は、友人やフォロワーとの交流のきっかけにもなります。
診断コンテンツがもたらす効果とメリット

マーケティングにおいて診断コンテンツを活用すると、以下のようなメリットが期待できます。
エンゲージメントを高めやすい
診断コンテンツは、ユーザーが質問に答えながら進める参加型の仕組みです。そのため、一方的に読むだけのコンテンツと比べて関与度を高めやすい特徴があります。
自分の興味や状況に近い内容に答えていく体験は、能動的な行動を促し、コンテンツへの没入感を生み出します。
クイズや簡易アンケートのような形式は気軽に楽しめるため、再訪や回遊のきっかけにもなりやすいでしょう。結果としてページ滞在時間の増加や閲覧数の向上が期待できます。
コンバージョン率の向上につながる
「結果を知りたい」という心理を自然に喚起できる診断コンテンツは、中間コンバージョンとして非常に有効です。
診断結果を通して、ユーザーが自分に合った商品やサービスを理解できるため、次のアクションへ進みやすくなります。
特に、結果に基づいたレコメンド形式は選択の迷いを減らし、購入や申し込みへのハードルを下げる効果があります。その結果、CPAの改善にも寄与するでしょう。
購買意欲を後押しできる
診断を通して、自分に合った提案を受けることで、ユーザーの購入意欲は自然と高まりやすくなります。
「何を選べばよいかわからない」「自分に合うものを知りたい」といった迷いを解消できるため、意思決定をスムーズに進められます。
自身の回答から導かれた結果であるため、一般的なおすすめ表示よりも納得感が強い点も特徴です。
商品点数が多い場合や、専門性の高い商材において特に効果を発揮し、効率的な売上向上につながります。
リード獲得とデータ活用に強い
診断結果の閲覧時にメールアドレスなどの情報入力を求める設計にすることで、見込み顧客の獲得が可能になります。
集まった回答データは、ユーザーの関心や属性を把握する貴重な材料となり、その後のマーケティング施策に活用できます。
回答内容をもとにしたセグメント分けや、個別ニーズに応じたアプローチが行えるため、より精度の高い施策を展開できる点も大きな利点です。
SNSでの拡散が期待できる
診断結果は「自分らしさ」を表現する要素として共有されやすく、SNSとの相性が良いコンテンツです。
ユニークな結果や共感を誘う内容であれば、ユーザーが自発的にシェアする可能性も高まるでしょう。
こうした拡散は、ユーザー自身が発信者となるUGCの創出につながり、広告費をかけずに認知拡大を図ることができます。
診断コンテンツの活用事例11選|成功事例を解説

診断コンテンツは大手企業でも活用されています。
自社サービスと診断コンテンツを組み合わせることで、サービスの認知度アップや成約率アップを狙えます。
診断コンテンツを活用している11の事例をピックアップしました。
それぞれの制作事例について詳しく解説します。
日本旅行 見つけよう!あなたにピッタリの旅行プラン診断
株式会社日本旅行が提供する「あなたにピッタリの旅行プラン診断」は、ユーザーに合った旅行先やプランを提案する診断コンテンツです。
旅行ニーズの把握や、ツアー情報の訴求、SNSでの拡散を目的に活用されています。
10問のシンプルな2択形式で構成されており、行き先選びに迷うユーザーの意思決定を後押ししているのが特徴です。
デザイン面でも工夫が施され、診断中から旅のワクワク感を演出することで、自然な流れで申込みへとつなげています。
マイナビ転職 ジョブリシャス診断
マイナビ転職では、自身の適職について診断してくれるジョブリシャス診断を実施しています。
転職は人生を大きく左右する可能性のあるライフイベントです。
転職の際に一番避けたいのは「転職に失敗すること」だと考える方も多いです。
ジョブリシャス診断では、20の質問に答えるだけで27のジョブタイプ別に適職を診断してくれます。
診断結果の詳細を見るにはマイナビ転職の会員登録をする必要があるため、自然な流れで登録者を増やせるという事例です。
マネ会 by Ameba 超簡単クレジットカード診断
ブログやゲームなど様々なサービスを展開しているAmebaが運営しているメディアのマネ会では、クレジットカードのおすすめ診断を行ってくれます。
クレジットカードは様々な会社が発行しており、人によって選ぶ基準が異なるので自身にあったクレジットカードを探すのは大変です。
マネ会では、いくつかのかんたんな設問に答えるだけでおすすめのクレジットカードを診断してくれます。
診断結果画面では、おすすめのクレジットカードを紹介しているページへ誘導されるため、かんたんにサイト滞在時間やコンバージョン率アップを狙える事例です。
ぐるなびWEDDING 結婚式スタイル診断
結婚式の情報検索サイトのぐるなびでは、かんたんな設問に答えると自身の理想とする結婚式スタイルを診断してくれます。
結婚式は人生で最も幸せだと感じるライフイベントの一つです。
結婚式への価値観は人それぞれで、盛大に盛り上がる結婚式にしたいという方もいれば落ち着いた雰囲気の結婚式が良いという方もいるでしょう。
結婚式スタイル診断を行うことで、ユーザーそれぞれに合った結婚式スタイルがわかるだけでなく、診断結果画面からそれぞれの結婚式スタイルに合った式場などを検索できます。
その結果、サイト滞在時間や回遊率アップを狙える仕組みになっています。
楽天オーネット 結婚チャンステスト
結婚相談所大手の楽天オーネットでは、結婚チャンステストと題して自身に合った理想の相手候補を診断してくれます。
結婚チャンステストで診断された理想の相手候補のプロフィールまで案内してくれます。
実際の会員データを元にプロフィールを紹介してくれるので、結婚に対して真剣に考えているユーザーはそのまま会員登録する流れに誘導できるでしょう。
また、相手候補の診断を行った際にユーザーの連絡先を入力する必要があるので、適切なタイミングでフォローアップの連絡もできるという事例です。
うまい棒の日を守れ!地球防衛プロジェクト(株式会社やおきん)
株式会社やおきんが1979年に発売したロングセラー商品「うまい棒」をテーマにしたプロモーション企画「うまい棒の日を守れ!地球防衛プロジェクト」が、2023年に実施されました。
本企画は「話題の拡散」が主な目的です。うまい棒のキャラクター「うまえもん」と共に、地球に迫る隕石を阻止するミッションへユーザーが参加するというストーリー性のある内容です。
参加者は診断コンテンツを通じて16種類の味ごとにチーム分けされ、ARコンテンツ内で「うまいパワー」を集める仕組みとなっています。最も多くのポイントを獲得したチームには、景品が当たるチャンスが用意されました。
診断によって普段選ばない味にも自然と目が向く設計となっており、結果を客観的に提示することでSNSでの共有やリアクションを促進しています。
この施策は、ユーザー参加型キャンペーンを簡単に構築できる「Metabadge」を活用して実施されました。
二世帯タイプ診断(株式会社Lakke)
株式会社Lakkeが提供する「二世帯タイプ診断」は、家族構成やライフスタイルに応じた二世帯住宅のタイプを提案する診断コンテンツです。
リード獲得と興味喚起を目的に展開されています。
約10問の質問に答えることで、生活スタイルに合った間取りや住まい方が提示され、将来の暮らしを具体的にイメージしやすくなっています。
診断後にはオンライン相談への導線も設けられており、次のアクションにつなげやすい構成になっているのが特徴です。
からだかがみ診断(クラシエホールディングス株式会社)
クラシエホールディングス株式会社が提供する「からだかがみ診断」は、ユーザーの体調や体質をもとに、適した漢方薬を提案する診断コンテンツです。
新規顧客の獲得や、漢方セラピーの認知向上を目的として展開されています。
質問数は多めですが、短時間で完了できる設計となっており、気軽に試せる点が特徴です。診断結果から自分に合った商品を見つけられるため、悩みの解消や満足度向上にもつながります。
商品は店舗販売のみのため、診断結果ページには位置情報と連動した購入可能店舗の案内が表示され、来店につながる導線が整えられています。
キャリタスクエスト(株式会社ディスコ)
株式会社ディスコが運営する新卒向け就職支援サービス「キャリタス就活」では、自己分析コンテンツ「キャリタスクエスト」を展開しています。
目的は、就活生の関心喚起とリード獲得、そしてサービス認知の向上です。
ゲーム要素を取り入れた構成で、ストーリーを進めながら回答する仕組みとなっており、楽しみながら自己理解を深められる点が特徴です。
全20問・1問1画面の設計で、回答は3択形式とすることで、ユーザーの負担を軽減しています。
診断結果の一部閲覧には会員登録が必要なため、自然な流れで登録を促進できる点もポイントです。進捗をキャラクターが知らせる演出により、離脱防止にも配慮されています。
あなたにぴったりの保険診断(ライフネット生命保険株式会社)
ライフネット生命保険株式会社が提供する「あなたにぴったりの保険診断」は、ユーザーの希望条件をもとに適した保険プランを提案する診断コンテンツです。
見込み顧客の獲得と、申込み促進を目的としています。
チェック形式で回答を進めると、診断結果では保険の種類に加え、月額保険料の目安も確認できます。
資料請求や相談申込みなど複数のアクション導線が用意されており、コンバージョンにつなげやすい設計が特徴です。
フジの母の日ギフト診断(株式会社フジ)
株式会社フジが展開する「フジの母の日ギフト診断」は、質問に答えることでお母さんのタイプを分類し、最適なギフトを提案する診断企画です。
タイプは5種類に分けられ、それぞれに合った商品が提示されるため、ギフト選びに悩むユーザーをサポートしています。
選ぶ楽しさを提供しながら、ニーズに合った商品提案を行うことで、満足度と購買意欲の向上が期待できます。
▼下記からは、Interviewzのデジタルギフト付きのアンケートに関する詳しい内容を無料でダウンロードできます。
このサービスを活用することで、通常のアンケートに比べて平均回答率が約2.8倍に改善された事例があります。ヒアリングやアンケートを効率的・効果的に改善したいとお考えの方は、ぜひご参照ください。
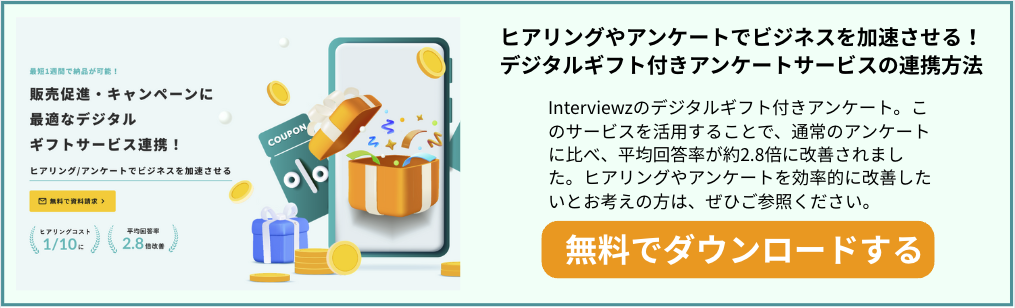
診断コンテンツの活用方法とおすすめの業界5つを紹介

診断コンテンツは自身の生活に関連した内容ほど興味を持ってもらえやすい傾向にあります。
その中でも代表的な5つのジャンルについて紹介します。
- 転職系
- 婚活・結婚系
- 旅行系
- クレジットカード系
- 保険系
それぞれのジャンルについて詳しく解説します。
おすすめジャンル1:転職系
転職は自分の人生に大きな影響を与えるライフイベントの一つです。
転職経験のない方など、転職する際のおすすめの職種や業界がわからないという方も多いでしょう。
転職系の診断コンテンツでは、自分の性格からおすすめの業種や職種をかんたんな質問に答えるだけで教えてくれるものが多いです。
転職系の診断コンテンツは、どの業界に転職するべきか迷っている方が利用することが多いです。
例えば、選んだ設問の選択肢に応じて最適な業界や職種の一例を紹介し、紹介した求人をチェックするために転職サイトの登録へ誘導する流れにするのがおすすめです。
その結果、自社転職サービスの登録率や長期的に見たときに求人申し込み件数アップを狙えるでしょう。
おすすめジャンル2:婚活・結婚系
婚活は様々な方法が存在しています。
最近では結婚相談所だけでなく、マッチングアプリなどの出会いの方法が存在します。
しかし、結婚相談所やマッチングアプリは一長一短で向いていない方もいるでしょう。
自身にはどちらの方法が向いているのかわからない方もいるので、そのような場合に婚活系の診断コンテンツがおすすめです。
診断コンテンツを活用することで、かんたんな質問で結婚相談所やマッチングアプリへの誘導ができます。
また、結婚系の診断コンテンツでは結婚式のおすすめプランなどを診断コンテンツを使って紹介することで、最適なプランを見つけてもらいやすいです。
自社サイトに診断コンテンツを設置し、問い合わせや申し込みフォームへ誘導するのがおすすめです。
おすすめジャンル3:旅行系
旅行をする際には様々な旅行プランから選ぶ必要があります。
旅行プランの種類が多すぎて迷った経験のある方もいるのではないでしょうか?
最近では新型コロナウイルスによる行動制限が緩和され、旅行の需要が増えています。
旅行プランを決めるのに迷っているという方に向けた診断コンテンツを作成するのがおすすめです。
航空会社や旅行代理店などの自社サイト内に、かんたんな質問形式でおすすめの旅行プランを紹介できる診断コンテンツを設置しておけば、興味を持ってもらえやすいでしょう。
紹介した旅行プランを元に、ツアープランの申し込みなど成約率向上を狙いやすくなります。
マスク緩和に始まる新型コロナウイルスの制限解除により、今後ますます需要が見込まれる業界です。
おすすめジャンル4;クレジットカード系
キャッシュレス決済が普及して現金を持たないという選択肢を選ぶ方も増えており、クレジットカードを持つ方も増えています。
一般社団法人日本クレジット協会によると、令和4年1月時点での日本の平均クレジットカード保有枚数は2.8枚というデータがあります。
クレジットカードは様々な会社が発行・提供しており、多種多様な特徴のものが存在する中でおすすめのクレジットカードを選ぶのは大変です。
診断コンテンツを活用すれば、かんたんな質問に答えるだけでおすすめのクレジットカードを紹介できるでしょう。
さらに、おすすめしたクレジットカードの申し込みページなどのリンクを用意しておけば、コンバージョン率アップを狙えます。
クレジットカード発行会社だけでなく、クレジットカードの情報を取り扱っているメディアなどでも利用されることが多いです。
おすすめジャンル5:保険系
保険は怪我や入院など、自身になにかトラブルが起きた際に助けてくれるサービスです。
生命保険や終身保険などに加入している方も多いです。
しかし、様々な保険会社がサービスを提供しており特徴が異なります。
ネット型の保険も増えてきており、どの保険を選んだら良いか迷う方も多いでしょう。
保険の加入を迷っている方向けに、ほけんの窓口のような様々な会社の保険を紹介してくれる場所も存在しています。
診断コンテンツを活用すれば、かんたんな設問に答えるだけでおすすめの保険商品を提案できるでしょう。
そこから資料請求や申し込みの問い合わせにつなげられるのでおすすめです。
新型コロナウイルスの影響で、自身の健康管理に関心を持つ方が増えたため今後も需要が高い業界です。
▼以下は、診断体験の概要と、診断コンテンツの重要性や具体的な設計方法を詳しく解説した資料です。営業活動の質や効率、効果を最大化したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
診断コンテンツの作り方6ステップと具体事例

診断コンテンツを作成する際には、ユーザーの興味を引き、価値ある結果を提供することが大切です。そこで、以下の6ステップに沿って具体的な事例を交えながら解説します。
1.目的を明確にする
まず、診断コンテンツの目的を決めます。
例えば次のような事例が挙げられます。
- マーケティング向け:「あなたにぴったりのスキンケア商品診断」
- 自己分析向け:「あなたの強み診断」
- エンタメ要素:「もしあなたが歴史上の人物なら誰?」
2.対象者を設定する
どんな人に向けた診断なのかを明確にします。
- 若年層向け:「あなたのSNS映え度チェック!」
- ビジネスパーソン向け:「あなたのリーダータイプ診断」
- 趣味・娯楽向け:「あなたの旅行スタイル診断」
3.診断の構成を考える
設問数や結果の種類を決めます。
設問は5~10問程度が一般的です。
結果は3~5種類用意すると分かりやすいでしょう。
例えば「あなたの仕事スタイル診断」の場合は、次のような設問例が挙げられます。
- 設問例:「チームで働くとき、どんな役割が多い?」
- 結果例:「リーダータイプ」「調整役タイプ」「アイデアマンタイプ」
4.設問と選択肢を作成する
答えやすく、楽しい設問を考えましょう。以下に、その一例を紹介します。
「はい/いいえ」形式
例:「休日は予定をきっちり決めたい?」
「数値で答える」形式
例:「1~5のうち、どれくらいチャレンジ精神がありますか?」
「選択肢から選ぶ」形式
例:「好きな映画のジャンルは? アクション/ミステリー/コメディ/ドラマ」
5.診断結果を作成する
診断結果がユーザーにとって有益であるようにします。以下で、その一例を紹介します。
結果に具体的なアドバイスを加える
例:「あなたの旅行スタイルは『冒険型』!おすすめの旅先はペルーやモロッコ」
共感を生む工夫をする
例:「あなたは『計画派』。旅行はしっかり準備したいタイプですね!」
6.デザインと公開
診断コンテンツのデザインを魅力的にし、適切な形で公開します。具体的には、次のような方法がおすすめです。
- WebページやSNSで配信
- インタラクティブな形式(アニメーション付き診断など)
- シンプルなUIで直感的に操作できるデザイン
また、診断コンテンツは楽しく簡単にできるものほど拡散されやすいです。例えば、性格診断やおすすめ商品診断は特に人気があります。ぜひ参考にしてください。
▼下記の資料では、自社のマーケティング施策に活用できる最適な『診断体験』の作り方を5つのステップで解説しています。診断コンテンツはユーザー自身の潜在的なニーズを深掘り、自分が求めるサービスや理想像をより明確にできるため、CVRの向上や診断コンテンツを通じてLTVを向上させることが可能です。自社のサービスで診断体験を通じたユーザー獲得や認知拡大をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
診断コンテンツを作る際の代表的な形式2つ|得点形式とフリーチャート形式

診断コンテンツには様々なロジックが存在しています。
今回の記事では、自社サービスの成約につなげられるようなロジックの中から代表的なものを2つ紹介します。
- 得点形式
- フローチャート形式
それぞれのロジックについて詳しく解説します。
1.得点形式
得点形式は、選んだ選択肢に応じて得点付けを行い、最終的な得点で結果が表示される形式のロジックです。
設問のどの選択肢を選んでも次の設問は同じという特徴があります。
最も手軽に作成できる診断コンテンツのロジックです。
しかし、「どの選択肢を選んでも設問が変わらないので飽きられやすい」、「単調に感じるので飽きられやすい」などのデメリットがあります。
繰り返し診断コンテンツで回答してもらいたい場合には不向きです。
設問数が目安5〜10問程度であれば、ユーザーにも飽きられにくいでしょう。
2.フローチャート形式
フローチャート形式は、選んだ選択肢により次の設問が変化する形式のロジックです。
「パーソナライズされた診断コンテンツだと感じてもらいやすい」、「自社サービスに興味を持ってもらいやすい」というメリットがあります。
診断コンテンツを作成する上でおすすめのロジックです。
それぞれの選択肢ごとに設問や診断結果が変化するため、得点形式のロジックと比較して作成に手間がかかるのがデメリットです。
しかし、【Interviewz】のような診断コンテンツ作成ツールを活用すれば、かんたんに質の高い診断コンテンツを作成できます。
取り扱っているサービスが多い場合や、何度も繰り返し診断コンテンツを利用してもらいたい場合におすすめです。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
診断ツールを簡単に作成できるおすすめサービス6選
次に、おすすめの診断ツール作成サービスを6つ紹介します。
1.Interviewz
 Interviewzは、操作性がわかりやすく誰でも簡単に高度な診断ツールが作成できるサービスです。
Interviewzは、操作性がわかりやすく誰でも簡単に高度な診断ツールが作成できるサービスです。
Interviewzの特徴は以下の通りです。
- シンプルな管理画面で直感的に操作できる
- 診断画面にキャラクターの設置や分岐式の設問を作成できる
- 外部サービスとの連携に強い
Interviewzは、シンプルな管理画面で誰でも簡単に操作できるユーザーインターフェースが魅力です。
診断画面中にキャラクターの設置ができたり、分岐式の設問など高度な診断ツールが作成できたりします。
また、外部サービスとの連携に強く、スプレッドシートだけでなくGoogleアナリティクスやGoogleカレンダー、Salesforceなど様々な外部サービスと連携できます。
診断結果の分析だけでなく、営業のアクションにつなげたい方にも非常におすすめの診断ツール作成サービスです。
2.Judge
Judgeは低価格で診断コンテンツを作成できるツールです。無料プランから有料プランまであり、条件分岐やGoogle Analytics連携など基本機能を備えています。最短10分で診断を作成でき、シンプルな操作性が魅力。小規模な診断やテスト運用に適しており、コストを抑えたい企業におすすめです
参照:Judge公式サイト
3.ヨミトル
ヨミトルはクラウド型の診断コンテンツ作成ツールで、10年以上の実績を持つピクルスが開発。多様な診断ロジックを内蔵し、初心者でも直感的な操作で高品質な診断を作成できます。既存の成功事例をひな型として活用でき、企画やデザイン面でも専門サポートを受けられるため、マーケティング成果に直結する診断を低コストで実現可能です。
参照:ヨミトル公式サイト
4.Questant
Questantはマクロミルが提供する診断ツール作成サービス。70種類以上のテンプレートや多様な質問形式を備え、専門知識不要で高度な診断が作成可能。上位プランでは専用の集計ツールも利用でき、詳細な分析や市場調査にも対応します。大規模なデータ収集や分析を重視する企業に最適です。
5.LINE公式アカウント拡張機能【診断Bot】
LINE公式アカウントの拡張機能として利用できる診断Botは、LINE上で手軽に診断コンテンツを提供可能。自動応答やユーザー属性の取得ができ、SNSマーケティングやリード獲得に効果的。LINEユーザーへのリーチを重視するビジネスにおすすめです。
参照:LINE公式アカウント拡張機能【診断Bot】公式サイト
6.Googleフォーム
Googleフォームは無料で利用でき、分岐型の診断テストも作成可能。シンプルなUIで手軽に設問作成や結果集計ができ、Googleスプレッドシートと連携してデータ管理も容易。コストをかけずに簡単な診断やアンケートを実施したい場合に適しています。
▼以下の資料は、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較した資料です。ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。 類似サービスの比較を行いたい方は、ぜひ参考にしてください。
診断コンテンツを作る際の重要ポイント3つ

診断コンテンツを作る上で必ず覚えておきたい3つのポイントについて紹介します。
制作事例で紹介したような質の高い診断コンテンツを新しく作成する上で、以下の3つのポイントを参考にするのが良いでしょう。
- 診断コンテンツ作成ツールを活用する
- 診断コンテンツ作成の目的を明確にしておく
- 診断コンテンツをSNSでシェアしてもらう
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
ポイント1:診断コンテンツ作成ツールを活用する
診断コンテンツの作成方法は以下の3つが存在します。
- プログラミングを行い自作する
- 外注して診断コンテンツを作成してもらう
- 診断コンテンツ作成ツールを活用して作成する
それぞれのメリット・デメリットを表にまとめました。
| 作成方法 | メリット・デメリット | |
|---|---|---|
| メリット | デメリット | |
| 1.プログラミングを行い自作する | コストがかからない | 作成に時間と手間がかかる 誰でも作成できるわけではない |
| 2.外注して診断コンテンツを作成してもらう | 手間がかからない | 数十万円以上のコストがかかる |
| 3.診断コンテンツ作成ツールを活用して作成する | 誰でも簡単に作成できる 導入がかんたん |
多少のコストがかかる |
プログラミングを使った自作方法は、コストがかからない代わりに手間と時間がかかり現実的ではありません。
診断コンテンツには制作会社が存在しており、外注することで診断コンテンツ作成の手間を削減できます。
しかし、診断コンテンツ作成を外注すると数十万円〜数百万円のコストがかかる可能性が高いです。
そのため、診断コンテンツ作成ツールを活用するのが最もおすすめの方法です。
診断コンテンツ作成ツールは誰でもかんたんに導入でき、使いやすい管理画面やテンプレートが用意されています。
最初はツールの操作性を覚えるのに時間がかかりますが、月額数千円〜数万円のコストで手軽に利用できるのでおすすめです。
ポイント2:診断コンテンツ作成の目的を明確にしておく
診断コンテンツの作成目的を明確にしておくことが、質の高い診断コンテンツ作成につながります。
具体的には、「自社サービスの認知度アップ」、「サイト流入を増やしたい」などの目的が挙げられます。
例えば複数の自社サービスを取り扱っており認知度アップを狙いたい場合は、ユーザーに興味を持ってもらいやすいフローチャート形式のロジックを使うなどの方法です。
診断コンテンツの目的を明確にしておかないと、間違ったロジックの使用により満足の行く診断コンテンツが作成できない可能性もあるので注意しましょう。
ポイント3:診断コンテンツをSNSでシェアしてもらう
診断コンテンツを作成して自社サイトに設置するだけでは、サイト流入やサービスの認知度アップを狙うには時間がかかります。
診断コンテンツを多くの方に利用してもらうには「SNSの活用」がおすすめです。
具体的には、「診断結果画面にSNSのシェアボタンを設置する」、「SNS公式アカウントで診断コンテンツをおすすめする」などの方法が挙げられます。
SNSを活用することで、興味を持ったユーザーが診断コンテンツを利用してくれてシェアしてくれる可能性が高まります。
その結果、診断コンテンツの利用者が増えてサイト流入やサービス認知度アップを狙えるでしょう。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。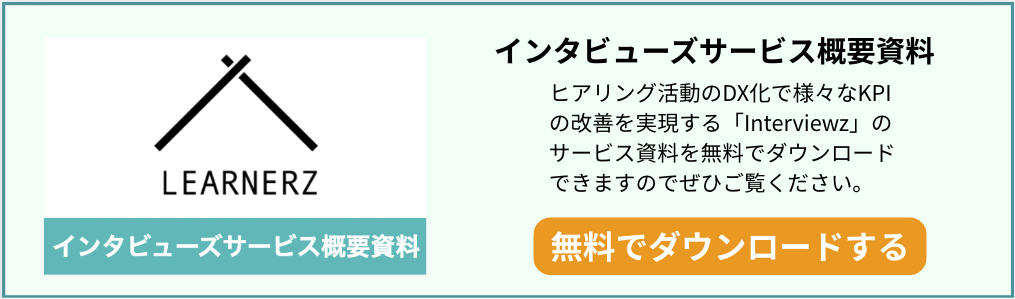
診断コンテンツの活用法のまとめ
今回の記事では、診断コンテンツを使った5つの制作事例や診断コンテンツの効果的な使い方、3つの作り方について解説しました。
診断コンテンツは様々な場面で利用されており、大手企業でも採用している場合があります。
診断コンテンツを活用すれば、自社サービスの認知度アップやサイト流入数アップを狙えるでしょう。
また、診断コンテンツを作る際には目的を明確にして適切なロジックで作成する必要があります。
目的を明確にしないまま診断コンテンツ作成に進んでしまうと、間違ったロジックで診断コンテンツを最適に活用できない可能性があります。
診断コンテンツを作成するには、【Interviewz(インタビューズ)】のような診断コンテンツ作成ツールを利用するのがおすすめです。
管理画面がシンプルで設問のカスタマイズ性も高く、無料期間が存在するので診断コンテンツ作成を検討している方はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか?
インタビューズは14日間のトライアル期間中もすべての機能を無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。
▼Interviewz(インタビューズ)に新機能が追加され、CSSカスタマイズとHTMLタグ埋め込みが可能となりました。これにより、自社ブランドのデザインに合わせた診断・ヒアリングページを最短1日で構築できます。
フォントやカラーの変更、アニメーション追加、外部ツールや分析コードの設置も簡単で、SEO対策やCVR向上、データ活用がスピーディーに行えます。さらに、プレビュー機能で事前確認し即時反映できるため、マーケティング施策の自由度と実行スピードが大幅に向上し、リード獲得や効果測定改善を加速させることが可能です。
ぜひ下記の資料から、インタビューズの詳しい機能をご確認ください。
インタビューズは14日間のトライアル期間中もすべての機能を無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。