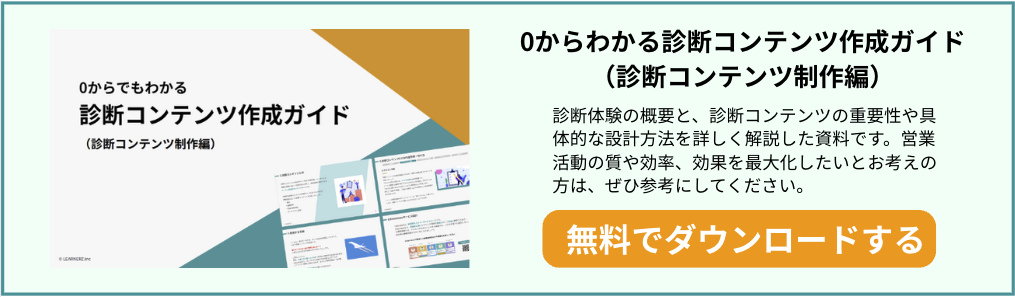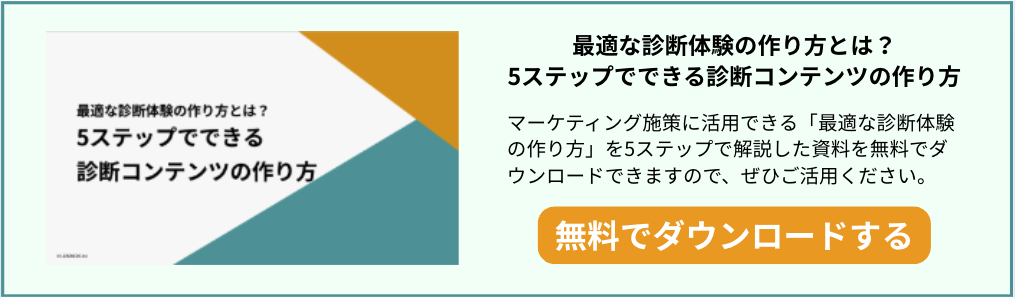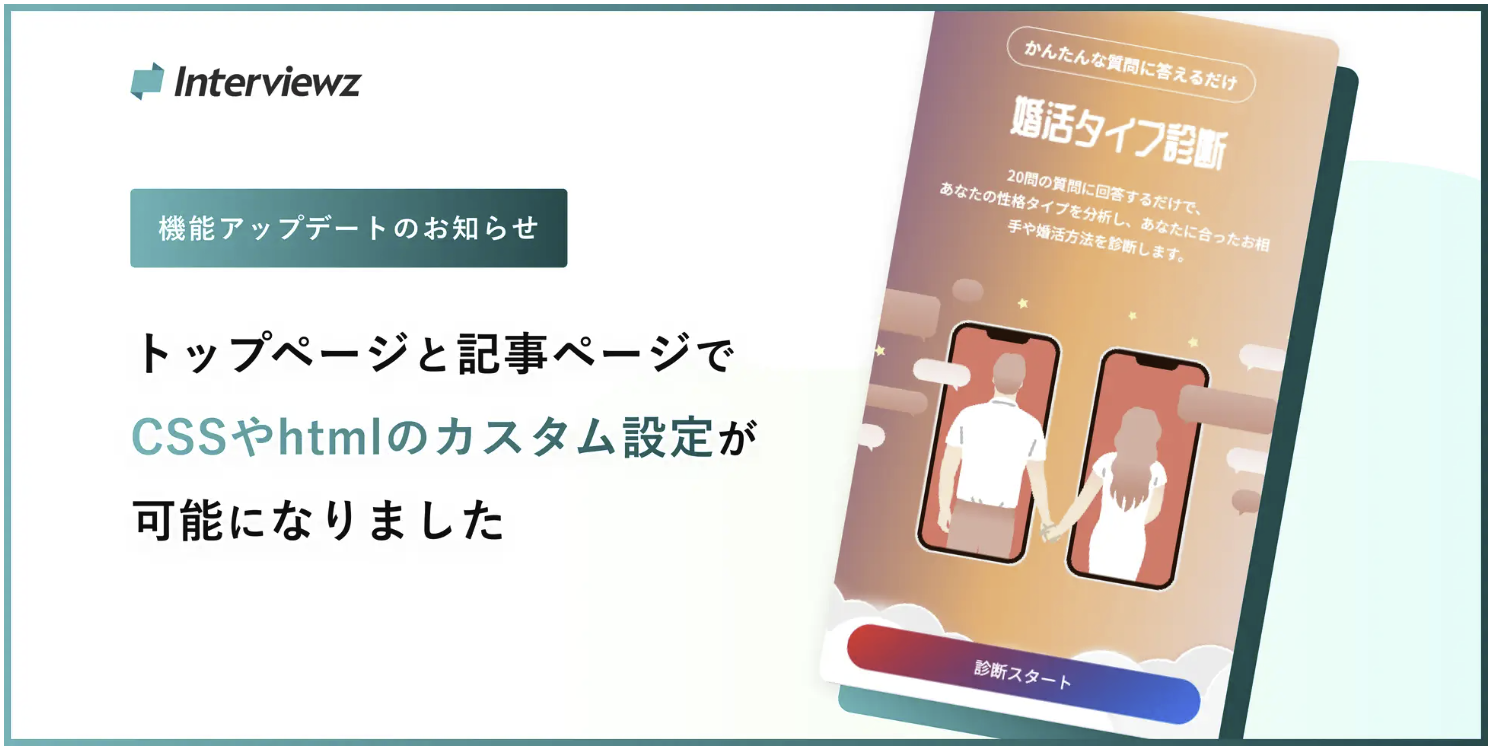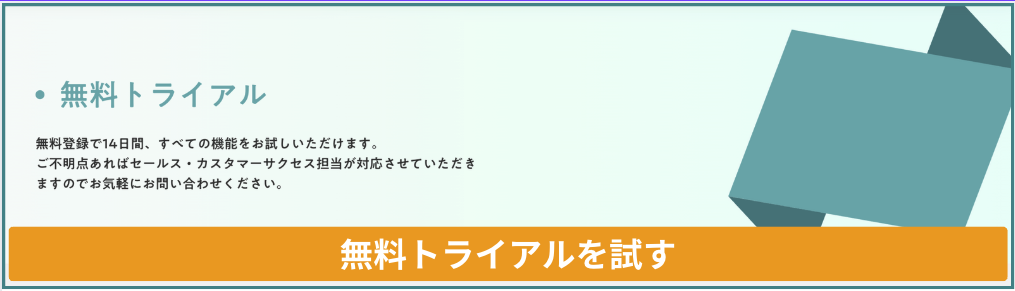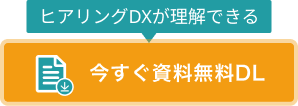診断ツールの作り方とおすすめツール6選|導入するメリットや成功事例も解説
- 2023/03/08
- 2025/08/24

目次
診断ツールは、ユーザーの興味を引き付ける参加型のコンテンツとして、多くの企業が活用しています。特に、マーケティング戦略の一環として導入することで、顧客の傾向を把握し、パーソナライズされたサービスの提供が可能です。
しかし、診断ツールを効果的に設計するには、適切なテーマ設定や操作性の向上が欠かせません。また、成功事例を参考にすることで、より効果的な活用方法が見えてくるでしょう。
そこで今回は、診断ツールの作り方とおすすめツール6選だけでなく、導入するメリットや成功事例も徹底解説しますので、ぜひ参考にしてください。
診断ツールとは?基礎知識を解説

診断ツールの特徴と仕組み
診断ツールとは、Web上で質問に回答するだけでユーザーに最適な結果やアドバイスを提示してくれるデジタルコンテンツです。多くの場合、複数の質問にYES/NOや選択肢で答えることで、ユーザーのニーズ・性格・課題を可視化します。
システムは、事前に設定したロジックやアルゴリズムに従って結果を自動で生成します。これにより、一人ひとりに合わせた提案や商品レコメンド、行動変容を手軽に促進できる点が大きな特徴です。
また、収集したユーザーの回答データを活用し、マーケティングや商品開発に生かすことも可能です。
業界別の診断ツール活用ニーズの変化
近年、診断ツールは業界を問わず多様な場面で導入が進んでいます。
- BtoC分野(化粧品・健康食品・教育・保険など)では、パーソナライズされた商品提案や会員獲得、リードジェネレーションのために活用する企業が増加中です。
- BtoB領域でも、営業商談の前段階でニーズ顕在化や自己診断によるリード育成ツールとしての導入が進んでいます。
- 採用や人材業界では、適性診断、キャリア診断など、求職者や従業員向けのフィードバックとして広がっています。
従来は「エンタメやSNS向け」が主流でしたが、近年は企業の業務効率化やマーケティング、顧客体験向上のために、より高機能・高精度な診断ツールへの需要が高まっています。
診断ツールが求められる理由とは
診断ツールが近年注目を集める理由には、以下のような点が挙げられます。
ユーザーの関心を引く体験型コンテンツである
診断ツールは、一般的な情報提供とは異なり、ユーザー自身が積極的に参加できるコンテンツです。この体験型の要素が、興味を持ちやすく、最後まで回答を続けるモチベーションにつながります。
簡単に自己分析や商品選びができる
性格診断や適職診断、商品レコメンド診断など、ユーザーのニーズに応じた診断が可能であり、情報収集の手間を省くことができます。特に、購買行動につながる診断ツールは、ECサイトでのコンバージョン率向上にも貢献します。
SNSでの拡散力が高い
診断結果を簡単にシェアできる仕組みを持たせることで、自然にSNSで話題になりやすくなります。特に、ユニークな診断結果や共感されやすい診断テーマは、多くのユーザーに共有され、ブランド認知拡大につながります。
データ分析に活用できる
ユーザーの回答データを収集することで、市場のトレンドや顧客の嗜好を分析でき、今後のマーケティング戦略に活かすことができます。特に、顧客の購買行動や興味関心の可視化が可能になるため、ターゲティング広告にも活用可能です。
このように、診断ツールは企業にとってマーケティングの新たな手段として非常に効果的な施策といえます。
診断ツールの主な種類と特徴
診断ツールにはさまざまな種類があり、目的に応じて適切なものを選択することが重要です。以下の表で主要な診断ツールの種類と特徴をまとめました。
| 診断ツールの種類 | 特徴 | 主な活用用途 |
|---|---|---|
| 性格診断ツール | ユーザーの特性や行動パターンを分析し、結果を提供 | エンターテイメント、SNS拡散、自己分析コンテンツ |
| 適職診断ツール | ユーザーの嗜好や強みから適した職業を提案 | 就職・転職サイト、キャリア支援サービス |
| 商品レコメンド診断 | 質問に基づいて最適な商品やサービスを提示 | ECサイト、ネットショップ、パーソナライズマーケティング |
| ライフスタイル診断 | ユーザーの価値観や生活スタイルを分析 | ブランドマーケティング、ターゲット層の理解促進 |
| マーケティング診断ツール | 市場分析や顧客層の傾向を診断 | 企業のターゲティング広告施策、販売戦略立案 |
診断ツールを活用することで、ユーザーとの関係性を深め、ブランドの認知拡大やマーケティングの強化につなげることができます。目的に応じた種類を選び、適切に運用することで、より高い効果を得ることができるでしょう。
診断ツールの作り方と設計のポイント

診断ツールを成功させるには、企画段階から設問の設計、結果表示の工夫まで、慎重に設計することが重要です。ここでは、診断ツールの作成において押さえるべきポイントを詳しく解説します。
診断ツールの企画段階で考えるべきこと
診断ツールを企画する際は、まず目的を明確にすることが重要です。診断ツールを何のために作るのかを定めることで、設計の方向性が決まります。具体的には以下の点を考慮しましょう。
ターゲット層の明確化
診断ツールを利用するユーザー層は誰かを明確にし、興味を引くテーマを設定します。例えば、就職活動中の学生向けなら「適職診断」、ECサイトなら「おすすめ商品診断」などが適しています。
診断結果の目的設定
診断結果をどう活用するかを考えます。マーケティング目的なら、パーソナライズされた商品提案を行う、ブランディング目的なら、診断結果をSNS拡散につなげるなど、用途に合わせた設計が必要です。
ユーザーの参加動機を設計
ユーザーが診断を受けたくなる動機を作ることが重要です。「あなたの性格タイプが分かる!」「最適なスキンケアアイテム診断」など、興味を引くキャッチコピーを設定すると効果的です。
これらのポイントを押さえることで、診断ツールの企画をスムーズに進めることができます。
設問設計のコツと分岐式の活用
診断ツールの設問設計は、ユーザーの回答を的確に分析し、最適な診断結果を提示するための重要なステップです。設問設計のポイントを以下にまとめます。
設問数は適切に設定する
診断ツールの離脱率を抑えるため、設問数は5~10問程度が理想です。長すぎると途中離脱しやすくなるため、簡潔で直感的な質問を心がけます。
回答の選択肢を工夫する
ユーザーが迷わず答えられるよう、明確な選択肢を用意します。例えば、「はい/いいえ」ではなく、「よく当てはまる/やや当てはまる/あまり当てはまらない」など段階的な回答を用意すると精度が向上します。
分岐式を活用する
診断の精度を向上させるために、ユーザーの回答によって質問が変化する分岐式を活用します。例えば、「あなたの職業タイプは?」という質問で「クリエイティブ系」を選んだ場合、次の質問をデザイン職に関連したものにするなど、個別化を図ります。
分岐式を活用することで、診断結果の質を高め、ユーザーにとってより有益なコンテンツを提供できます。
診断結果の表示方法とユーザー満足度向上の工夫
診断結果の表示は、ユーザーが満足し、シェアしたくなる設計にすることが重要です。以下のポイントを押さえましょう。
診断結果は視覚的に表現する
テキストのみではなく、アイコンやグラフを活用すると、分かりやすい診断結果が得られます。例えば、性格診断では「〇〇タイプ」などのラベルをアイコン付きで表示すると、ユーザーの理解が深まります。
結果の説明を充実させる
診断結果が簡潔すぎると満足度が低くなるため、結果の解説を充実させましょう。「あなたは〇〇タイプです。このタイプの特徴は~」など、詳細な説明を加えることで、納得感を与えることができます。
SNSシェア機能を組み込む
診断結果を簡単にSNSで共有できるようにすると、拡散率が向上します。特に、ユニークな診断結果やキャッチーなタイトルを設定することで、話題性を持たせることができます。
診断結果の表示方法を工夫することで、ユーザー満足度を高め、診断ツールの効果を最大限発揮させることができます。
診断ツールの作成において、企画・設問設計・結果表示のそれぞれの段階で適切な工夫を施すことで、ユーザーにとって魅力的なコンテンツとなるでしょう。
▼以下は、診断体験の概要と、診断コンテンツの重要性や具体的な設計方法を詳しく解説した資料です。営業活動の質や効率、効果を最大化したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
診断ツールの活用メリットとビジネス効果

診断ツールを活用すると、企業にとってさまざまなメリットが得られます。
具体的なメリットは主に以下の4つです。
-
リード獲得・顧客情報の収集
-
購買率・CVR向上への貢献
-
ブランド認知・SNS拡散効果
-
顧客満足度・ロイヤルティ向上
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
1.リード獲得・顧客情報の収集
診断ツールは、ユーザーが診断結果を得るために必要な情報を入力する仕組みを活用し、自然な形でリード情報や顧客データを収集できます。これにより、従来の問い合わせフォームよりも高いコンバージョン率が期待でき、質の高いリストを獲得可能です。また、ユーザーの興味関心や属性データも取得できるため、今後のマーケティング施策やパーソナライズされたアプローチに活用しやすくなります。
2.購買率・CVR向上への貢献
診断ツールは、ユーザーのニーズや課題に合わせた最適な商品やサービスをレコメンドできるため、購買意欲を高め、購入や申し込みへの誘導がスムーズになります。ユーザーごとにパーソナライズされた提案を行うことで、意思決定のハードルを下げ、結果としてCVR(コンバージョン率)の向上に大きく寄与するでしょう。特にECサイトやサブスクリプションサービスで高い効果が期待されています。
3.ブランド認知・SNS拡散効果
診断ツールは、ユーザーが楽しみながら参加できるコンテンツとして拡散性が高く、SNSでのシェアや口コミを促進します。診断結果をSNSで共有する仕組みを設けることで、自然にブランドやサービスの認知拡大が図れます。話題性のある診断コンテンツはバズを生みやすく、新規ユーザーの流入や潜在層へのリーチにも効果的です。
4.顧客満足度・ロイヤルティ向上
診断ツールを活用することで、ユーザーは自分に合った情報やサービスを受け取ることができ、満足度が向上します。パーソナライズされた体験を提供することで、顧客とのエンゲージメントが強化され、再訪率やリピート利用の増加、ブランドへのロイヤルティ向上にもつながります。顧客の声を反映した診断内容の改善も、長期的な関係構築に有効です。
▼下記からは、Interviewzのデジタルギフト付きのアンケートに関する詳しい内容を無料でダウンロードできます。
このサービスを活用することで、通常のアンケートに比べて平均回答率が約2.8倍に改善された事例があります。ヒアリングやアンケートを効率的・効果的に改善したいとお考えの方は、ぜひご参照ください。
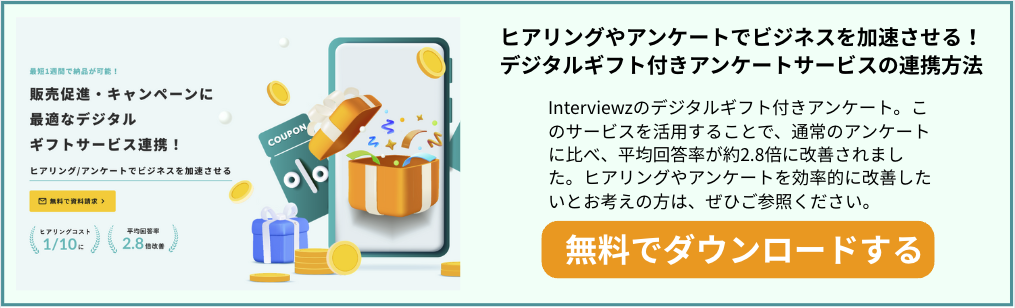
診断ツールを簡単に作成できるおすすめサービス6選
診断ツールを簡単に作成できるサービスを知っておけば、自分に合った最適なサービスを利用して高度な診断ツールを作成できるでしょう。
以下では、おすすめの診断ツール作成サービスを6つ紹介します。
1.Interviewz
 Interviewzは、操作性がわかりやすく誰でも簡単に高度な診断ツールが作成できるサービスです。
Interviewzは、操作性がわかりやすく誰でも簡単に高度な診断ツールが作成できるサービスです。
Interviewzの特徴は以下の通りです。
- シンプルな管理画面で直感的に操作できる
- 診断画面にキャラクターの設置や分岐式の設問を作成できる
- 外部サービスとの連携に強い
Interviewzは、シンプルな管理画面で誰でも簡単に操作できるユーザーインターフェースが魅力です。
診断画面中にキャラクターの設置ができたり、分岐式の設問など高度な診断ツールが作成できたりします。
また、外部サービスとの連携に強く、スプレッドシートだけでなくGoogleアナリティクスやGoogleカレンダー、Salesforceなど様々な外部サービスと連携できます。
診断結果の分析だけでなく、営業のアクションにつなげたい方にも非常におすすめの診断ツール作成サービスです
2.Judge
Judgeは低価格で診断コンテンツを作成できるツールです。無料プランから有料プランまであり、条件分岐やGoogle Analytics連携など基本機能を備えています。最短10分で診断を作成でき、シンプルな操作性が魅力。小規模な診断やテスト運用に適しており、コストを抑えたい企業におすすめです
参照:Judge公式サイト
3.ヨミトル
ヨミトルはクラウド型の診断コンテンツ作成ツールで、10年以上の実績を持つピクルスが開発。多様な診断ロジックを内蔵し、初心者でも直感的な操作で高品質な診断を作成できます。既存の成功事例をひな型として活用でき、企画やデザイン面でも専門サポートを受けられるため、マーケティング成果に直結する診断を低コストで実現可能です。
参照:ヨミトル公式サイト
4.Questant
Questantはマクロミルが提供する診断ツール作成サービス。70種類以上のテンプレートや多様な質問形式を備え、専門知識不要で高度な診断が作成可能。上位プランでは専用の集計ツールも利用でき、詳細な分析や市場調査にも対応します。大規模なデータ収集や分析を重視する企業に最適です。
5.LINE公式アカウント拡張機能【診断Bot】
LINE公式アカウントの拡張機能として利用できる診断Botは、LINE上で手軽に診断コンテンツを提供可能。自動応答やユーザー属性の取得ができ、SNSマーケティングやリード獲得に効果的。LINEユーザーへのリーチを重視するビジネスにおすすめです。
参照:LINE公式アカウント拡張機能【診断Bot】公式サイト
6.Googleフォーム
Googleフォームは無料で利用でき、分岐型の診断テストも作成可能。シンプルなUIで手軽に設問作成や結果集計ができ、Googleスプレッドシートと連携してデータ管理も容易。コストをかけずに簡単な診断やアンケートを実施したい場合に適しています。
診断ツールを活用したマーケティングの成功事例3つ

診断ツールは、ユーザーに自分のニーズや嗜好、性格などを診断して結果を提示するオンラインツールのこと。診断ツールは、ユーザーの興味を引き、ブランドや商品に関する情報を提供する効果的なマーケティング手法の一つです。
以下では、診断ツールを活用したマーケティング事例を3つ紹介します。
1. ユニクロの「パーソナルカラー診断」
ユニクロは、自分のパーソナルカラーを診断して、その色に合った服をオススメする「パーソナルカラー診断」を実施しました。
ユーザーは、自分の顔写真をアップロードするか、肌色や髪色などの質問に答えることで、自分のパーソナルカラーを4つのタイプ(スプリング、サマー、オータム、ウィンター)から判定できます。
診断結果では、自分のパーソナルカラーに合ったユニクロの商品が紹介され、そのままオンラインショッピングにつなげることができます。この診断ツールは、ユーザーに自分に似合う服を見つける楽しさを提供し、ユニクロの商品への関心や購買意欲を高める効果がありました。
2. ロート製薬の「目の疲れ度チェック」
ロート製薬は、目の疲れや乾燥に悩む人に向けて、「目の疲れ度チェック」を実施しました。ユーザーは、スマートフォンやパソコンなどの画面使用時間や目の不調などの質問に答えることで、自分の目の疲れ度を5段階で判定できます。
診断結果では、自分の目の状態に応じた目薬やサプリメントなどの商品が紹介され、そのままオンラインショッピングにつなげることができます。
この診断ツールは、ユーザーに自分の目の健康状態を気づかせ、ロート製薬の商品への信頼感や購買意欲を高める効果がありました。
3. サントリーの「お酒好み診断」
サントリーは、自分のお酒好みを診断して、その嗜好に合ったお酒や料理をオススメする「お酒好み診断」を実施しました。
ユーザーは、自分が好きな味や香りなどの質問に答えることで、自分のお酒好みを4つのタイプ(甘い派、辛い派、香り派、すっきり派)から判定できます。診断結果では、自分のお酒好みに合ったサントリーの商品や料理が紹介され、そのままオンラインショッピングやレシピ検索につなげることができます。
この診断ツールは、ユーザーに自分に合ったお酒や料理を見つける楽しさを提供し、サントリーの商品への関心や購買意欲を高める効果がありました。
診断ツールの活用場面と実際の活用事例7つ

診断ツールには、自社サービスの認知度アップや成約率アップなど様々な効果があり、大手企業などでも活用シーンが増えています。
代表的な活用事例として以下の7つのジャンルをかいせつします。
- 転職診断
- 婚活診断
- おすすめクレジットカード診断
- 旅行プラン診断
- 結婚式プラン診断
- 組織診断(組織サーベイ)
- 働き方診断(従業員サーベイ)
活用事例①:転職診断
転職は人生を大きく左右するライフイベントの一つです。
相性の良い転職先を見つけることで、今後の人生を豊かに生きられる可能性が高まります。
しかし、「どの業界に転職したら良いかわからない」、「適正のある職種が知りたい」と考えている方も多いでしょう。
マイナビ転職では、20の質問に答えるだけで簡単に適職を診断してくれる診断ツールが公開されています。
自分の考え方と相性の良い職種を見つけて、理想の転職を成功させやすくなるでしょう。
活用事例②:婚活診断
診断ツールは婚活の場面でも活用されています。
例えば、婚活サービス【楽天オーネット】では、質問に回答するだけで簡単に自分に合った婚活タイプなどがわかります。
結婚は人生でも1,2を争うビッグイベントでもあると同時に、今後の人生が大きく左右されるでしょう。
自分のライフスタイルに合った婚活をしたい方は、楽天オーネットの婚活タイプ診断を利用することで、最適な婚活タイプがわかります。
「良い出会いがない」、「結婚を見据えてお付き合いできる相手を探している」という方は利用してみることをおすすめします。
活用事例③:おすすめクレジットカード診断
クレジットカード選びに迷った経験がある方も多いのではないでしょうか?
クレジットカードは様々な会社が参入しており、百種類以上ものクレジットカードが存在します。
自分に合ったクレジットカードを探すのは大変です。
お金に関連する情報発信をしているWebメディア【NETMONEY】では、10秒で結果がわかるクレジットカード診断を実施しています。
簡単な質問に回答するだけで、おすすめのクレジットカードをランキング形式で紹介してくれます。
クレジットカード選びに迷っている方は、一度利用してみるのが良いでしょう。
活用事例④:旅行プラン診断
旅行したいと考えたときに、具体的な旅行プランをどうするか悩んだ経験はありませんか?
日本旅行が実施している旅行プラン診断では、簡単な質問に答えるだけで自分の希望に合った旅行先をおすすめしてくれます。
診断結果で出てきた旅行先のプランも簡単に検索できるので、旅行プランを立てるのに悩んでいる方はぜひ一度利用してみることをおすすめします。
活用事例⑤:結婚式プラン診断
結婚式は女性にとって最も大きいライフイベントの一つといわれています。
結婚式では、プランによって数十万~数百万円以上の費用がかかります。
そのため、どのプランを選ぶのが良いか迷う方も多いでしょう。
ぐるなびウェディングが実施している結婚式プラン診断では、簡単な質問に答えるだけで自分の理想の結婚式プランがわかります。
診断結果を元にした会場を検索できるので、これから結婚式を考えている方はぜひ一度利用してみることをおすすめします。
活用事例⑥:組織診断(組織サーベイ)
組織診断(組織サーベイ)とは、組織の現状や課題を客観的に把握するためのツールです。組織のメンバーにアンケートやインタビューを行い、組織の強みや弱み、改善すべき点などを分析します。
組織診断(組織サーベイ)を活用することで、以下のようなメリットがあります。
- 組織のパフォーマンスやエンゲージメントを向上させることができます。
- 組織のコミュニケーションや協働を促進することができます。
- 組織の変革や改革に必要な施策や方針を策定することができます。
活用事例⑦:働き方診断(従業員サーベイ)
働き方診断(従業員サーベイ)とは、従業員の働き方や働きがいを評価するためのツールです。
従業員にアンケートやインタビューを行い、従業員の満足度やモチベーション、ストレスや負担などを測定します。働き方診断(従業員サーベイ)を活用することで、以下のようなメリットがあります。
- 従業員のエンパワーメントやロイヤルティを高めることができます。
- 従業員の健康や安全を保障することができます。
- 従業員の離職率や欠勤率を低減することができます。
診断ツールの活用事例と成功パターン

BtoC向け商品レコメンド事例
化粧品やアパレルなどのBtoC業界では、診断ツールを活用してユーザーの悩みや好みに合わせた商品を提案する事例が増えています。例えば、肌質診断やファッション診断を通じて、最適な商品をレコメンドし、購入までの導線をスムーズに設計。ユーザーは自分に合う商品を簡単に見つけられるため、満足度と購買率の向上に貢献しています。
BtoBリード獲得・資料請求事例
BtoB分野では、企業向けサービスの診断コンテンツを提供し、課題診断や最適なソリューション提案とともにリード情報を獲得する事例が多く見られます。診断後に詳細な診断レポートやホワイトペーパーをダウンロードできる仕組みを設けることで、質の高い見込み顧客を効率的に獲得し、営業活動の効率化や成約率向上にもつながっています。
SNS拡散型キャンペーン事例
SNSを活用した診断キャンペーンは、ユーザーが診断結果をシェアすることで拡散が促進され、短期間で多くの新規ユーザーを獲得できます。例えば、診断結果をシェアした人の中から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施し、参加率や話題性を高める事例が増加。ブランド認知の拡大やフォロワー獲得にも大きな効果を発揮しています。
実際の企業活用例と成果
大手企業やスタートアップを問わず、診断ツールの導入によってリード獲得数の増加やCVRの向上、SNSでの話題化など、さまざまな成果が報告されています。例えば、ある企業では診断ツールを導入後、月間リード数が2倍に増加し、営業効率も大幅に向上しました。実際のデータやユーザーの声をもとに、継続的な改善を行うことで、さらなる成果を生み出しています。
▼下記の資料では、自社のマーケティング施策に活用できる最適な『診断体験』の作り方を5つのステップで解説しています。
診断コンテンツはユーザー自身の潜在的なニーズを深掘り、自分が求めるサービスや理想像をより明確にできるため、CVRの向上や診断コンテンツを通じてLTVを向上させることが可能です。
自社のサービスで診断体験を通じたユーザー獲得や認知拡大をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
診断ツールの作成には専用サービスの活用がおすすめな理由3つ

診断ツールは専用のサービスを活用すれば簡単に作成できます。
診断ツールを作成するには、外部委託して作成してもらう方法や、HTMLの知識を使って自作する方法などもあります。
しかし、高額な費用がかかったり、専門知識が必要で誰でも作れるわけではなかったりデメリットが多いです。
診断ツール作成サービスは、月額数千円~数万円のコストしかかからず誰でも簡単に診断ツールを作成できます。
診断ツール作成サービスを活用するべき理由は以下の3つです。
- 直感的な操作で簡単に診断ツールを作成できる
- 豊富なテンプレートがありジャンルに合わせて選べる
- 診断結果はデータ上で管理できるので市場調査・商品開発に役立てられる
それぞれの理由について詳しく解説します。
1.直感的な操作で簡単に診断ツールを作成できる
診断ツール作成サービスにおいて一番重要なのは「誰でも簡単に作成できること」です。
簡単に作成できなければ、診断ツール作成サービスを利用する意味がありません。
今回の記事で紹介する診断ツール作成サービスは、直感的な操作で誰でも簡単に作成できます。
診断ツール作成サービスの中には、線で引っ張るだけで最短5分で公開可能なものも存在します。
2.豊富なテンプレートがありジャンルに合わせて選べる
診断ツールの活用場面は会社によって様々です。
ユーザーから飽きられにくい診断ツールを作成するには、豊富なテンプレートが用意された診断ツール作成サービスを利用するのが良いでしょう。
テンプレートの種類が多いと、診断ツールのジャンルに応じて適切なテンプレートを選べます。
今回の記事で紹介する診断ツール作成サービスは、豊富なテンプレートが用意されたものばかりなので安心して利用できます。
3.診断結果はデータ上で管理できるので市場調査・商品開発に役立てられる
診断ツールは市場調査・商品開発の場面でも活用できます。
具体的には、診断ツールで得た診断結果はデータ上で管理できるので、スプレッドシート連携機能などにより複数メンバーで分析できるでしょう。
集計したデータを分析することで、ユーザーが求めているニーズがわかったり、商品開発のアイデアを得られたりするメリットがあります。
▼下記の資料では、実際にアンケートを作成する際に回答率の高いアンケートを作成するために『どんな項目があるばべきか』『回答率の高いアンケートの特徴』など、実例を交えながら解説しいます。
アンケート作成でお悩みのある方は、下記の資料を参考にしながら効果的ななアンケートの作成方法を確認してみてください。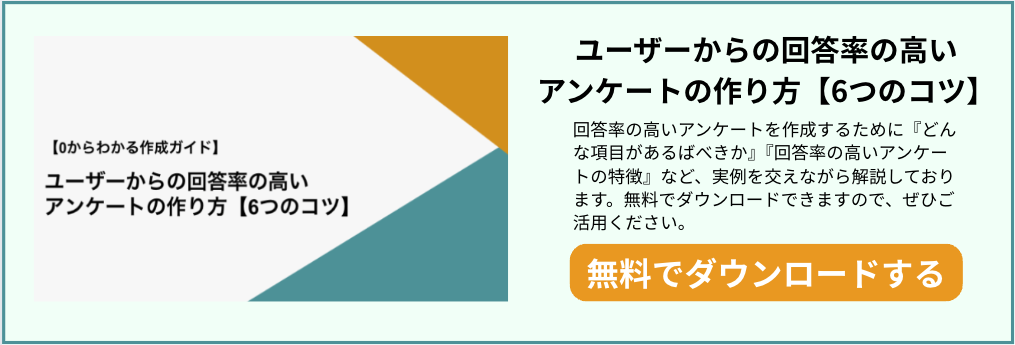
診断ツールを作成するサービスの選び方のポイント5つ
診断ツール作成サービスは様々な種類のものが存在します。
自分に合ったサービスを選ぶことで、適切に活用ができるでしょう。
診断ツール作成サービスの選び方のポイントは以下の5つです。
- 目的に合った機能
- カスタマイズ性
- データの解析機能
- 使いやすさ
- 価格とサポート
それぞれ解説します。
1.目的に合った機能
診断ツールを選ぶ際には、まずそのツールが自分の目的に合った機能を持っているかを確認することが重要です。
例えば、リードジェネレーション、顧客アンケート、スキル評価など、具体的な利用目的に適した機能が備わっていることを確認しましょう。
目的に合ったツールを選ぶことで、効率的なデータ収集と分析が可能となり、ビジネスの成長をサポートします。
2.カスタマイズ性
診断ツールのカスタマイズ性も重要な選定基準です。
自社のブランディングに合わせたデザイン変更や、質問項目の追加・修正が容易にできるツールを選びましょう。
カスタマイズ性が高いツールは、より具体的かつニーズに合った診断を実施することができ、ユーザーエクスペリエンスの向上につながります。
柔軟なカスタマイズが可能なツールは、長期的に見ても価値があります。
3.データの解析機能
診断結果のデータ解析機能が充実しているかも重要なポイントです。
収集したデータを簡単に分析し、グラフやレポートとして出力できる機能があるツールを選ぶと、より効果的なマーケティング戦略を立てることができます。
データ解析機能が豊富であるほど、ビジネスの意思決定に役立つインサイトを得やすくなります。
4.使いやすさ
診断ツールの使いやすさも大切な要素です。
直感的なインターフェースや操作性が優れているツールを選ぶことで、初めて使用する人でもスムーズに設定や運用ができます。
使いやすいツールは、社内での導入が容易で、教育やサポートにかかるコストを削減できます。また、ユーザーエクスペリエンスの向上にも寄与します。
5.価格とサポート
最後に、ツールの価格とサポート体制を考慮しましょう。予算に見合った価格設定であること、そして必要なサポートが受けられるかどうかを確認することが重要です。
価格が適切であれば、長期的な利用が可能となり、サポートが充実していれば、トラブル発生時にも迅速に対応できます。
投資対効果の高いツールを選ぶことが、ビジネスの成功に繋がります。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
診断ツールの導入で注意すべきポイント

1.診断結果を活用し、アクションにつなげること
診断ツールを導入するだけで満足せず、得られたデータをもとに具体的な改善策やアクションプランを策定・実行することが重要です。診断結果を分析し、課題の本質を見極め、定期的に進捗を確認しながら施策を見直すことで、ツールの導入効果を最大化できます。
2.利用者の負担やストレスに配慮すること
診断ツールの質問数が多すぎたり、操作が煩雑だったりすると、利用者の負担になり回答率が低下します。アンケートや診断は短時間で簡単に回答できる設計にし、頻度やタイミングにも配慮しましょう。事前の案内やサポート体制も大切です。
3.診断結果を鵜呑みにせず、多角的に判断すること
ツールの診断結果はあくまで一つの指標であり、すべてを鵜呑みにせず他の情報や現場の声と合わせて総合的に判断することが重要です。ツールには得意・不得意分野があるため、見落としや誤認のリスクも考慮し、必要に応じて専門家の意見や追加調査も活用しましょう。
4.コストや運用体制を事前に検討すること
診断ツールの導入には初期費用や運用コストがかかる場合があります。自社の目的や運用体制、必要な機能を明確にし、費用対効果や運用負荷を十分に検討した上で選定・導入することが大切です。
5.セキュリティ・プライバシー対策を徹底すること
収集するデータの機密性や個人情報の取り扱いには十分な注意が必要です。セキュリティ対策やアクセス制御、プライバシーポリシーの明示、法令遵守など、情報管理体制を整えた上で運用しましょう。
▼以下の資料は、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較した資料です。ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。 類似サービスの比較を行いたい方は、ぜひ参考にしてください。
診断ツールの導入でよくある質問Q&A5選

Q1.診断ツールの導入に専門知識は必要ですか?
多くの診断ツールは専門知識がなくても導入できる設計になっています。管理画面で直感的に操作できるものや、テンプレートが用意されているサービスも多く、初めての方でもスムーズに導入可能です。導入サポートやマニュアルも充実しているため、安心して利用を開始できます。
Q2.導入後の運用やメンテナンスは難しいですか?
診断ツールは定期的なメンテナンスや内容の更新が必要ですが、多くのサービスは管理画面から簡単に編集や修正が可能です。FAQやサポート体制が整っているツールを選ぶことで、運用負荷を軽減できます。分析機能を活用し、改善点を見つけやすいのも特徴です。
Q3.セキュリティや個人情報の管理はどうなっていますか?
診断ツールは個人情報を扱う場合が多いため、データの暗号化やアクセス制限、プライバシーポリシーの明示が求められます。信頼できるサービスを選び、法令遵守やセキュリティ対策が徹底されているか事前に確認しましょう。ユーザーへの説明責任も重要です。
Q4.導入にかかる費用や期間はどのくらいですか?
診断ツールの費用や導入期間はサービスによって異なりますが、無料プランやトライアルを用意しているものもあります。最短1分で登録・利用開始できるツールもあり、コストや導入スピードの面でも柔軟に選択できます。
Q5.トラブルが発生した場合のサポート体制は?
万が一トラブルが発生した際は、FAQやサポート窓口を活用できます。多くのサービスがチャットやメール、電話でのサポートを提供しており、トラブル内容に応じて迅速に対応してもらえます。導入前にサポート内容を確認しておくと安心です。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。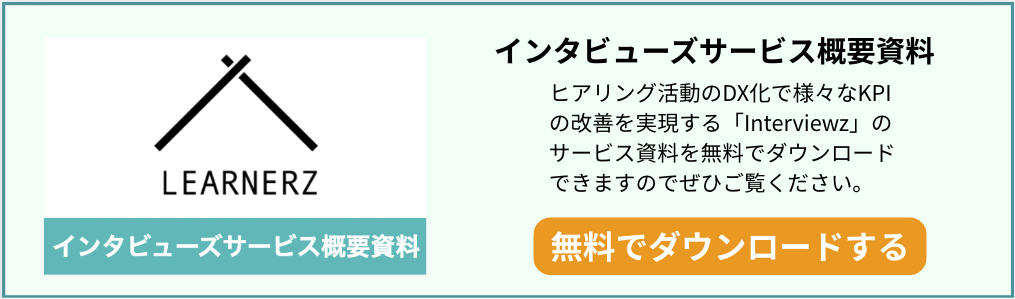
診断ツールの導入にはインタビューズがおすすめ!
インタビューズの診断ツールは、直感的な操作性と高度なカスタマイズ機能を備えており、企業のマーケティング施策に最適です。特に、分岐式の設問を簡単に設定できるため、ユーザーにパーソナライズされた診断を提供可能です。
また、SNSとの連携機能が充実しており、診断結果の拡散を促進し、ブランド認知度の向上につながります。さらに、収集したデータを分析し、ターゲット層の傾向を把握することで、より効果的なマーケティング戦略を立案できます。
診断コンテンツを活用した顧客エンゲージメントの強化を考えている企業にとって、インタビューズは非常に有用なツールとしておすすめです。
▼Interviewz(インタビューズ)に新機能が追加され、CSSカスタマイズとHTMLタグ埋め込みが可能となりました。これにより、自社ブランドのデザインに合わせた診断・ヒアリングページを最短1日で構築できます。
フォントやカラーの変更、アニメーション追加、外部ツールや分析コードの設置も簡単で、SEO対策やCVR向上、データ活用がスピーディーに行えます。さらに、プレビュー機能で事前確認し即時反映できるため、マーケティング施策の自由度と実行スピードが大幅に向上し、リード獲得や効果測定改善を加速させることが可能です。
ぜひ下記の資料から、インタビューズの詳しい機能をご確認ください。
そこで、ぜひこの機会に、14日間の無料トライアルをお試しください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。