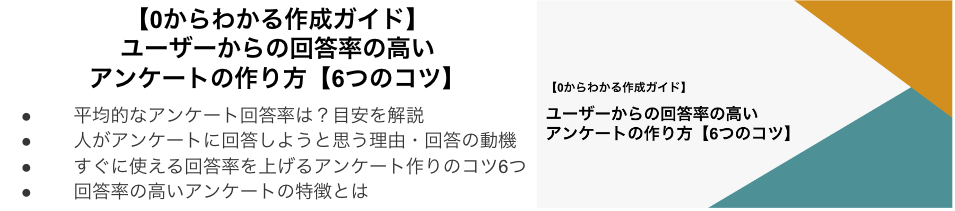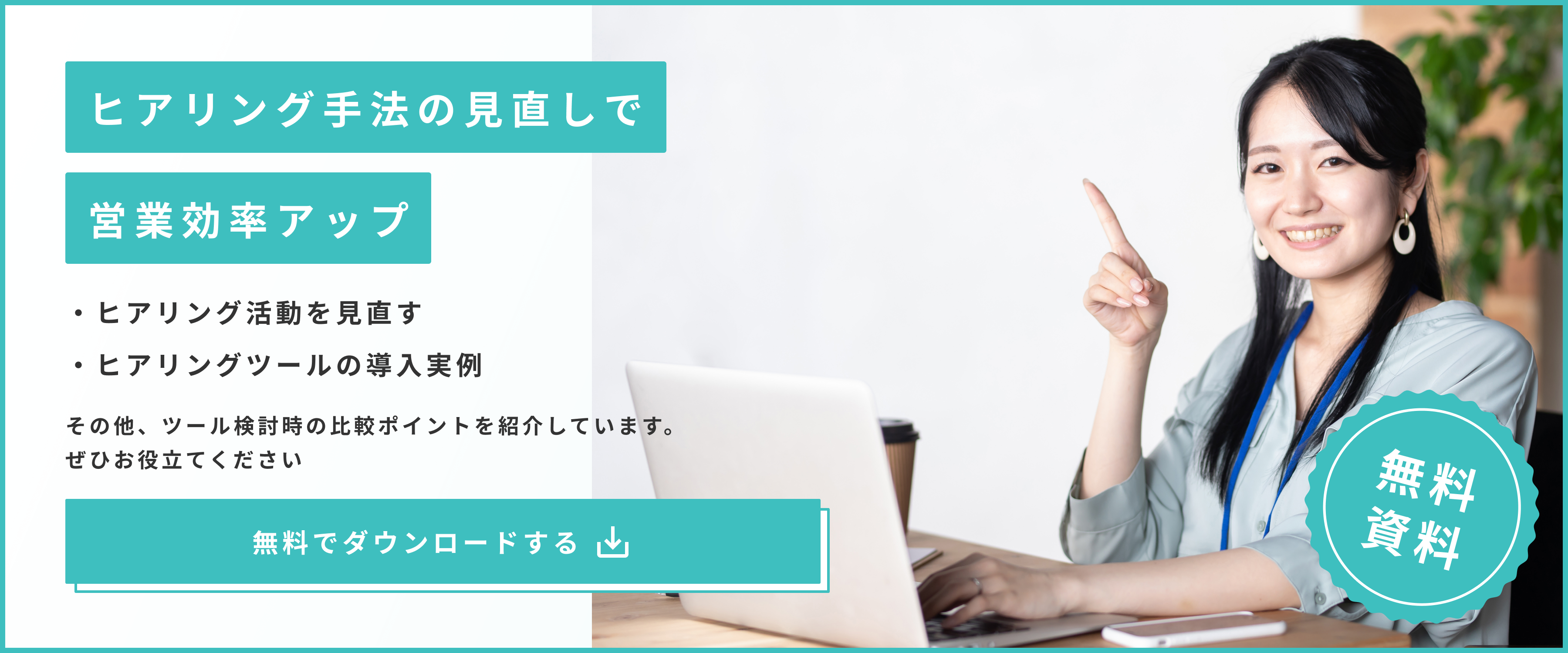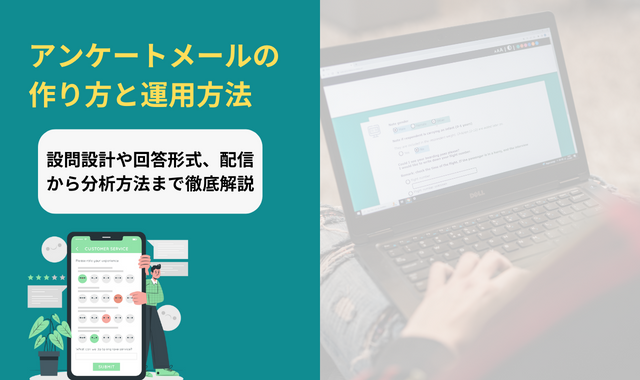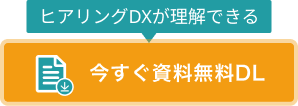問い合わせ業務を効率化する方法|よくある課題とマニュアル作成のコツも解説
- 2023/04/19
- 2025/06/21

目次
問い合わせ業務は、対応の属人化や情報共有の不足などにより、効率化が難しいと感じる企業が多いのが現状です。
マニュアルの未整備や業務フローの複雑化は、対応品質のばらつきや顧客満足度の低下にもつながります。
このような課題を解決するには、分かりやすいマニュアルの整備や業務プロセスの見直し、ITツールの活用が効果的です。
そこで今回は、問い合わせ業務を効率化する方法と、よくある課題やマニュアル作成のコツを解説します。ぜひ参考にしてください。
問い合わせ業務の効率化が求められる背景と課題

問い合わせ対応業務の属人化と非効率さ
問い合わせ対応業務が属人化すると、担当者以外が業務フローやオペレーションを把握できず、非効率な運用が常態化します。この主な原因は、情報共有の仕組みが整っていないことや、業務の専門性が高く他のメンバーが対応しにくいこと、また担当者が多忙でノウハウ伝達の時間が取れないことなどです。
この結果、特定の従業員に業務が集中し、長時間労働や業務過多によるストレス、最悪の場合は離職リスクも高まります。さらに、ノウハウが個人に蓄積されるため、担当者の不在時には業務が滞り、組織全体の生産性や柔軟性が低下します。
情報共有不足による対応品質のばらつき
情報共有が不足すると、問い合わせ対応の品質に大きなばらつきが生じます。属人化した業務では、担当者ごとに対応方法や判断基準が異なり、顧客への説明や対応内容に一貫性がなくなります。また、情報共有の仕組みがない場合、他のメンバーが最新の対応履歴やノウハウにアクセスできず、ミスや二重対応が発生しやすくなるのです。
このような状況が続くと、組織全体の信頼性が損なわれ、顧客からのクレームや不満が増加する原因となります。情報共有を徹底し、誰でも同じ水準で対応できる体制を整えることが、品質安定と業務効率化のポイントです。
顧客満足度や対応スピード低下のリスクがある
問い合わせ対応の属人化や情報共有不足は、顧客満足度の低下や対応スピードの遅延という重大なリスクをもたらします。
特定の担当者に依存した体制では、その人が不在の場合に対応が遅れたり、十分な説明やフォローができず顧客の不満を招きます。また、対応品質のばらつきやミスが増えることで、顧客からの信頼を損ない、最悪の場合は顧客離れや売上減少につながるでしょう。
迅速かつ的確な対応を実現するためには、業務の標準化やナレッジ共有、ITツールの活用を通じて、誰でも一定の品質で対応できる仕組みづくりが不可欠です。
問い合わせ業務を効率化する具体的な方法4つ

1.業務フローの標準化とマニュアル整備
業務フローの標準化は、問い合わせ対応の効率化に不可欠です。まず現状の業務プロセスを調査・分析し、全体の流れや各作業手順を明確化しましょう。
フローチャートや業務フロー図を活用し、現場の目線で直感的に理解できる形で可視化することが重要です。そのうえで、各作業ごとに詳細な手順や注意点、関連資料へのリンクをマニュアル化します。
マニュアルは「原則」を明示し、誰でも同じ手順で対応できる内容にすることで、属人化を防ぎ品質を均一化できます。現場からのフィードバックを反映し、継続的な見直しとアップデートを行うことで、実際の業務に即した「使える」マニュアルとなり、問い合わせ対応の生産性と安定性が向上します。
2.FAQやチャットボットの導入
FAQやチャットボットの導入は、問い合わせ対応の効率化に大きく貢献します。よくある質問や標準的な対応をFAQとして整理・公開することで、顧客や従業員が自己解決できる範囲が広がり、対応件数や負担を大幅に削減可能です。
さらに、チャットボットを導入すれば、24時間自動で一次対応が可能となり、即時回答や案内が実現します。これにより、オペレーターは複雑な問い合わせや個別対応に集中でき、業務全体の生産性が向上するでしょう。
FAQやチャットボットの内容は定期的に見直し、実際の問い合わせ傾向やフィードバックを反映させることで、継続的な改善と顧客満足度の維持が可能です。
3.ヒアリングツール・診断コンテンツの活用法
ヒアリングツールや診断コンテンツを活用することで、問い合わせ内容の事前整理や自動化が進みます。たとえば、インタビューズのヒアリングツールを使えば、顧客や従業員の状況や課題をWebフォームやチャット型の診断コンテンツでヒアリングし、適切な回答や案内を自動で提示できます。これにより、担当者の負担を軽減し、対応の属人化やミスを防止します。また、収集したデータは自動で集計・分析されるため、業務改善やFAQのアップデートにも役立ちます。ヒアリングツールは、問い合わせ業務の効率化と顧客体験の向上を同時に実現する有効な手段です。
4.ITツールによる自動化・一元管理
ITツールを活用した自動化・一元管理は、問い合わせ業務の効率化に直結します。問い合わせ管理システムやCRMを導入することで、問い合わせ内容や対応履歴を一元的に管理でき、情報共有や進捗管理が容易になるからです。
自動返信やチケット発行、対応状況の可視化により、対応漏れや重複を防止し、業務の抜け漏れも減少します。さらに、データ分析機能を使って問い合わせ傾向や課題を把握し、業務改善や人員配置に活かすことも可能です。
ITツールの導入により、業務フロー全体の見える化と標準化が進み、組織全体の生産性と顧客満足度が向上します。
▼以下の資料では、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較しています。
ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。
類似サービスの比較を行いたい方は、1分で比較できる以下の表を是非ご参考ください。
問い合わせ対応マニュアル作成のポイントとコツ

マニュアル作成の基本ステップ
マニュアル作成は、まず業務の全体像を把握し、必要な項目を大分類・中分類・小分類に整理することから始まります。
次に、作成の目的や対象者、運用開始時期を明確にし、スケジュールを立てることが重要です。情報収集と構成の検討を経て、実際に手順や注意点を文書化しましょう。
完成後は現場でテスト運用し、フィードバックを反映して改善します。このような段階を踏むことで、誰でも使いやすく、現場で実際に活用できるマニュアルが完成します。
分かりやすいフォーマットとテンプレートを活用する
分かりやすいマニュアルを作るには、見出しや目次を活用した階層的な構成が有効です。重要な情報は左上や冒頭に配置し、視線の動きを意識したレイアウトにします。文字の装飾やインデント、箇条書きを適切に使い、情報の整理と強調を図るのも有効です。
テンプレートを活用することで、全体のフォーマットが統一され、誰が作成しても一定の品質が保てます。検索性を高める工夫や、Q&A形式のページを設けるのも効果的です。
図解やフローチャートで視認性を高める
業務全体の流れや複雑な手順は、図解やフローチャートを使って視覚的に整理します。
フローチャートは、大分類から小分類までの業務を階層化し、対応の流れを一目で把握できるようにするのがポイントです。図やイラストを挿入することで、初心者でも直感的に理解しやすくなり、マニュアルの活用率が向上します。
特にイレギュラー対応や分岐が多い業務では、図解を活用することでミスや混乱を防止できます。
継続的な見直しとアップデートを繰り返す
マニュアルは一度作成して終わりではなく、現場の声や業務の変化に応じて定期的に見直し、アップデートすることが重要です。
運用開始後は、利用者からのフィードバックや業務改善の要望を集め、内容の修正や追加を行いましょう。責任者を決めて管理体制を整えることで、変更点の反映や現場への周知がスムーズになります。
このような継続的な改善が、実際に役立つマニュアルの維持と業務効率化につながります。
▼下記からは、ユーザーからの回答率の高いアンケートの作り方のコツを無料でダウンロードできます。
この資料を活用することで、平均的なアンケートの回収率や、答えたくなるアンケートの作り方のコツなどを詳しく理解することが可能です。
自社のアンケート内容を効果的に改善したいとお考えの方は、ぜひご参照ください。
問い合わせ業務における課題を解決した事例6つ
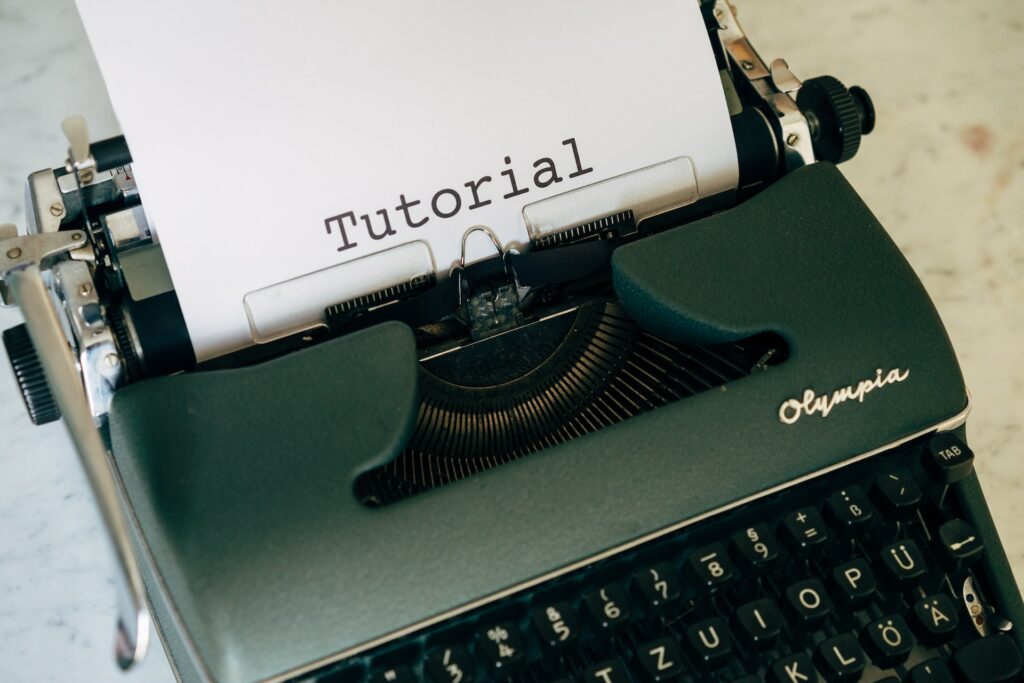
問い合わせ業務に関する課題は、どの企業でも一度は抱えたことがあるといっても過言ではありません。
とはいえ課題を解決してきた企業は数々あり、これから問い合わせ対応の効率を検討している方は成功事例を参考にすることをおすすめします。
ここでは、問い合わせ業務の課題を解決した成功事例を6つ紹介します。
株式会社ヤッホーブルーイング
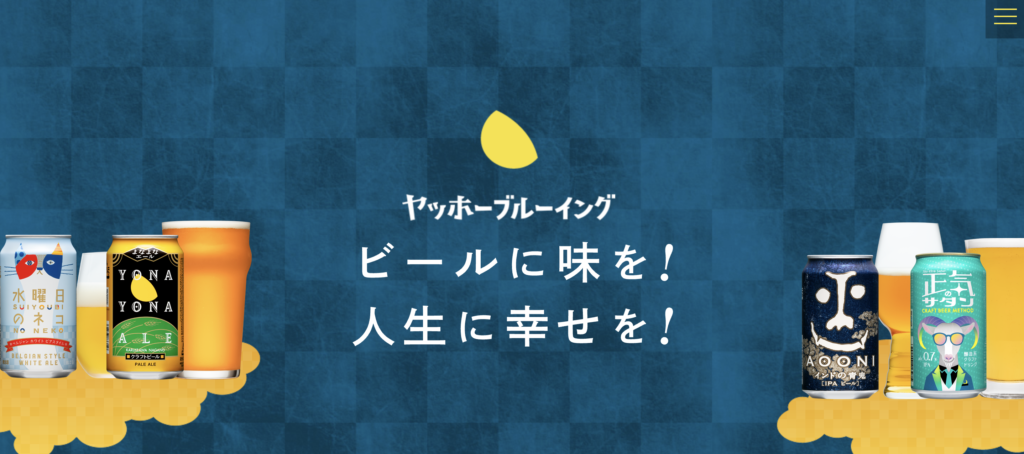
引用元:株式会社ヤッホーブルーイング
株式会社ヤッホーブルーイングでは、最善の対応を行うことを目標にしているものの、対応に遅れてしまうことが課題でした。
問い合わせを受けてメール返信を行う前には、過去の注文履歴やメールをチェックする流れとなっており、このフローに時間がかかってしまうケースが多発していました。
問い合わせ管理システムを導入してからは、メールの確認画面からすぐに対象者の注文情報ページにアクセスできるようになりました。
顧客情報を確認するための流れを効率化でき、問い合わせ業務の対応時間を大幅に削減しています。
株式会社シェアリングエネルギー

引用元:株式会社シェアリングエネルギー
株式会社シェアリングエネルギーは、顧客用とハウスビルダー用の2つのGmailアカウントを使ってメールを管理していました。
担当スタッフごとにメールを手動で分別しており、メールの振り分けで30分〜1時間ほどかかっていた点が過去の課題です。
さらにどの担当スタッフに振り分ければ良いかわからないメールも存在しており、対応漏れによるクレームも来ていました。
問い合わせ管理システムの導入後、メールが自動で振り分けられるので愛朝行うメールの確認業務は10分程度におさまりました。
以前まで1週間ほどかかっていた問い合わせの返信は、遅くても2日〜3日で返信できるようになっています。
弁護士ドットコム株式会社

引用元:弁護士ドットコム株式会社
弁護士ドットコム株式会社では、ユーザー数の増加に伴って対応に遅れたり、対応漏れが生じたりしていました。
問い合わせが来て時間が経ってから気づくこともあり、他のスタッフとの情報共有が十分にされていなかった点が課題です。
システムを導入してからは、対応できていないメールを一目で確認できるようになりました。
それに伴い対応遅れや対応漏れなどの課題はすぐに解消され、未対応の問い合わせをゼロにすることで仕事が全体的に回るようにもなりました。
株式会社リンク

引用元:株式会社リンク
株式会社リンクでは、個人メールアドレスで顧客とやり取りを行っており、メールの見落としがよく起こる点が課題でした。
顧客からの依頼を見逃してしまうことも多発していました。
問い合わせ業務の効率化を行ってから、対応できているか状況を一目で確認できるようになり、メールの見落としがなくなりました。
問い合わせ対応が完了したメールは、すぐに「対応完了」の欄に移動するようルールをあらためて定めました。
株式会社日本橋夢屋

引用元:株式会社日本橋夢屋
株式会社日本橋夢屋では、特定のスタッフが問い合わせ業務を行っていたので、業務の属人化が最大の課題でした。
そのため担当スタッフが休みの日には、問い合わせ内容が共有されておらず、対応が完了するまで時間がかかっていました。
問い合わせ業務の効率化をしてから、チームで問い合わせ業務を行うという方針に変更しています。
問い合わせ業務の属人化は解消され、対応時間が削減されたことで顧客満足度がアップしました。
またスタッフの平均残業時間は、課題を抱えていた頃の4分の1〜3分の1に抑えられています。
株式会社ブイキューブ

引用元:株式会社ブイキューブ
株式会社ブイキューブでは、オンラインイベントの需要が高まったことにより問い合わせ数が増加しました。
毎日3,000件以上のメールを受信しており、メールの対応漏れや対応遅れが多発した点が課題でした。
業務効率化が進んでからは、個人メールアドレスでの対応を廃止したことで業務の属人化が解消されました。
またリアルタイムで情報共有ができるようになって、複数のスタッフで業務を請け負うこととなりました。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
問い合わせ業務の運用でよくある課題と解決策や注意点

回答率や対応スピードを高めるコツ
問い合わせ業務の回答率や対応スピードを高めるには、業務フローやマニュアルの見直しが重要です。現場担当者の意見を取り入れながら、無駄な工程や複雑な手順を省き、シンプルで標準化された対応プロセスを構築しましょう。
FAQやチャットボットを整備し、自己解決できる仕組みを用意することで、一次対応の負担を減らし、スピーディーな対応が可能になります。
また、問い合わせ管理システムを導入し、進捗や履歴を一元管理することで、抜け漏れや重複対応を防止し、全体の業務効率が向上します。
個人情報保護とセキュリティ対策
問い合わせ対応では、顧客や従業員の個人情報を扱うため、情報管理とセキュリティ対策が不可欠です。
まず、個人情報の利用目的や管理体制を明確にし、社内でルールを徹底しましょう。不要な個人情報の取得は避け、アクセス権限を限定することでリスクを最小限に抑えます。
問い合わせ管理システムやクラウドサービスを利用する場合は、データの暗号化やログ管理、定期的なセキュリティチェックを実施しましょう。万が一の情報漏洩に備えた対応マニュアルや教育も重要です。
フォローアップ・再調査のタイミング
フォローアップや再調査は、問い合わせ対応の品質向上や顧客満足度アップに直結します。問い合わせ完了後には、一定期間をおいてお礼や満足度確認のメールを送ることで、顧客の声を収集しやすくなります。
また、対応内容や業務改善の効果を検証するため、定期的に再調査を実施するのも有効です。未解決案件やクレーム対応には、迅速なフォローアップを心がけることで信頼関係を維持できます。こうしたサイクルを仕組み化することで、継続的な業務改善が実現します。
社内共有と現場定着のポイント
効率的な問い合わせ対応を実現するには、マニュアルやFAQ、ナレッジを社内で共有し、現場に定着させることが不可欠です。最新版のマニュアルやテンプレートを誰もがアクセスできる場所に保管し、定期的なアップデートと周知を徹底しましょう。
新任担当者へのオンボーディングや定期研修も有効です。現場からのフィードバックを積極的に取り入れ、業務フローやマニュアルを実態に合わせて改善し続けることで、属人化を防ぎ、全員が均一な品質で対応できる体制を築けます。
▼Interviewz(インタビューズ)では、ヒアリング体験をDX化し、質の高い情報をスピーディーに収集、顧客・ユーザー理解を深め、サービスのあらゆるKPIの改善を可能にします。
テキストタイピングを最小化した簡単かつわかりやすいUI/UXと、収集した声をノーコードで様々なシステムに連携し、ユーザーの声を様々なビジネスプロセスで活用することで、よりビジネスを加速させることが可能です。
以下の資料ではそんなInterviewz(インタビューズ)のより詳しいサービスの概要を3分で理解いただけます。Interviewzについてより詳しく知りたい方は、以下の資料をご参照ください。
問い合わせ業務の効率化にはインタビューズのヒアリングツールがおすすめ!
インタビューズのヒアリングツールは、問い合わせ業務の効率化に最適です。なぜなら、専門知識不要で直感的に高品質なヒアリングフォームを短時間で作成でき、豊富なテンプレートやカスタマイズ機能により現場のニーズに柔軟に対応できるからです。
ヒアリング内容を標準化できるため、担当者ごとの品質差や情報の抜け漏れを防ぎ、顧客対応を均一化できます。
回答データはリアルタイムで自動集計され、Googleスプレッドシート連携や分析機能も充実しているため、情報共有や意思決定がスムーズです。
さらに、紙や手作業によるコストや手間も大幅に削減でき、セルフ解決を促進することでサポートコストも抑えられます。
そこで、ぜひこの機会に30日間の無料トライアルをお試しください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。