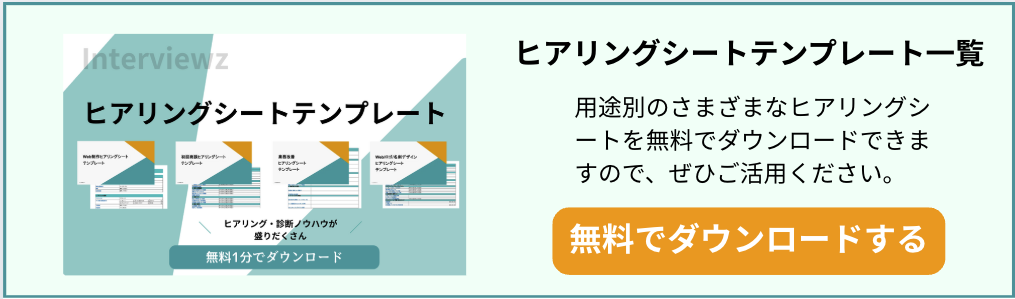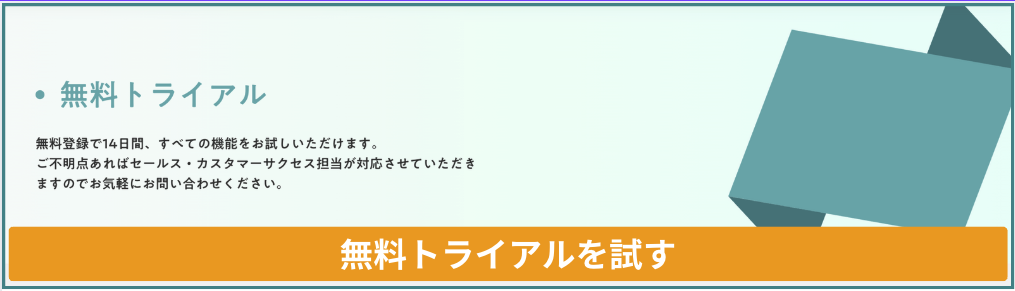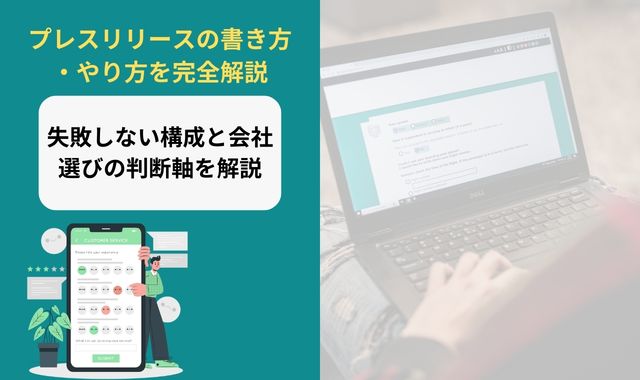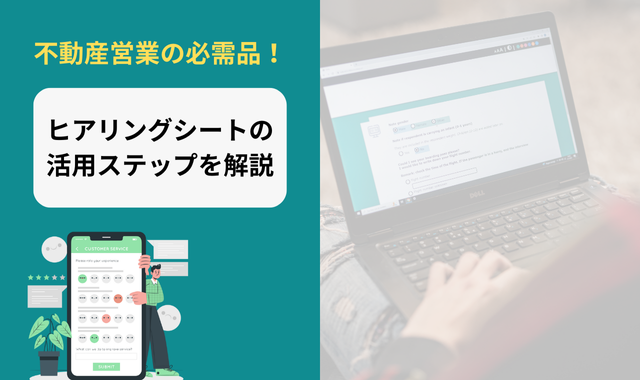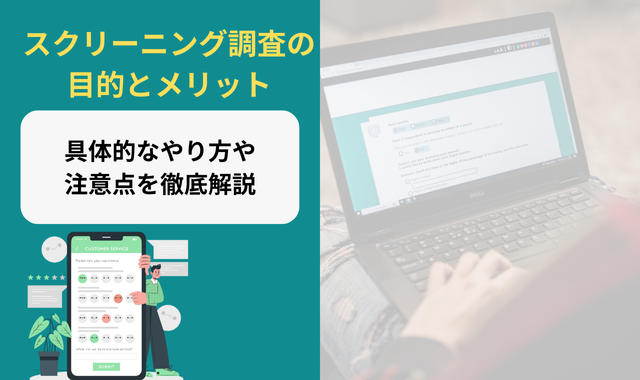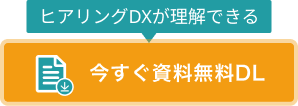インタビュー調査のやり方|準備方法や質問内容、成功するコツも解説
- 2025/07/25
- 2025/07/26

目次
インタビュー調査で得られた膨大なデータも、適切な分析方法を用いなければ本質的な発見につなげることはできません。コーディングやKJ法など、体系的な手法を使うことで発言のパターンやテーマを明確にし、調査結果をより深く理解できるようになります。
また、資料作成の際には、情報の整理や伝え方にも工夫が必要です。分析の質が調査全体の成果を大きく左右するため、手順や注意点を押さえることが重要です。
そこで今回は、インタビュー調査の主な分析方法4つと資料作成のコツや注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
インタビュー調査とは?基本的な概念と重要性を解説

インタビュー調査の定義と目的
インタビュー調査とは、対象者に直接インタビューを行い、その行動や背景にある意識・感情・価値観などを深く掘り下げて把握する定性調査の一種です。
主な目的には、ターゲット層の実態把握、課題設定や仮説の発見・検証、意思決定に影響するインサイトの発掘などが挙げられます。
数値データでは見えない「なぜそう考えるのか」「どんな背景があるのか」といった深層心理や行動理由を明らかにできる点が特徴です。
定量調査との違いとメリット・デメリット
以下では、インタビュー調査(定性調査)と定量調査の違い、およびそれぞれのメリット・デメリットを表にまとめます。
|
比較項目 |
インタビュー調査(定性) |
定量調査(アンケート等) |
|
目的 |
背景・理由・感情などの深掘り |
傾向・割合・数値データの把握 |
|
データの種類 |
言語情報(自由回答、発言内容、非言語情報) |
数値データ(選択肢、スコア等) |
|
メリット |
・深層心理や行動理由の把握 ・想定外の発見 ・非言語情報も観察可能 |
・統計的な傾向把握 ・大規模調査が容易 ・分析の客観性 |
|
デメリット |
・サンプル数が限られる ・主観的解釈のリスク ・実施コストが高い |
・深層心理や背景が分かりにくい ・自由回答が少ない |
インタビュー調査は、参加者の発言や表情、声のトーンなどから表面的でない本音や新たなニーズを発見できる一方で、サンプル数が少なく主観的な解釈に注意が必要です。
ビジネスにおけるインタビュー調査の活用場面
インタビュー調査は、以下のようなビジネスシーンで活用されています。
- 新商品・サービスの企画・開発
ターゲットユーザーの実態や意思決定プロセスを深く把握し、開発や改善に反映する。
- マーケティング戦略の立案
顧客インサイトやペルソナ作成、カスタマージャーニーの設計に活用できる。
- 広告・クリエイティブ評価
アイデアやコンセプト、広告表現へのリアルな反応や印象を収集する。
- 既存サービスの課題抽出・改善
定量調査で見えた課題を深掘りし、具体的な改善策を導き出す。
- 従業員エンゲージメントや社内施策
従業員の本音や職場課題の発見、組織改善のヒントを得る。
上記のように、インタビュー調査は、数値では捉えきれない顧客やユーザーの本音・深層心理を明らかにし、ビジネスの意思決定や商品・サービスの成功に直結するインサイトを提供する重要な手法です。
定量調査と組み合わせることで、より立体的で実践的なマーケティングや商品開発が可能となります。
インタビュー調査の主な種類と手法

個人インタビュー(デプスインタビュー)の特徴
デプスインタビュー(Depth Interview)とは、1対1でじっくりと行う面談形式のインタビューです。
1人あたり30分~90分程度をかけて深く掘り下げるため、対象者の本音や価値観、意思決定の背景、デリケートな話題まで詳細に把握できます。また、他人の目を気にせず話せるため、個人の深層心理やパーソナルな体験の収集に最適です。
デプスインタビューは、新商品開発やカスタマージャーニーの深掘り、仮説探索などに活用されています。
グループインタビュー(フォーカスグループ)の特徴
グループインタビュー(Focus Group Interview)とは、4~8名程度の対象者を一堂に集めて座談会形式で実施するインタビューの手法です。
モデレーターが進行し、参加者同士の意見交換を促すことで、多様な意見や相乗効果による新たな気づきが得られやすいのが特徴です。短期間・比較的低コストで多くの意見を収集できる反面、個人の深掘りは難しく、他者の影響で本音が出にくい場合もあります。
グループインタビューは、コンセプト評価やターゲット層の特性把握などに適しています。
|
手法 |
主な特徴 |
適した用途 |
|
デプスインタビュー |
1対1、深掘り、本音・背景の把握 |
新商品開発、意思決定要因の分析 |
|
グループインタビュー |
4~8名、座談会、意見の多様性・相乗効果 |
コンセプト評価、属性別の実態把握 |
オンラインインタビューとオフラインインタビューの比較
オンラインインタビューはZoomやTeamsなどのビデオ会議ツールを利用するインタビューで、場所や時間の制約が少なく、遠方や多忙な対象者にも対応しやすいのが利点です。自宅から参加できるためリラックスして話しやすく、感染症対策にも有効です。ただし、通信環境や操作リテラシーの課題、非言語情報(表情・仕草など)の取得がやや限定される場合があります。
一方、オフライン(対面)インタビューは会場などで直接実施するため、表情や雰囲気などの非言語情報も含めて詳細に観察できる点が強みです。信頼関係を築きやすく、深い対話が可能ですが、移動や会場手配などコストと手間がかかります。
|
比較項目 |
オンラインインタビュー |
オフライン(対面)インタビュー |
|
実施場所 |
自宅・遠隔地 |
会場・オフィス |
|
コスト・手間 |
低い |
高い |
|
非言語情報取得 |
やや限定的 |
詳細に観察可能 |
|
参加のしやすさ |
高い |
やや低い |
構造化インタビューと非構造化インタビューの使い分け
構造化インタビューとは、あらかじめ決められた質問項目・順序に沿って進行するインタビューの手法です。複数人への比較やデータの標準化に適しており、調査者によるバラつきを抑えられます。主に大規模調査や定量的な比較分析に有効です。
一方、非構造化インタビューとは、自由な会話形式で進め、対象者の発言や反応に応じて質問を柔軟に変化させる手法です。予想外の発見や深いインサイトの抽出に強みがあり、探索的な調査や仮説生成に適しています。
半構造化インタビューは、両者の中間で、基本的な質問枠組みを持ちながらも、自由な深掘りや追加質問が可能です。効率と柔軟性のバランスが取れるため、実務で最も多用されています。
|
手法 |
特徴 |
主な用途 |
|
構造化 |
質問・順序が固定、比較・標準化に強い |
大規模調査、定量比較 |
|
半構造化 |
基本枠組み+自由質問、柔軟な深掘りが可能 |
実務全般、仮説検証 |
|
非構造化 |
完全自由、予想外の発見や深層心理の抽出に強い |
探索的調査、仮説生成 |
上記のように、インタビュー調査を実施する際は、目的や対象、得たい情報の深さ・広さに応じて最適な手法を選ぶことが重要です。
個人・グループ、オンライン・オフライン、構造化の度合いなどを柔軟に組み合わせることで、より質の高いインサイトを得ることができます。
インタビュー調査の準備方法5つと流れ

1.調査目的の明確化と仮説設定
インタビュー調査の最初のステップは、調査の目的を明確にすることです。
「何を明らかにしたいのか」「調査結果をどのように活用したいのか」を具体的に設定し、現状の課題や仮説を整理しましょう。
例えば「新商品のターゲットユーザーの購買動機を知りたい」「サービス利用者の不満点を深掘りしたい」など、ゴールを明確にすることで、質問設計や分析の方向性がぶれません。
2.対象者(インタビュイー)の選定基準と募集方法
次に、誰にインタビューをするかを決めましょう。
年齢・性別・地域などの基本属性だけでなく、「週3回以上利用している」「特定の課題を持っている」など、調査目的に合った条件を設定します。なお、スクリーニングアンケートで条件に合う対象者を抽出する方法が一般的です。
偏りのないサンプル選定や、参加者が安心して話せる環境(匿名性の担保など)も重要です。
3.インタビューガイドの作成方法
インタビューガイドとは、質問項目や進行の流れをまとめた台本です。調査目的に沿って「必ず聞く質問」と「状況に応じて深掘りする質問」を整理します。
質問は、専門用語を避け、シンプルで分かりやすく設計し、二重質問や誘導的な表現を避けることがポイントです。アイスブレイクから本題、クロージングまでの流れを意識し、制限時間内に収まるように調整しましょう。
4.必要な機材と環境の準備
インタビューの録音・録画にはボイスレコーダーやカメラ、予備バッテリーなどが必須です。
オンラインの場合は、通信環境(Wi-Fi推奨)、デバイスのOSやアプリのバージョン確認、接続テストも事前に行いましょう。会場の場合は、静かな場所・雑音対策・適切な照明も重要です。
参加者のプライバシー保護や、データの安全な保存方法も確認しておくことが重要です。
5.事前のリハーサルと準備チェックリスト
本番前にリハーサルを行い、質問の流れや機材の動作確認、想定問答の練習をしておくと安心です。
セルフチェックリストを活用し、「目的・仮説の明確化」「対象者の条件」「質問項目の妥当性」「機材・環境の整備」「当日の進行」などを一つずつ確認しましょう。
準備の流れのまとめ
|
準備項目 |
具体的なポイント例 |
|
調査目的・仮説設定 |
目的・課題・仮説を明文化、ゴールを明確にしておく。 |
|
対象者選定・募集 |
属性・条件の設定、スクリーニング、偏り防止、匿名性に配慮する。 |
|
インタビューガイド作成 |
質問リスト、進行台本、分かりやすい表現、深掘り用質問を準備する。 |
|
機材・環境準備 |
録音・録画機材、予備バッテリー、通信環境、静音・照明、データ管理を徹底する。 |
|
リハーサル・チェック |
質問練習、機材テスト、進行確認、チェックリストを活用する。 |
上記の事前準備を徹底することで、インタビュー調査の質と成功率が大きく向上します。
効果的な質問内容の作り方

質問設計の基本原則
効果的な質問設計の基本は、ユーザーの実際の体験や事実に基づいた内容を尋ねることです。
「もし○○だったらどう思いますか?」のような仮定や未来の質問ではなく、「直近いつ、どんな場面で困りましたか?」など、具体的な過去の出来事や行動を聞くことで、正確で信頼性の高い回答が得られます。
また、ユーザー自身も気づいていないインサイトを引き出すため、「なぜ?」「どうしてそう思った?」と深掘りし、表面的な回答の奥にある本音や背景を探ることが重要です。
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの使い分け
オープンクエスチョンとは「どのように感じましたか?」「その時どうしましたか?」など、自由に答えられる質問で、相手の考えや感情、背景を深く掘り下げるのに有効です。
一方、クローズドクエスチョンは「はい」や「いいえ」などの選択肢で答えられる質問で、事実確認や属性把握、数値的な情報の収集に適しています。
両者をバランスよく組み合わせることで、全体像と深層の両方を把握できます。
段階的な質問構成(アイスブレイク→本題→深掘り)
段階的な質問構成は、アイスブレイク→本題→深掘りの順で行います。
1.アイスブレイク
緊張をほぐし、話しやすい雰囲気を作るための簡単な質問(例:「今日はどちらから来られましたか?」)。
2.本題
調査目的に沿ったメインの質問(例:「最近○○を使ってみて、どんな点が便利だと感じましたか?」)。
3.深掘り
本題の回答を受けて、理由や背景、具体的なエピソードをさらに掘り下げる質問(例:「そのとき、なぜそう思われたのですか?」)。
避けるべき質問パターンと誘導質問の注意点
「どんな機能があったら使いますか?」のような未来の仮定質問や、「○○という課題、ありますよね?」といった誘導的な質問は避けましょう。
回答者の自由な発言を妨げたり、調査者の期待通りの答えを引き出してしまうリスクがあります。
曖昧な表現や二重質問も避け、1つの質問で1つの内容を尋ねることが大切です。
業界別・目的別の質問例とテンプレート
|
業界・目的 |
質問例 |
|
ITサービス |
「直近1ヶ月でシステム利用時に困ったことは何ですか?」 「その課題を解決しようとした際、どんな方法を試しましたか?」 |
|
小売・EC |
「前回オンラインで購入した商品を選んだ理由を教えてください」 「購入時に迷った点はありましたか?」 |
|
人事・組織 |
「最近、職場でやりがいを感じた瞬間はいつですか?」 「その背景にはどんな出来事がありましたか?」 |
|
商品開発 |
「新商品を初めて使ったときの印象を教えてください」 「他社製品と比較して良かった点・悪かった点は?」 |
テンプレート例
- アイスブレイク:「まずは簡単に自己紹介をお願いします」
- 本題:「最近○○で困ったことはありますか?」
- 深掘り:「そのとき、なぜそう感じたのか詳しく教えてください」
上記のように、質問設計では、事実ベース・具体的・段階的に深掘り・誘導を避けることが基本です。業界や目的に応じてテンプレートを柔軟にカスタマイズし、価値あるインサイトを引き出しましょう。
インタビュー調査の実施手順と進行のコツ

インタビュー当日の流れと時間配分
インタビュー当日は、まずアイスブレイク(5分程度)で緊張をほぐし、主目的や同意事項を再確認します。その後、本題の質問(約45~70分)に入り、優先順位の高い質問から順に進行。最後にクロージング(5~10分)で追加質問や感謝を伝え、全体で60~90分が一般的です。なお、グループインタビューは90~120分が目安です。
効果的な聞き方とコミュニケーション技術
インタビュー調査では、話しやすい雰囲気づくりが重要です。相槌やうなずきで安心感を与え、オープンクエスチョン(自由回答型)を多用しましょう。
「なぜ」を直接使わず、「理由を教えてください」「どんな背景がありましたか?」など柔らかい表現を意識することが重要です。
相手の本音を引き出すテクニック
相手の本音を引き出すテクニックとしては、次のようなものが挙げられます。
- アイスブレイクで緊張を解く
- まず事実や体験を尋ね、徐々に感情や理由を深掘りする
- 「もう少し詳しく教えていただけますか?」と追加質問
- 否定せず共感を示し、自由な発言を促す
このような工夫で、表面的な答えだけでなく本音やインサイトを引き出しやすくなります。
想定外の回答への対応方法
予定外の話題が出ても、まずは遮らず最後まで聞きましょう。
回答の内容が調査目的に関係する場合は深掘りし、関係が薄い場合は「貴重なご意見ありがとうございます」と受け止めてから本題に戻します。
このように、インタビュー調査では、柔軟な対応力が求められます。
記録・録音の取り方とメモのコツ
録音は事前に許可を取り、必ず実施しましょう。メモは発言の要点や印象的な言葉、非言語情報(表情・声のトーンなど)を簡潔に記録します。
録音に頼りすぎず、聞きながら重要ポイントをメモすることで、後の分析やレポート作成がスムーズになります。
インタビュー進行のポイントのまとめ
|
項目 |
ポイント例 |
|
時間配分 |
アイスブレイク5分/本題45~70分/クロージング5~10分 |
|
聞き方 |
オープンクエスチョン、共感、柔らかい表現 |
|
本音の引き出し |
事実→感情→理由の順で深掘り、追加質問 |
|
想定外の回答対応 |
遮らず傾聴、必要に応じて深掘り、本題に戻す |
|
記録・メモ |
録音+要点・非言語情報を簡潔に記録 |
▼以下の資料は、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較した資料です。ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。 類似サービスの比較を行いたい方は、1分で比較できる以下の表を是非ご参考ください。
インタビュー調査を成功させるための重要なポイント

インタビュアーに求められるスキルと心構え
インタビュアーには、高いコミュニケーション力と共感能力、そしてメタ認知能力(自分の質問や態度を客観的に振り返る力)が不可欠です。相手の話を傾聴し、情報を整理しながら、読者や調査目的を意識して会話を導く力が求められます。
また、調査現場での実務知識や、業界特有の「勘所」も重要です。インタビュー前には対象者の情報を徹底的にリサーチし、臨機応変に対応できる準備が必要です。
調査対象者との信頼関係の構築方法
調査対象者との信頼関係を築くには、事前に調査目的や流れを丁寧に説明し、プライバシーや発言内容の取り扱いを明確に伝えることが大切です。
アイスブレイクで緊張をほぐし、相手の話に共感や肯定的なリアクションを示すことで、安心して本音を話してもらえる雰囲気を作りましょう。
バイアスを避けるための注意点
インタビュアーは常に中立的な立場を維持し、先入観や期待が質問や態度に表れないよう注意しましょう。参加者の意見に反論したり、誘導的な質問をしたりせず、話を遮らずに傾聴する姿勢が重要です。
データ分析時も主観的な解釈を避け、複数の視点で検証することが大切です。
効率的なインタビューの進め方
効率的にインタビューを進めるために、次の点に留意しましょう。
- 行動→態度→意識の順で質問し、段階的に深掘りする。
- 優先順位の高い質問から進め、時間配分を意識する。
- 想定外の話題が出ても遮らず傾聴し、必要に応じて本題に戻す。
- 記録やメモは要点と非言語情報も簡潔に残す。
トラブル対応と緊急時の対処法
トラブル対応と緊急時の対処法として、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 参加者が不快・体調不良を訴えた場合は、すぐに休憩や中止を申し出る。
- 質問が理解されていないと感じたら、言い換えや説明を加える。
- 機材トラブル時は、予備機材や手書きメモで対応。
- プライバシーや同意に関する問題が発生した際は、速やかに説明・謝罪し、必要に応じて調査を中止する。
▼ビジネスにおいて「ヒアリングの質」は、その後の提案の精度や成果を大きく左右します。しかし、実際の現場では以下のような悩みがよく聞かれます。
- 「何をどこまで聞けばいいのかわからない」
- 「毎回ヒアリングの内容が属人化していて、標準化できない」
- 「新人や外注メンバーにヒアリング業務を任せにくい」
- 「案件ごとに内容が違うため、毎回シートをゼロから作ってしまう」
下記のヒアリングシートテンプレートでは、上記のような現場の課題を解決するためにWeb制作・採用・営業・ブランディングなど、用途別・目的別にヒアリング項目が体系立てられており、誰でもすぐに使えるフォーマットになっています。
さらに、テンプレートには診断ノウハウやチェック項目も付属していますので、ヒアリングを通じて「課題の構造化」や「次のアクション提案」まで自然に導けます。
無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
インタビュー結果の分析・活用方法

定性データの整理と分析手法
インタビュー調査で得られた定性データは、まず発言録(文字起こし)を作成し、Excelなどで質問ごと・対象者ごとに整理しましょう。
その後、発言内容をカテゴリーごとに分類する「コーディング」や、情報をカード化してグルーピングする「KJ法」、重要度や階層構造を明らかにする「上位下位関係分析」などの手法を用いて、データを体系的に整理・分析します。
これにより、複数の参加者に共通する意見や、特徴的な行動・感情などが浮き彫りになります。
インサイトの抽出と報告書作成
整理したデータから、調査目的や仮説に沿って本質的な気づき(インサイト)を抽出します。例えば、「多くのユーザーが○○に不満を感じている」「△△なシーンで利用されやすい」といった示唆です。
報告書は、調査概要・要約・詳細分析・発言録などの構成で、論理的かつ視覚的にわかりやすくまとめます。グラフや図解を活用し、主張の裏付けとなる発言や事例も盛り込みましょう。
結果をビジネスに活かす具体的な方法
抽出したインサイトは、商品・サービスの企画改善、マーケティング戦略の立案、カスタマージャーニーやペルソナ設計、広告やクリエイティブの評価、社内施策の改善など、幅広いビジネス領域で活用できます。
例えば、ユーザーの不満や要望を新機能開発に反映したり、購買行動の背景をプロモーション施策に応用したりすることで、実効性の高い施策立案が可能です。
次回調査への改善点の見つけ方
分析・レポート作成後は、調査目的や仮説に対して十分な示唆が得られたか、分析プロセスに主観やバイアスが入っていないか、情報の整理や可視化が適切だったかを振り返ります。
また、デブリーフィング(関係者による振り返りミーティング)を行い、質問設計や進行、分析手法などの課題や改善点を共有します。
これにより、次回調査の設計や運用精度を高めることが可能です。
定性データ分析手法の比較表
|
手法名 |
特徴・用途 |
|
コーディング |
発言内容をカテゴリー分けし、体系的に整理・比較 |
|
KJ法 |
情報をカード化し、グルーピングや図解で構造を可視化 |
|
上位下位関係分析 |
重要度や階層構造を明確化し、本質的なニーズを抽出 |
このように、インタビュー調査では、発言録作成→分類・グルーピング→インサイト抽出→報告書作成→振り返りの流れが基本です。
また、インサイトは具体的な事業施策や次回調査の精度向上に直結する重要な要素となりますので、特に注意深い考察が必要です。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
インタビュー調査の具体事例と成功のコツ

BtoB企業での顧客インタビュー成功事例
BtoB企業では、顧客インタビューを通じてペルソナ設定やカスタマージャーニーマップの精度を高め、マーケティング施策や営業戦略に活用するケースが増えています。
例えば、人材サービス企業では、業界特有の顧客行動を深掘りし、専門コンサルの知見も活用してコンテンツ設計や戦略立案を実施。その結果、リード数が前年比2倍以上に増加した事例があります。
また、顧客解像度を高めて広告やLPに反映し、問い合わせ数・商談化数の向上につなげた転職支援サービスの事例もあります。
新商品開発におけるインタビュー活用事例
新商品開発では、ターゲットとなる顧客の課題や要望、既存商品の不満点をインタビューで収集し、開発や改善に活かすのが一般的です。
例えば、BtoB企業が顧客インタビューから得た「導入前の課題」「情報収集の方法」「他社との比較ポイント」などをもとに、実際のニーズに即した商品設計やサービス改善を行い、競合との差別化や市場投入後の成功につなげています。
サービス改善のためのユーザーインタビュー事例
既存サービスの改善では、ユーザーインタビューで利用時の困りごとや満足・不満点、導入後の変化をヒアリングし、具体的な改善策を導き出すことが可能です。
例えば、インタビュー内容をもとにカスタマージャーニーマップを見直したり、ユーザーの声を公式サイトの導入事例として掲載することで、信頼性向上と新規顧客獲得にもつなげています。
失敗例から学ぶ改善ポイント
失敗事例としては、インタビュー対象者の選定ミスや、目的が曖昧なまま質問を進めてしまい、得られた情報が活用できなかったケースが挙げられます。また、顧客の本音を引き出せず、表面的な回答しか得られなかったり、インタビュー後の情報整理や活用方法が不十分で成果につながらなかった例もあります。
改善ポイントは、事前準備の徹底(目的・仮説の明確化、対象者の適正選定)、インタビューガイドの作成、データ整理と分析の体制強化、インタビュー内容の具体的な施策への落とし込みです。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。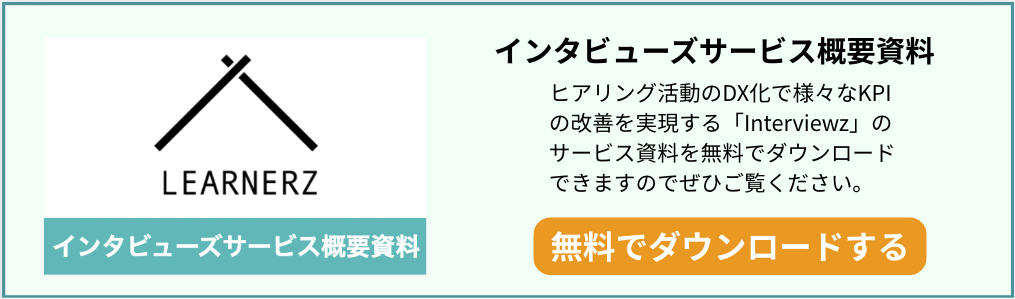
インタビュー調査にはインタビューズのヒアリングツールがおすすめ!
インタビュー調査には、インタビューズのヒアリングツールがおすすめです。
直感的なタップ操作で回答できる診断・アンケートフォームを簡単に作成できるため、回答者の負担を大幅に軽減し、回収率と回答の質が向上します。管理画面もシンプルで、専門知識がなくても即時に設問やデザインの改善ができ、運用コスト削減にもつながります。
また、GoogleスプレッドシートやSalesforceなど主要な外部ツールと自動連携できるため、集計・分析・営業活動への活用がスムーズです。セキュリティ対策も万全で、企業の情報管理基準にも対応しています。
多様なフォームテンプレートが用意されており、アンケートや問い合わせ、ユーザーインタビューなど幅広い用途に対応可能です。また、複数ユーザーでの同時運用やリアルタイム集計にも強く、チームでの効率的な調査運用が実現します。
このように、インタビューズは「使いやすさ」「データ活用」「セキュリティ」「運用効率」のすべてを高いレベルで両立しているため、インタビュー調査の成果と業務効率を同時に最大化できるツールとしておすすめです。
インタビューズのヒアリングツールは、アンケート調査の分析や効率化に最適です。また、インタビューズでは、14日間の無料トライアル期間でも全ての機能を利用可能ですので、ぜひこの機会にお試しください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。