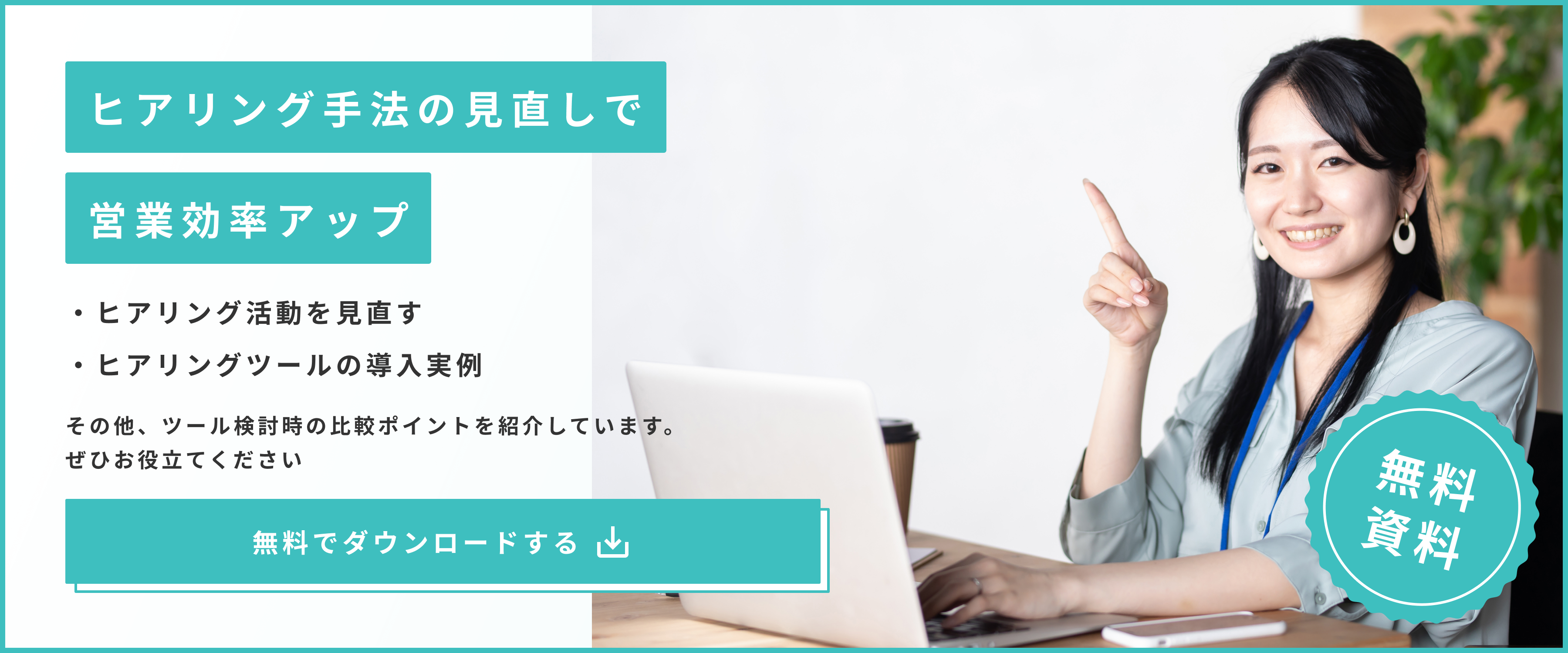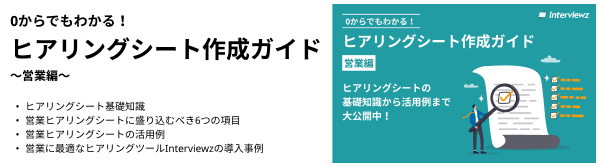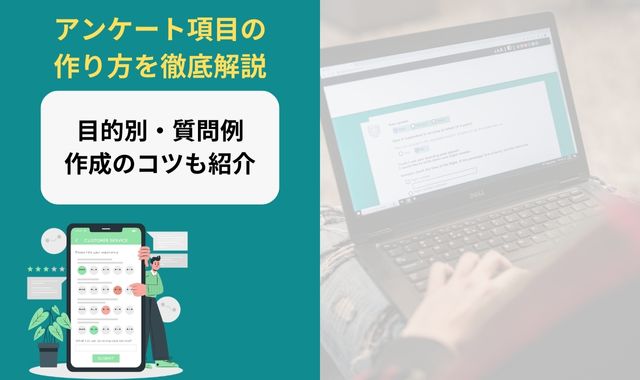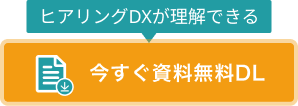アンケート調査とは?やり方と分析方法、ビジネス活用の事例を徹底解説
- 2023/03/30
- 2025/06/21

目次
ビジネスの現場で意思決定や改善策を導き出すには、客観的なデータの収集と分析が欠かせません。
アンケート調査は、顧客や従業員の声を効率的に集め、現状把握や課題発見に役立つ有力な手法です。
しかし、やり方や分析方法を誤ると十分な成果につながりません。
そこで今回は、アンケート調査について、そのやり方と分析方法、ビジネス活用の事例を徹底解説しますので、ぜひ参考にしてください。
アンケート調査の基本とビジネスにおける重要性を解説

アンケート調査とは、特定の調査対象者に対して設計された質問票を用い、その回答を収集・分析することで、意見や行動、ニーズなどの情報やデータを得る手法です。
郵送や電話、訪問、Webなど多様な方法で実施され、定量的な数値データや自由記述による定性的データの両方を収集できます。
得られたデータは統計的手法で分析され、企業や組織の意思決定や課題解決に活用されます。
ビジネスでアンケート調査が求められる背景
ビジネス環境が急速に変化し、顧客や市場のニーズが多様化・複雑化する中、企業は的確な意思決定のために客観的なデータが必要です。
アンケート調査は、顧客満足度や従業員意識、商品・サービスの評価など、現場のリアルな声を効率的に収集できるため、マーケティングリサーチや経営戦略の策定に不可欠な手法となっています。また、PDCAサイクルの評価や改善にも活用されます。
アンケート調査のメリット・デメリット
アンケート調査のメリットは、多数の対象者から効率的にデータを収集でき、結果を定量的に分析できる点です。コストや手間を抑えつつ、幅広い意見や傾向を把握できるため、経営判断や商品開発に役立ちます。
一方で、設問設計や配布方法が不適切だと正確なデータが得られず、回答率が低下するリスクもあります。また、自由記述の分析には手間がかかる場合があるため、効果的かつ効率的な運用が重要です。
アンケート調査のやり方と設計のポイント

調査目的とターゲットを明確化する
アンケート調査は、最初に「何のために実施するのか」「誰から情報を集めるのか」を明確にすることが重要です。
目的や課題を箇条書きで整理し、必要な情報を逆算して設問に落とし込みます。ターゲットも具体的に設定することで、無駄のない設計が可能となり、分析や改善アクションにつなげやすくなります。
設問設計とレイアウトのコツ
設問設計では、回答者がストレスなく答えられる構成を意識します。最初は答えやすい質問から始め、全体→詳細、または過去→現在→未来の流れが自然です。
設問は簡潔で明確な表現を使い、選択肢も過不足なく設定しましょう。自由記述は要点を絞り、必要最小限にとどめることで回答率が上がります。
実施方法の選び方(Web・紙・メール)
実施方法は、ターゲットや調査内容、回収効率を考慮して選ぶことが重要です。
Webアンケートは手軽で集計が自動化しやすく、幅広い層に短期間で配布可能です。一方、紙アンケートはネット利用が難しい層や現場調査向き、メールは既存顧客や社内調査に適しています。
調査の目的や対象に応じて最適な手段を選択しましょう。
回答率を上げるための工夫を行う
回答率を高めるには、設問数を絞り、所要時間を明記するなど回答者の負担を減らす工夫が重要です。
冒頭で調査の目的や活用方法を伝え、インセンティブや謝礼を用意するのも効果的です。リマインドメールや回答期限の設定も有効で、回答しやすいタイミングやデバイス対応も意識しましょう。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
アンケート調査の分析方法とデータの活用方法

データ集計・クロス集計の基本手順
アンケート調査の分析は、まず単純集計で各設問の回答数や割合を算出することから始めます。次に、クロス集計を活用し、属性(例:部署や役職)や設問同士を掛け合わせて傾向や関係性を深掘りするのが効果的です。
Excelのピボットテーブル機能を使えば、分析軸ごとに集計表を作成でき、全体傾向と特定層の違いが一目で分かります。これにより、施策の検討やターゲットの明確化に役立ちます。
顧客満足度・従業員意識の可視化
顧客満足度や従業員意識を可視化するには、5段階評価やNPSなどのスコアを算出し、グラフやヒートマップで視覚的に表現します。属性別や部署別のクロス集計で違いを明らかにし、どの層で満足度が高い・低いかを把握しましょう。
これにより、課題や強みを定量的に示し、関係者が現状を直感的に理解できるようになります。テキストデータも頻出ワードや傾向を可視化することで、定量・定性両面から現状を把握できます。
テキストマイニングや自由記述の分析
自由記述の回答は、テキストマイニング手法を使って分析します。
まず全回答を収集し、頻出ワードやキーワードの出現頻度を集計します。さらに、ポジティブ・ネガティブな意見や共通する課題を分類し、傾向を整理しましょう。
ワードクラウドやカテゴリー分けを活用することで、多様な意見の中から重要なテーマや改善点を抽出しやすくなります。定量データと組み合わせて活用することが、実践的な分析につながります。
改善アクションへの落とし込み方
分析結果から見えた課題や傾向をもとに、具体的な改善アクションを立案します。
例えば、満足度が低い項目や要望が多い内容を優先的に抽出し、現場で実行可能な施策に落とし込みます。改善策は担当部署や実施時期を明確にし、PDCAサイクルで効果検証を行うことが重要です。
分析からアクションまでの流れを一貫して設計することで、アンケート調査が実効性のある経営改善やサービス向上につながります。
▼下記の資料はヒアリングを効率化できるヒアリングシートの作り方をステップ別に解説した資料です。ぜひご活用ください。
ビジネスにおけるアンケート調査の活用と成果の事例

顧客満足度向上のための事例
顧客満足度向上のためにアンケート調査を活用した事例は多岐にわたります。
例えば、スターバックスコーヒージャパンは定期的な顧客アンケートを実施し、顧客の声を店舗運営やサービス改善に反映しています。従業員にはマニュアルではなく行動規範を配布し、現場で自発的に顧客満足につながる行動を促進。さらに、地域ごとの特色を活かした店舗づくりや、顧客の意見を反映した商品・サービス改良を行うことで、リピーターの増加や企業イメージの向上に成功しています。
このように、アンケートで得た定量・定性データを迅速に現場へフィードバックし、具体的な改善策に結びつけることが、顧客満足度向上の鍵となります。
商品・サービス開発での活用例
商品・サービス開発の現場でもアンケート調査は重要な役割を果たします。
ある家電メーカーでは、新製品発売前にデザインや機能に関するアンケートを実施し、顧客のフィードバックをもとに製品仕様を一部変更。その結果、発売後の顧客満足度が大幅に向上しました。また、飲料メーカーでは、味やパッケージデザインに関する定期的なアンケートを実施し、顧客の要望を反映した新フレーバーを追加。これが売上増加につながった事例もあります。
アンケートを通じて顧客ニーズを的確に把握し、開発や改善に即座に反映させることで、競争力のある商品・サービスの創出が可能です。
従業員エンゲージメント向上の事例
従業員エンゲージメント向上のためにもアンケート調査は広く活用されています。
例えば、定期的な従業員満足度調査やエンゲージメントサーベイを通じて、職場環境や働き方、評価制度などに対する従業員の本音を収集。これをもとに、コミュニケーション施策や福利厚生の見直し、キャリア支援制度の導入など、具体的な改善策を実施した企業では、離職率の低下や生産性の向上、従業員のモチベーションアップにつながった事例が報告されています。
従業員の声を経営に反映し、双方向のコミュニケーションを強化することが、組織の活性化と持続的成長の原動力となります。
アンケート結果を経営判断に活かす方法
アンケート調査で得られたデータは、経営判断の質を高めるための重要な材料となります。
顧客や従業員の満足度、商品・サービスへの評価などを数値化し、課題や強みを客観的に把握。これをもとに、商品開発やサービス改善、組織改革、マーケティング戦略などの意思決定に活用します。
定量データだけでなく、自由記述から得られる定性的な声も分析し、現場のニーズや市場動向を経営層がリアルタイムで把握できる体制を整えることで、迅速かつ的確な経営判断が実現します。
下記の記事では、ビジネスアンケートの作り方をすぐに使えるビジネスアンケートのテンプレート付きで解説していますので、ぜひご活用ください。
関連記事:ビジネスアンケートの作り方をすぐに使える業種別テンプレート付きで解説
▼以下の資料では、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較しています。
ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。
類似サービスの比較を行いたい方は、1分で比較できる以下の表を是非ご参考ください。
アンケート調査運用のよくある課題と解決策

1.回答率が伸びない原因と対策
アンケートの回答率が伸びない主な原因は、設問数が多すぎる、質問が分かりにくい、回答の負担が大きい、アンケートの目的や意義が伝わっていない、インセンティブがないなどです。
対策としては、冒頭でアンケートの主旨や重要性、活用方法を明確に伝えることが重要です。また、設問数を最小限に絞り、簡潔で分かりやすい設問文にすることで回答者の負担を減らしましょう。
回答にかかる目安時間を明記し、謝礼やインセンティブを用意することも効果的です。さらに、選択式の設問を中心にし、自由記述は必要最小限に抑えることで、途中離脱を防ぎます。
2.個人情報保護とセキュリティ対策
アンケート運用では、個人情報保護とセキュリティ対策が不可欠です。
個人情報の利用目的や管理体制を冒頭で明記し、「統計分析のみに利用し個人を特定しない」ことを伝えましょう。不要な個人情報は求めず、匿名性を担保する設計が信頼性向上につながります。
また、データの暗号化やアクセス権限の管理、信頼できるアンケートシステムの利用など、技術的なセキュリティ対策も徹底します。これにより、回答者が安心して協力できる環境を整えることができます。
3.フォローアップと再調査のタイミング
アンケート配信後のフォローアップや再調査は、回答率やデータの質を高めるうえで重要です。
未回答者には、回答期限前後にリマインドメールやお礼のメッセージを送り、協力を促しましょう。イベントや説明会後は、アンケート記入のための時間を設けることで回収率が向上します。
また、施策実施後や一定期間経過後に再調査を行うことで、改善効果の検証や新たな課題発見につながります。定期的なフォローアップにより、継続的なデータ収集と信頼関係の構築が可能です。
4.設問数や内容を最適化する
アンケート調査で一番避けたいことは、アンケート回答前に離脱されてしまうことです。アンケート回答前に離脱される原因は、アンケート調査の内容に飽きてしまう場合があるからです。
単調な質問や、答えにくい質問が続くと顧客は回答するのを面倒に感じてしまい、アンケート回答前に離脱してしまう可能性があります。
アンケート調査で飽きさせないようにするには、以下の方法がおすすめです。
- 分岐式の質問を取り入れる
- アンケート回答画面にキャラクターの設置
- 質問はできるだけ簡潔にする
- 質問を多くしすぎない
分岐式の質問は、答えた質問の選択肢に応じて次の質問が変化する方式の質問です。
分岐式の質問を導入することで、顧客にパーソナライズされたアンケート調査だと感じてもらいやすくなるでしょう。
【Interviewz】であれば、分岐式の質問がかんたんに作れるだけでなく、アンケート回答画面でキャラクターの設置ができます。
テンプレートを作る際には、できるだけわかりやすく簡潔に作成した方がよいでしょう。
質問の文字数などが多すぎると、顧客は読むのに疲れてしまい、離脱される原因になります。
また、顧客に対して色々質問を思いつくかもしれませんが、どのアンケート調査でも10個前後の質問にしておくことがおすすめです。
質問が多すぎると、顧客から飽きられて離脱されやすくなります。
▼Interviewz(インタビューズ)では、ヒアリング体験をDX化し、質の高い情報をスピーディーに収集、顧客・ユーザー理解を深め、サービスのあらゆるKPIの改善を可能にします。
テキストタイピングを最小化した簡単かつわかりやすいUI/UXと、収集した声をノーコードで様々なシステムに連携し、ユーザーの声を様々なビジネスプロセスで活用することで、よりビジネスを加速させることが可能です。
以下の資料ではそんなInterviewz(インタビューズ)のより詳しいサービスの概要を3分で理解いただけます。Interviewzについてより詳しく知りたい方は、以下の資料をご参照ください。
ビジネスアンケートの作成と実施にはインタビューズのヒアリングツールがおすすめ!
インタビューズのヒアリングツールは、ビジネスアンケートの作成と実施に最適です。
直感的なUIで専門知識がなくても簡単にアンケートを作成でき、ブランドイメージに合わせたカスタマイズも可能です。
GoogleスプレッドシートやSalesforceなど外部ツールとも自動で連携でき、データ集計や分析も効率的に行えるのが魅力です。
EFO機能や入力支援によりユーザーのストレスを軽減し、回答率向上と離脱防止を実現。ヒアリングコストを最大90%削減し、顧客満足度や業務効率を大幅に高めます。
そこで、ぜひこの機会に30日間の無料トライアルをお試しください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。