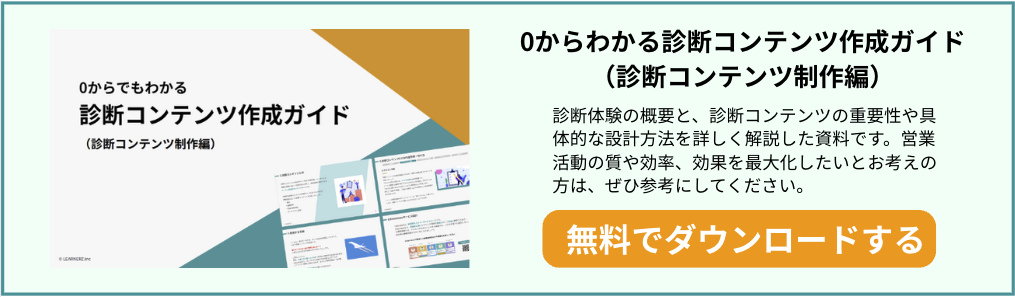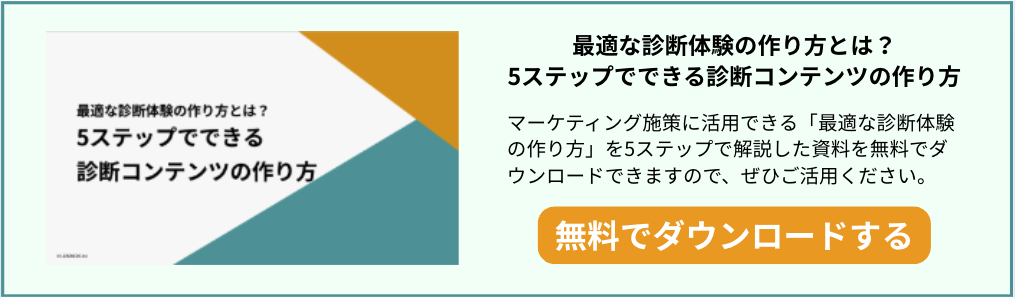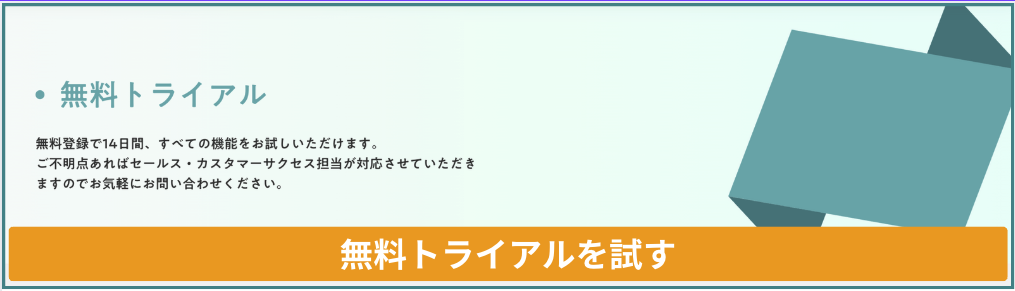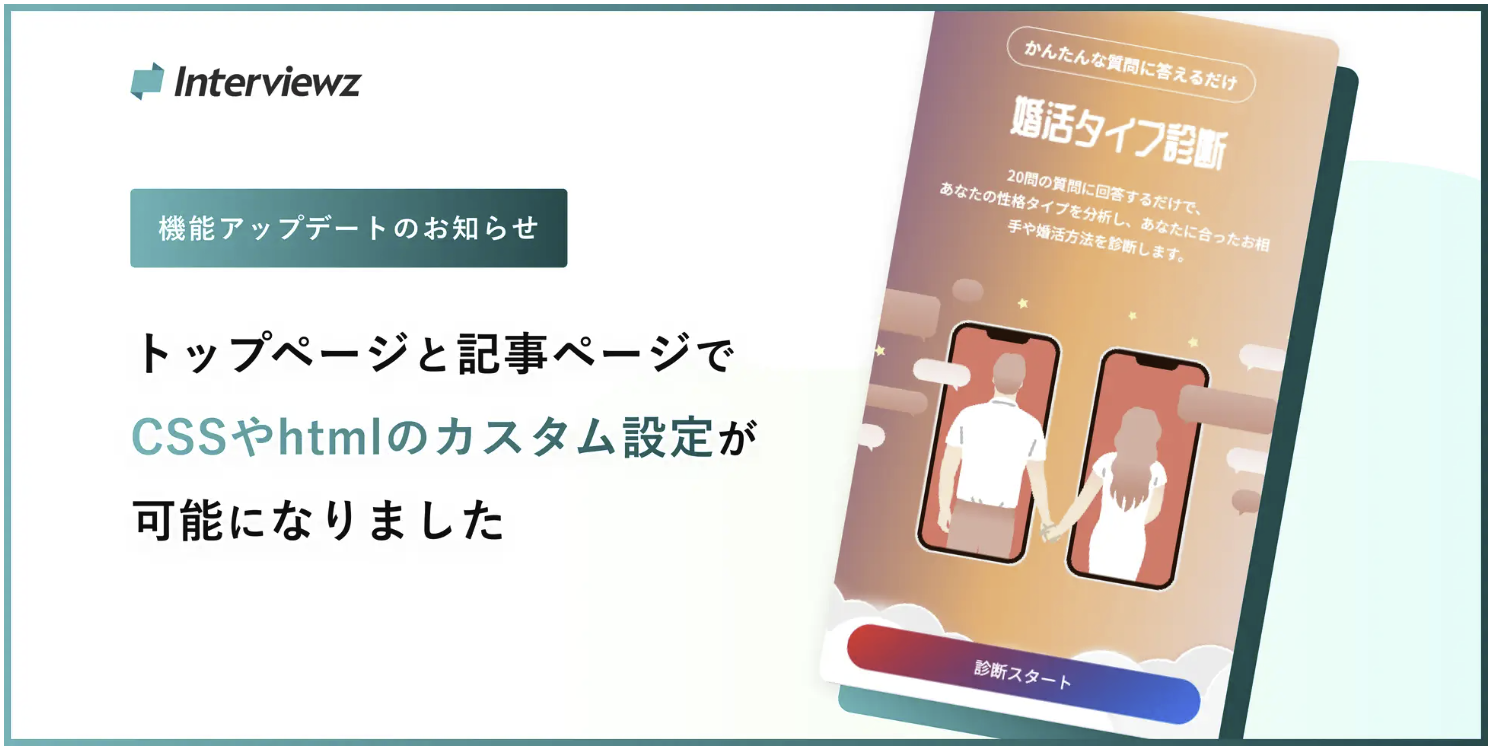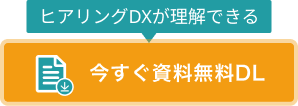診断コンテンツがマーケティングに効果的な理由と成功事例7つを解説
- 2022/12/22
- 2025/08/24

目次
診断コンテンツは、ユーザーが楽しみながら自分に合った結果を得られるため、顧客とのエンゲージメントを高める効果的なマーケティング手法として注目されています。
なぜなら、パーソナライズされた提案や自然なSNS拡散を通じて、ブランド認知の向上やリード獲得に繋がるからです。
さらに、多様な成功事例からは、診断コンテンツがさまざまな業界で成果を上げていることがわかります。
しかし効果を最大化するには、適切な設計と活用が不可欠です。
そこで今回は、診断コンテンツがマーケティングに効果的な理由と成功事例7つを徹底解説しますので、ぜひ参考にしてください。
まずは診断コンテンツの基礎知識を解説

診断コンテンツとは、企業が事前に用意した複数の質問にユーザーが回答し、その回答内容に基づいて最適な結果や提案を自動で表示する双方向型のWebコンテンツです。
多くの場合、ゲーム感覚で楽しめる形式となっており、回答結果はSNSで共有されやすいため、企業の認知拡大や商品訴求に効果的です。
主な形式には、一問一答形式、チェックシート形式、ステップ形式があり、それぞれ特徴と適用シーンが異なります。また、診断ロジックには回答に応じて質問や結果が分岐するフローチャート形式と、得点を集計して結果を決定する得点形式の2種類があります。これにより、ユーザーの回答に基づいてパーソナライズされた提案が可能です。
診断コンテンツは、商品やサービスの購買促進、顧客との接点強化、マーケティングデータの収集に活用されています。
診断コンテンツの基本的な種類と特徴

診断コンテンツの基本的な種類と特徴は主に以下の通りです。
診断コンテンツの基本的な種類5つ
1.一問一答形式
ユーザーが1つの質問に答えるごとに画面が切り替わり次の質問に進む形式です。直感的でわかりやすく、初心者でも答えやすいですが、多数の質問がある場合は回答の修正がしにくく負担になることがあります。
2.チェックシート形式
1画面に複数の質問が表示され、まとめて回答できる形式です。画面遷移が少なく回答負担が軽減されやすい点が特徴で、回答の選択肢は「はい/いいえ」など簡潔な場合が多いです。
3.ステップ形式
回答ごとに次の質問が展開され、回答に応じて質問内容が変わることもあります。ゲーム性が高く、ユーザーの継続的な参加が促されやすい形式です。
4.フローチャート(分岐)形式
回答によって質問や結果が分岐する形式で、より精度の高い診断を実現します。ユーザーの回答に沿ってパーソナライズされた結果を導きます。
5.得点(ポイント)形式
各質問に点数を付け、合計点で結果を決めるシンプルな形式です。設計が比較的容易で、多種多様な診断に適応可能です。
診断コンテンツの特徴5つ
- 診断コンテンツは、ユーザー参加型で双方向性が高く楽しみながら自己理解や選択を支援できることが特徴です。
- 結果がパーソナライズされているため、ユーザーの関心を引き付けやすく、エンゲージメントが高まります。
- SNSシェアが促進されやすく、自然な拡散や口コミ効果が期待できます。
- 企業はユーザーの回答データをマーケティング施策や商品開発に活用できます。
- それぞれの形式やロジックは用途や対象ユーザー、目的に応じて使い分けられます。
診断コンテンツの種類は一例として、パーソナライズ診断(肌質やファッションなど)、性格・適性診断(適職診断や性格タイプ分析)、ビジネス・スキル診断、健康・メンタル診断など多様な分類もあります。
このように、診断コンテンツは形式の違いと目的に応じた多彩な種類があり、それぞれの特徴を理解して最適な設計を行うことが重要です。
▼下記からは、Interviewzのデジタルギフト付きのアンケートに関する詳しい内容を無料でダウンロードできます。
このサービスを活用することで、通常のアンケートに比べて平均回答率が約2.8倍に改善された事例があります。ヒアリングやアンケートを効率的・効果的に改善したいとお考えの方は、ぜひご参照ください。
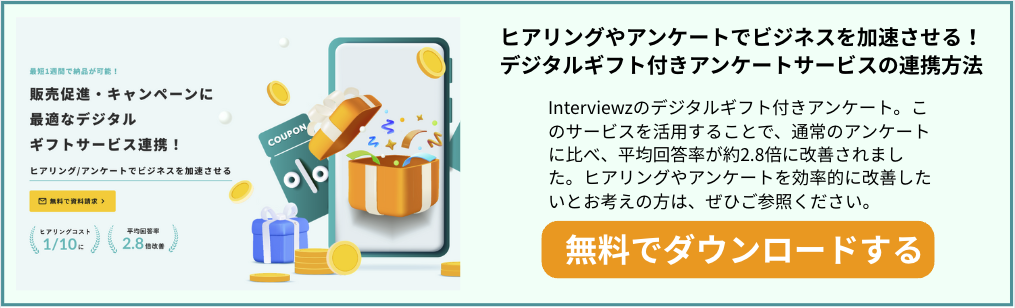
診断コンテンツがマーケティングに効果的な理由5つ

診断コンテンツがマーケティングに効果的な理由を、以下の5つのポイントで詳しく解説します。
1.ユーザーエンゲージメントの向上メカニズム
診断コンテンツは、ユーザーが楽しみながら参加できる双方向型コンテンツです。
自己理解や自己表現の欲求を満たすため、ユーザーの興味を引きつけサイト滞在時間を延ばせます。
パーソナライズされた結果により満足度が高まり、ブランドへの親近感も強化されるため、高い利用率と低い離脱率を実現し、継続的な関係構築に寄与します。
2.顧客ニーズの把握とパーソナライズ提案
診断から得られるユーザーの回答データを分析することで、趣味や関心、悩みなど顧客の具体的なニーズを把握可能です。
この情報を基に、個々に最適な商品・サービスを提案し、コンバージョン率の向上が期待できます。
ターゲットにマッチしたパーソナライズ提案は顧客満足度も高めます。
3.SNSを活用した自然拡散効果の仕組み
診断結果は面白く、意外性があり、個性を表現できる内容であればSNSでのシェアが促進されやすいです。
ユーザーのSNS拡散を通じて、自然な口コミ効果が生まれ、新規顧客への認知拡大につながります。
ゲーム性や楽しさが拡散を後押しします。
4.リード獲得と育成における役割
診断結果の送信時にメールアドレス等の情報を収集し、見込み顧客の獲得が可能です。
取得したデータを活用してフォローアップマーケティングを行うことで、リードの育成と商談化率の向上に貢献します。
診断コンテンツは質の高いリード獲得ツールとしても有効です。
5.ブランド認知度向上への貢献
エンターテイメント性が高く参加しやすい診断コンテンツは、ブランドや商品への興味・理解を自然に深められるのも魅力です。
SNSシェアによる拡散でブランド認知度が上がり、新規顧客層へのアプローチも容易になります。
結果を通じた提案で、購買意欲も刺激されるでしょう。
以上の理由から、診断コンテンツはマーケティングにおいてユーザーとの接点強化、効果的な顧客理解、拡散力、リード獲得、ブランド向上の五つの重要な役割を果たします。
▼以下は、診断体験の概要と、診断コンテンツの重要性や具体的な設計方法を詳しく解説した資料です。営業活動の質や効率、効果を最大化したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
診断コンテンツを導入した成功事例7選

化粧品ブランドの肌タイプ診断による売上アップ(LINE活用事例)
ある化粧品ブランドは、LINE公式アカウント上で「肌タイプ診断」を提供しました。ユーザーは簡単な質問に答えることで自分の肌質に最適なスキンケア商品を提案されます。
この診断はブランド認知度向上と売上増加に寄与し、気軽に診断できるLINEのプラットフォームがユーザーの参加を後押ししました。ユーザーデータの収集にも成功し、その後のマーケティングに活用されています。
旅行会社の趣味別おすすめ旅行先診断で予約数増加
旅行会社では、ユーザーの趣味や好みを診断するコンテンツを提供し、個々に合った旅行先を提案。診断結果に割引クーポンを付与する施策を展開しました。
これにより旅行予約数の増加が実現され、ニーズの顕在化と顧客の購買誘導効果が高まりました。また、SNSでのシェアも促進され、新規顧客開拓にもつながっています。
人材業界の性格診断を活用した採用強化事例
ポケモンセンターは、「ポケモン自己分析」という性格診断を採用活動に活用。性格タイプをポケモンに例えることで親しみやすく、応募者の多様性の理解や企業の採用方針のアピールに成功しています。
この診断はブランド認知拡大にも寄与し、採用応募者数の増加につながりました。
教育業界の学習スタイル診断による顧客満足向上
教育分野の学習塾では、学習スタイルを診断し、それに応じた学習プログラムを提案することで、顧客満足度を向上させています。
ユーザーのニーズを的確に把握し、最適化された学習支援が評価されており、継続利用や口コミ拡大に繋がっています。
ポケモンセンターの自己分析診断でのブランド認知拡大
前述のように、ポケモンのキャラクターを用いた自己分析診断は、ターゲット層に好評で、採用のみならずブランド認知の向上にも大きく寄与。SNSでの拡散を促進し、多方面からの注目を集めています。
SaaS企業の課題診断で効果的なリード獲得
SaaS企業では、自社サービスに関連する課題を無料診断するコンテンツを提供。見込み顧客の関心を具体化するとともに、診断完了後に連絡先を取得し、効率的なリード獲得と育成に成功しています。
また、データ分析を通じた営業戦略の高度化にもつながっています。
不動産業界のマイホーム購入診断による購買支援
不動産業では、利用者の希望条件を診断し、理想のマイホームを提案する診断コンテンツを導入。利用者の購入意欲を高め、購買判断支援の効果が実証されています。
加えて診断後のフォローアップでリードの商談化率を向上させています。
上記の7つの成功事例は、それぞれの業界の特性を活かし、ユーザー体験の最適化と明確なマーケティング目的の設定が共通点です。診断コンテンツは業種を問わず、マーケティング成果に直結する有効な手法であることがわかります。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
診断コンテンツ作成のポイントと成功の秘訣

目的とターゲットの明確化
診断コンテンツ作成の出発点は、明確な目的設定とターゲットの具体化です。
何を達成したいのか(例:リード獲得、ブランド認知向上、購買促進など)を具体的にし、その目標をKPIで数値化して設定します。また、ターゲットユーザーは年齢や性別、興味関心、課題感などのペルソナを詳細に定めることで、響く設問設計や結果提供につながります。
目的とターゲットを明確にしないと、ユーザーの期待と離れてしまい成果が得にくいため、ここは最も重要なステップです。
響く設問設計と診断ロジック構築
設問はターゲットに刺さる内容で、わかりやすく具体的に作ることが大切です。
選択肢は多すぎず4〜5つ程度に絞り、ユーザーの迷いを減らしましょう。ロジックはフローチャート型(回答に応じて分岐)や得点型(回答ごとにポイントをつけ総合点で結果判定)を使い分け、診断結果が的確で納得感がある設計を心がけます。
結果にはユーザーが満足しやすい説明や、関連商品・サービスへの誘導(CTA)を設けると効果的です。
ユーザー体験を高めるUX設計
診断の質問数や画面遷移が多すぎず、直感的に操作できるUIデザインが重要です。
スマホ利用者が多いためモバイル最適化は必須で、レスポンシブ対応、タップしやすいボタン配置、読み込み速度の最適化もユーザー満足度に直結します。
結果画面はビジュアルを工夫しSNSでの共有を促す仕掛けや、診断後の行動導線もスムーズにすることでエンゲージメント向上につながります。
継続的なデータ分析とPDCAサイクルの重要性
診断開始後は設定したKPI(例:コンバージョン率、滞在時間、SNSシェア数など)を定期的に分析し、ユーザーデータや行動ログをもとに改善ポイントを抽出します。
PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回し続けることで、設問内容やロジック、UI/UXを最適化し続け、常に効果を高めることが重要です。
ユーザーフィードバックも取り入れるとより実態に即した改善ができます。
プロモーション戦略と拡散施策
診断コンテンツ単体での成功だけでなく、SNSやメール、広告などを活用した多角的なプロモーションが成功のポイントです。
特にSNSでの共有を促進するために、シェアボタンの設置や、結果の面白さや意外性を演出することが効果的です。SNS投稿を動機付けるための特典やキャンペーン連携も活用されます。
さらに、SEO対策としてはキーワードを意識した導入文や結果ページ設計も忘れてはなりません。
これらのポイントを押さえれば、ユーザーの参加意欲を高めつつ、目的達成につなげられる診断コンテンツの制作が可能になります。
▼下記の資料では、自社のマーケティング施策に活用できる最適な『診断体験』の作り方を5つのステップで解説しています。診断コンテンツはユーザー自身の潜在的なニーズを深掘り、自分が求めるサービスや理想像をより明確にできるため、CVRの向上や診断コンテンツを通じてLTVを向上させることが可能です。自社のサービスで診断体験を通じたユーザー獲得や認知拡大をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
おすすめ診断コンテンツツール5選

Interviewz(インタビューズ)の活用メリット
Interviewzは、ヒアリングDXを実現するノーコードの診断コンテンツツールで、ユーザーの入力負担を軽減することに特化しています。回答は択一や複数選択形式で直感的に操作でき、画像や動画の挿入も可能でユーザー体験が優れているのが特徴です。
入力支援機能(EFO)により、過去の入力内容の自動反映や予測入力で離脱率を低減し、コンバージョン率の向上に貢献。既存データと診断結果を紐づけられるため、マーケティングに活用しやすく、HubSpotやSlack、スプレッドシートなどと連携可能です。
Webサイトやアプリにタグで簡単に埋め込め、導入のスピード感も魅力です。初期費用なしで月額3万円から利用可能で、コンサル支援も受けられます。全体として、手軽かつ効果的にユーザー情報を集め、分析し、活用したい企業に最適なツールとしておすすめです。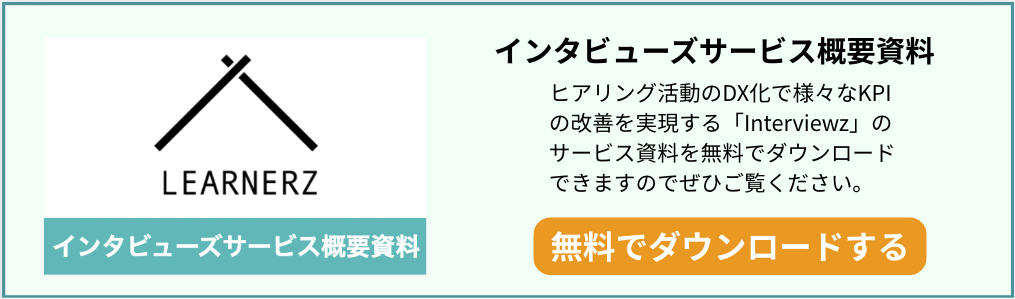
formrun(フォームラン)
formrunは、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で問い合わせフォームや診断コンテンツを簡単に作成できるツールです。
ノーコードで非エンジニアでも利用可能で、作成したフォームはモバイル対応済みで操作性も良好。複数のテンプレートが用意されており、初心者でもスムーズにスタートできます。
フォームの公開やSNS連携、データの自動集計・管理が容易で、顧客対応の効率化に役立ち、リード獲得に強みがあります。
参考:formrun
Questant(クエスタント)
QuestantはWebアンケートや診断コンテンツ作成に特化し、豊富なテンプレートとカスタマイズ機能を備えています。
特徴は詳細な分析機能で、回答データのクロス集計やグラフ可視化が簡単に行え、マーケティング施策の精度を高めます。リアルタイムでデータを確認できるため、迅速な意思決定につなげられるでしょう。
多様な質問タイプに対応し、複雑なロジック設定も可能で、属人化しない運用がしやすい点が強みです。
参考:Questant
typeform
typeformは美しいデザインと優れたユーザー体験(UX)に定評がある診断・アンケート作成ツールです。直感的に操作できるインターフェースとモバイル最適化により、高い回答率が期待できます。
質問は1画面ずつ表示されるため、回答者の集中を促し、離脱を防ぎます。柔軟なカスタマイズ機能や多言語対応も備えており、ブランドイメージに合ったフォームを作成可能です。
多数の外部ツールとの連携も可能で、マーケティングオートメーションとの組み合わせに強力です。
参考:typeform
Lフレックス
Lフレックスはチャットボット形式の診断コンテンツ作成ツールで、対話型のインターフェースが特徴です。
ユーザーとの自然な会話体験を提供し、ゲーム性を持たせたコンテンツ設計が可能です。質問の分岐も柔軟に設定でき、診断精度を上げることができます。
チャット形式なので親しみやすく、スマートフォン利用者にも使いやすいことが魅力。こうした対話的UXによりエンゲージメントを高め、結果のシェアも促進します。
参考:Lフレックス
以上のように、それぞれのツールには特徴と強みがあります。その中でも、特にInterviewzはヒアリングDXに注力して入力支援や多様な連携機能が充実しているため、業務効率化と顧客のストレス軽減に最適な診断コンテンツツールと言えるでしょう。
▼以下の資料は、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較した資料です。ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。 類似サービスの比較を行いたい方は、ぜひ参考にしてください。
診断コンテンツ導入時の課題とトラブル回避策

プライバシー保護とデータ管理のポイント
診断コンテンツで収集するユーザーの個人情報や回答データは、厳格なプライバシー保護が必要です。
まず、個人情報保護法やGDPRなどの関連法規を遵守し、ユーザーから明確な同意を得ることが重要です。データは最小限に収集し、必要に応じて匿名化や暗号化を施すことで不正アクセスや漏洩リスクを低減します。
プライバシーポリシーの明示やユーザーがデータ管理に関して問い合わせや削除を求めるための窓口を設置し、透明性を保つことが信頼獲得に繋がります。また、安全なサーバー管理やアクセス制御など技術面でも対策を講じるべきです。
コスト管理とサポート体制の比較
診断コンテンツ導入には制作・運用にかかるコスト管理が欠かせません。
初期の制作費用だけではなく、導入後のメンテナンス費用やツール利用料、改善対応のための工数も考慮し、予算を計画しましょう。サポート体制も重要で、特に技術的トラブルや運用上の問題解決を迅速に行えるかどうかが成功のポイントです。
導入予定のツールやサービスのサポート契約内容を比較し、無料トライアルや導入事例を確認することで、安心して長期運用できる環境を選ぶことが推奨されます。信頼性の高いサポートはトラブル抑止と改善の迅速化に寄与します。
ターゲットに刺さるコンテンツ作成の難しさ
ターゲットのニーズや心理に響く診断コンテンツ作成は簡単ではありません。
まずペルソナ設定を精緻に行い、どのような問題解決を望んでいるのか、何に興味を持つのかを明確にしましょう。設問文も専門用語を避け、わかりやすく具体的に設定し、回答の選択肢は多すぎずユーザーのストレスを抑えることが重要です。
加えて、適切な診断ロジックで的確な結果を導く必要があり、不適切な設計はユーザーの信頼を損ないます。さらに、多様なユーザープロファイルや利用環境に対応するUX設計も求められるため、調査・テストと継続的改善が不可欠です。
効果測定と改善施策の継続
診断コンテンツは導入後の効果測定とPDCAサイクル運用が成功のポイントです。
KPI(リード獲得数、滞在時間、シェア数など)を設定し、定期的にデータを分析しましょう。分析結果を踏まえて、質問内容の見直し、診断ロジックの調整、結果表示の改善、UXの向上などを継続的に実施し、ユーザー満足度とコンバージョン率の向上を図ります。
ユーザーフィードバックの活用や、新たなマーケットトレンドの反映も効果的です。こうした継続的な改善によって、診断コンテンツの質を高めることが可能です。
これらのポイントを踏まえた慎重な運用が、診断コンテンツ導入時の課題を克服し、トラブルを未然に防ぐ秘訣となります。
▼下記の資料では、実際にアンケートを作成する際に回答率の高いアンケートを作成するために『どんな項目があるばべきか』『回答率の高いアンケートの特徴』など、実例を交えながら解説しています。
アンケート作成でお悩みのある方は、下記の資料を参考にしながら効果的ななアンケートの作成方法を確認してみてください。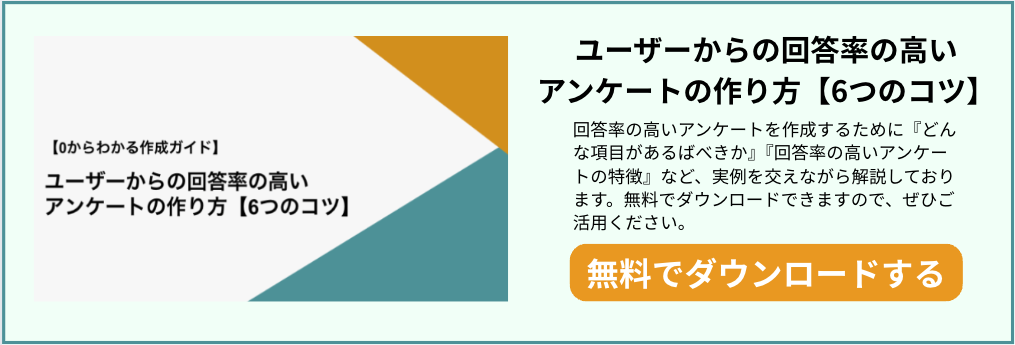
診断コンテンツの主な形式とロジック

一問一答形式vs.チェックシート形式
一問一答形式は、1画面に1つの質問を表示し、回答するごとに画面が切り替わる形式です。ユーザーは直感的に回答でき、スピーディーに診断を進められます。また、次の質問への期待感を高め、ゲーム性を感じさせることができます。
一方、チェックシート形式は複数の質問を一覧で表示し、まとめて回答する形式です。設問数が多い場合や細かい項目設定が必要な場合に適しています。ユーザーは全体を把握しながら回答でき、回答の修正も容易です。選択には診断の目的や設問数、ユーザー体験を考慮する必要があります。
フローチャート(分岐)形式とスコア形式の比較
フローチャート(分岐)形式は、ユーザーの回答に応じて次の質問が変化する形式です。個別性の高い結果を導き出せ、ユーザーの興味を維持しやすいという特徴があります。
一方、スコア形式は各回答に点数を割り当て、合計点で結果を決定する形式です。多様な要素を考慮した総合的な診断が可能で、結果の段階付けがしやすいメリットがあります。
フローチャート形式は直感的で分かりやすい反面、設計が複雑になる可能性があります。スコア形式は設計が比較的容易ですが、ユーザーに計算過程が見えにくいのがデメリットです。
診断コンテンツによるマーケティング効果以外のメリット3つ

診断コンテンツでは、マーケティングリサーチ以外にもさまざまな効果が得られます。商品やサービスの認知度が低い、リードの獲得率が低い、などの課題を抱えている場合は診断コンテンツを活用すると良いでしょう。
診断コンテンツのマーケティング効果以外のメリットは以下の3つです。
- ブランドや商品への理解を深める
- リード獲得
- 購買意欲を高める
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
1.ブランドや商品への理解を深める
1つ目に紹介するメリットは、ブランドや商品・サービスへの理解を深めてもらえる点です。
診断コンテンツの診断結果を表示する際に、おすすめの自社商品やサービスを提示すれば、まず商品やサービスの存在に気づいてもらえるでしょう。さらに商品やサービスを販売している企業やブランドについて、知ってもらえる機会にもなります。
また理解促進のために診断コンテンツを活用する場合は、商品・サービスの機能やベネフィットなどを十分に伝える必要があります。その際、長文で説明するよりも、画像を用いて端的に説明すると良いでしょう。
無駄な言葉は並べず最も伝えたい魅力が伝われば、勧誘や営業をすることなく成約につながる可能性が高まります。結果的に営業スタッフの人件費削減にもつながったり、社員数が少ない小規模企業でも十分な効果が得られたりと、企業にとって大きなメリットにもつながる場合があります。
2.リード獲得
2つ目に紹介するメリットは、リード獲得につながる点です。
そもそもリード獲得とは、商品やサービスを購入する可能性がある見込み客や潜在顧客を獲得することを指します。ターゲット層にダイレクトに該当する顧客はもちろん、見込み客や潜在顧客を獲得することで、売上向上につながりやすいでしょう。
また顧客獲得だけではなく、人材獲得の場でも診断コンテンツを活用できます。たとえば、求人サイトなどで適職診断を設けると、自分に合う求人を探す方の後押しにもなるでしょう。診断結果を知るために会員登録を必須とすると、自然な流れでリード獲得となります。
求人サイト以外の場合でも、診断結果を知るために会員登録を促せば、リード獲得の効果が得やすいでしょう。
3購買意欲を高める
3つ目に紹介するメリットは、ユーザーの購買意欲を高められる点です。
診断コンテンツを利用する方の中には、自分に合う商品やサービスなどを知りたいという目的の方が多くいます。ユーザーの悩みを解決できるような商品をおすすめすることで、そのまま購入に至るケースも期待できるでしょう。
またさまざまな商品やサービスを扱っている企業の場合、すべての商品について理解してもらうことは難しいでしょう。
そのようなときに診断コンテンツを活用すれば、ユーザーが自分に合った商品を知った流れで、「他にどんな商品があるんだろう」と他の商品に興味を持ってもらえる可能性があります。
診断結果で商品やサービスを推奨する際には、そのまま契約に進めるフォームのURLを貼っておくと良いでしょう。するとユーザーが自分で購入フォームを探す手間が省けるので、ユーザーのストレスフリーにもつながります。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。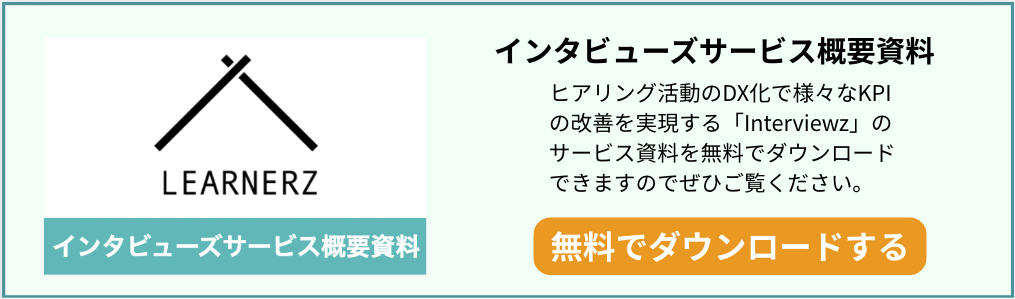
診断コンテンツの導入にはインタビューズのヒアリングツールがおすすめ!
診断コンテンツは、自己認識をしたい、自己表現をしたい、他人が利用しているものに興味を持つ、などの人が持っているであろう性質から、マーケティングリサーチに有効であるといえます。
特に診断結果には、SNSでシェアできるボタンを設けることができ、診断コンテンツとSNSとの相性は抜群です。
またマーケティングリサーチ以外にも、ブランドや商品への理解を深めてもらえたり、購買意欲を高めてもらえたりするなど、さまざまなメリットがあります。
企業の中には、診断コンテンツと動画を組み合わせて、質問の背景にどのような企業であるか、どのような商品を扱っているかをイメージづけるための動画を流しているところもあります。
これから診断コンテンツの導入を考えている方は、メリットや効果だけではなく、実際に診断コンテンツを活用している事例も参考にしましょう。
効果的なマーケティング施策の実行には、インタビューズのヒアリングツールがおすすめです。インタビューズは14日間のトライアル期間中もすべての機能を無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。
フォントやカラーの変更、アニメーション追加、外部ツールや分析コードの設置も簡単で、SEO対策やCVR向上、データ活用がスピーディーに行えます。さらに、プレビュー機能で事前確認し即時反映できるため、マーケティング施策の自由度と実行スピードが大幅に向上し、リード獲得や効果測定改善を加速させることが可能です。
ぜひ下記の資料から、インタビューズの詳しい機能をご確認ください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。