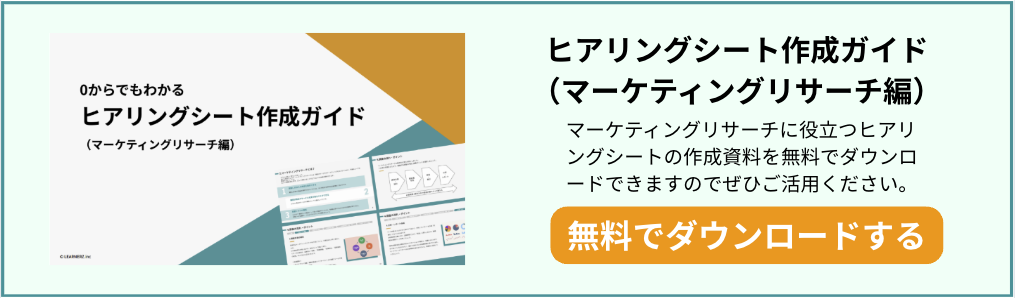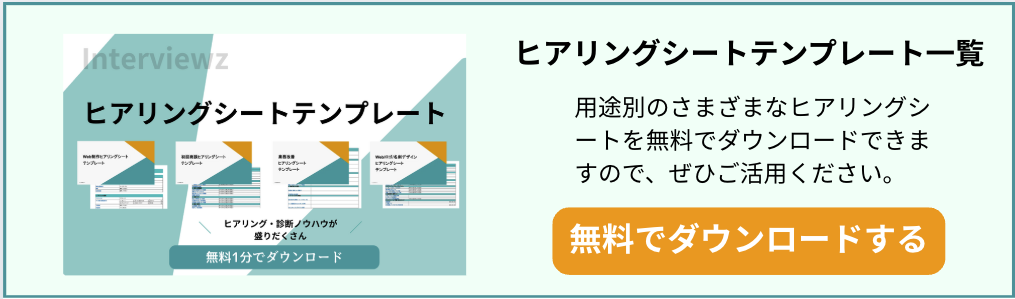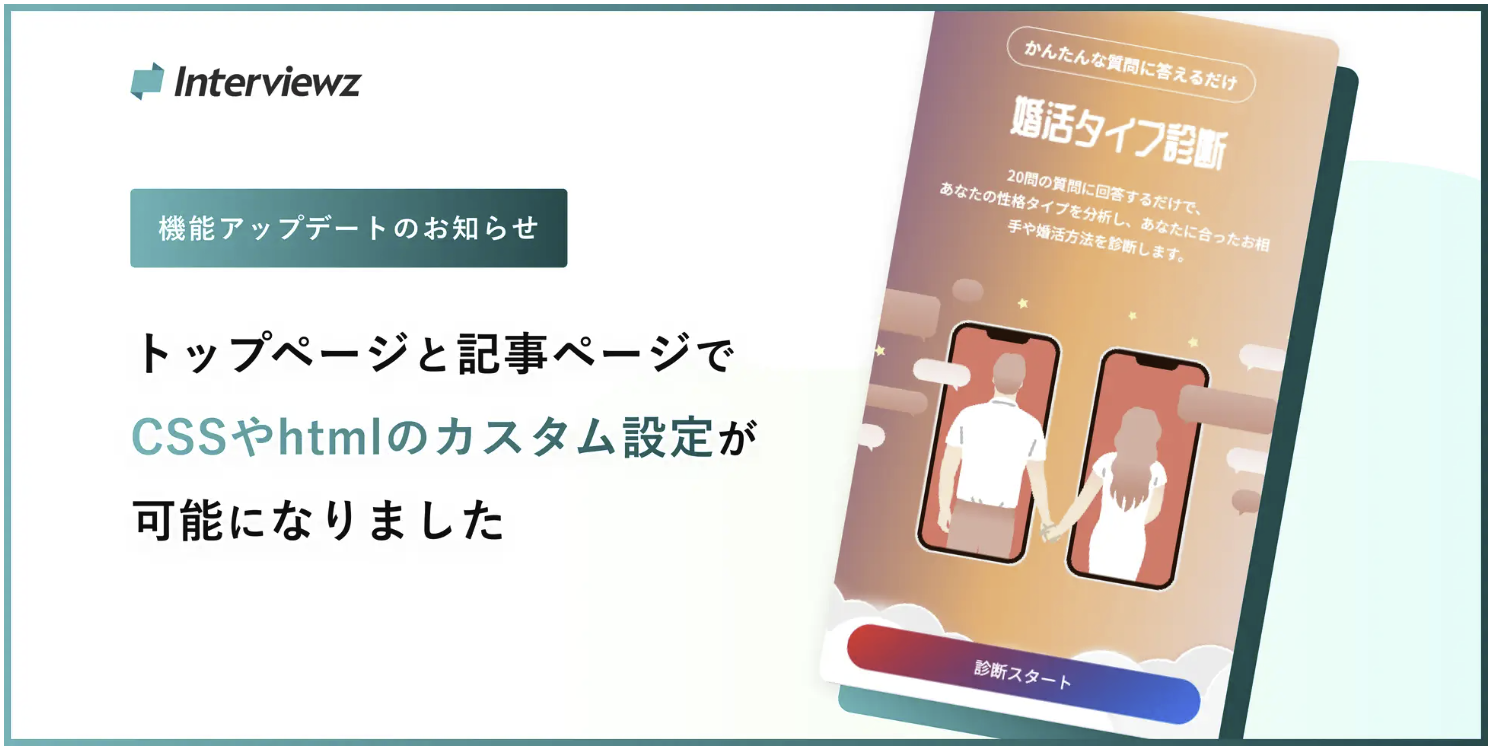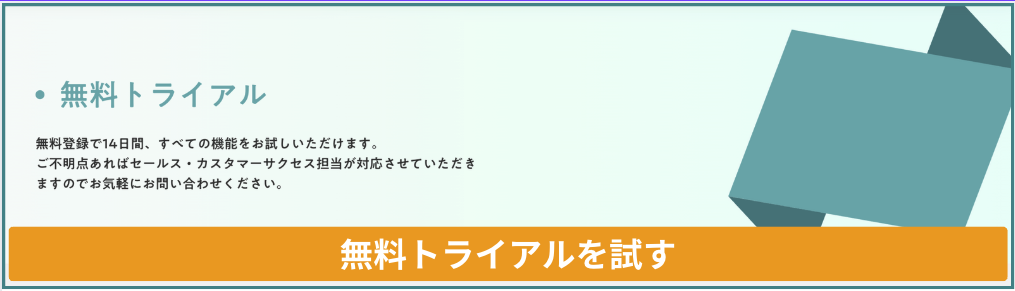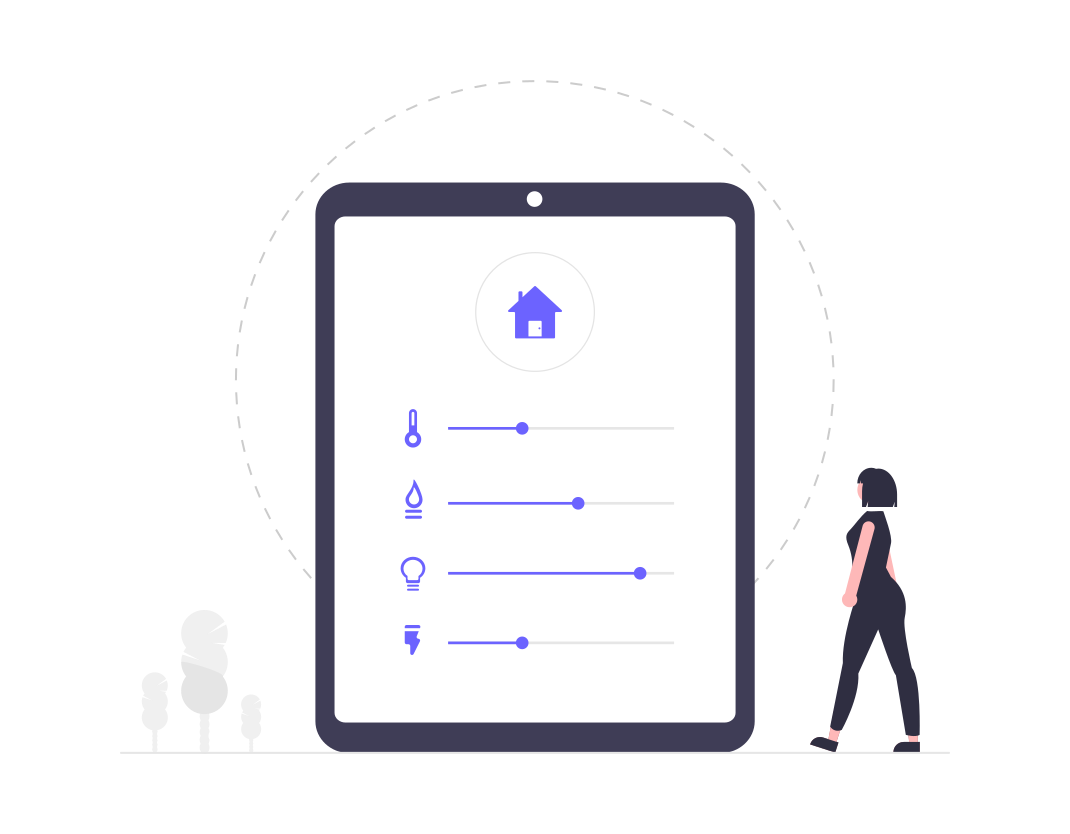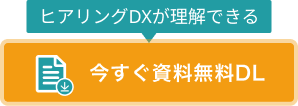展示会でヒアリングシートが重要な理由と効果的な質問事項5つを解説【テンプレート付き】
- 2023/01/04
- 2025/08/12

目次
展示会は貴重なビジネスチャンスですが、来場者と効果的にコミュニケーションを取ることが成功のポイントです。
しかし、短時間で相手のニーズを正確に把握し、後の商談につなげるのは容易ではありません。
そこで活用したいのが「ヒアリングシート」です。
適切な質問を事前に準備し、記録を取ることで、商談の精度を高めることができます。さらに、質問の内容次第で、顧客の関心度を引き出すことも可能です。
そこで今回は、展示会でヒアリングシートを活用する重要性と効果的な質問事項5つをテンプレート付きで解説しますので、ぜひ参考にしてください。
ヒアリングシートとは?展示館で活用する重要性も解説

展示会では、多くの来場者と短時間で会話を交わすため、後々の営業活動に役立つ情報を適切に収集することが重要です。そのために活用したいのが「ヒアリングシート」です。
アンケートとは異なり、ヒアリングシートは商談に向けた具体的な情報を記録するツールです。適切に活用すれば、商談の成功率を高めることができます。
ヒアリングシートとアンケートの違い
ヒアリングシートとアンケートはどちらも情報収集の手段ですが、目的が異なります。
アンケートは統計データを取得し、顧客全体の傾向を把握するためのものです。一般的に選択式の質問が多く、広範囲の意見を収集できます。
一方、ヒアリングシートは個別の顧客情報を収集し、営業活動に活かすためのものです。訪問者の具体的な課題や要望を把握することで、最適な提案につなげることができます。
展示会では、商談を見据えた情報収集が求められるため、ヒアリングシートの活用が効果的です。
ヒアリングシートで得られる情報

展示会でヒアリングシートを活用することで得られる重要な情報を以下の表にまとめました。各情報が営業活動や商談にどのように活用できるかも詳しく記載していますので、ぜひ参考にしてください。
| 項目 | 詳細情報 | 活用方法 |
|---|---|---|
| 来場者の会社名・業種・役職 | 企業名、業界、担当者の役職などを記録することで、ターゲット市場を分析できる。 | 来場者の業種・業界別の傾向を把握し、営業戦略の最適化に活用。役職に応じたアプローチ方法の選定。 |
| 現在抱えている課題やニーズ | 企業が直面している問題や求めているソリューションをヒアリングする。 | 顧客のニーズに即した製品・サービスを提案。共通する課題を分析し、新たなソリューション開発のヒントとして活用。 |
| 導入検討の時期 | 製品・サービスの導入予定時期を把握し、営業活動の優先度を決定する。 | 短期検討の顧客には積極的な提案を実施し、長期検討の顧客には定期的な情報提供を行う。 |
| 関心のある製品・サービス | 展示会で興味を示した製品や機能を記録し、商談の際に活用する。 | 顧客の興味に合わせた資料提供や具体的な活用事例の紹介を行い、購買意欲を高める。 |
| 予算感や意思決定の流れ | 予算の有無や決裁者の情報を取得し、提案内容を調整する。 | 予算内での最適な提案を実施。意思決定フローを把握することで、適切なタイミングでフォローアップを行い、成約率を向上させる。 |
▼下記の資料は、自社のマーケティング戦略の立案を効率化するためのヒアリングシートの作り方をステップ別に解説した資料です。この資料では、マーケティングの課題や調査目的、今回の調査で明らかにしたい事柄を明確にすることができますので、ぜひご活用ください。
展示会でヒアリングが効果的な理由とメリット5つ

展示会でヒアリングを行う理由と、そのメリットは主に以下の5つです。
- 来場者のニーズを正確に把握できるから
- 有望なリードを選別できるから
- 商談の成功率を向上させることができるから
- 展示会後のフォローアップを効率化できるから
- 顧客との信頼関係を構築できるから
それぞれの理由について詳しく解説します。
1.来場者のニーズを正確に把握できるから
展示会に訪れる顧客は、何かしらの課題や興味を持っています。
ヒアリングを通じて、顧客が求めている具体的なニーズを掘り下げることで、より最適な提案が可能です。また、表面的な質問だけでなく、背景にある問題や導入の障壁なども把握できるため、商談に向けた準備がしやすくなります。
適切なヒアリングを行うことで、顧客は「自社の課題を理解してくれている」と感じ、信頼関係を構築しやすくなるでしょう。
2.有望なリードを選別できるから
展示会では、多くの来場者と接することになりますが、全員が即座に商談につながるわけではありません。ヒアリングを通じて、導入の可能性が高いリードを選別できれば、効果的な営業戦略を立てることが可能となります。
例えば、ヒアリングによって「すぐに予算を確保できる」「導入の意思決定者が訪問している」といった情報を得られれば、成約率の高い顧客に絞ってフォローアップできます。
このように、限られた営業資源を効率的に活用するためにも、ヒアリングによるリード選別が欠かせないのです。
3.商談の成功率を向上させる
ヒアリングで収集した情報をもとに商談を進めることで、より顧客のニーズに合った提案が可能となります。事前に課題や予算、導入検討時期などの詳細を把握しているため、商談時にスムーズな話し合いができます。
また、ヒアリングを通じて顧客の興味関心を引き出しておけば、展示会後の商談でも「この企業は自社のことをよく理解している」と感じてもらえる可能性が高くなります。その結果、提案が受け入れられやすくなり、商談の成功率が向上します。
4.展示会後のフォローアップを効率化できる
展示会後に適切なフォローアップを行うためには、ヒアリングで収集した情報が不可欠です。例えば、ヒアリングを通じて「導入時期は半年後」「競合製品を比較検討している」などの情報が得られれば、その顧客に合わせたフォローアップが可能です。
一般的なフォローアップメールを送るのではなく、個別の関心に合わせた情報提供を行うことで、商談につながる可能性を高められるでしょう。
展示会の成果を最大化するためにも、ヒアリングを活用したフォローアップ戦略が重要です。
5.顧客との信頼関係を構築できる
ヒアリングは単なる情報収集ではなく、顧客との信頼関係を築く重要な機会でもあります。
展示会に訪れた顧客は、何らかの期待を持っていますが、一方的な説明だけでは満足度が低くなることもあります。ヒアリングを通じて「貴社の課題に共感し、最適な解決策を考えたい」という姿勢を示せば、顧客は「この企業は信頼できる」と感じ、関係性が深まりやすいでしょう。
このように、単なる営業活動を超えて長期的な関係を築くことができる点も、ヒアリングの大きなメリットです。
▼下記の資料では、実際にアンケートを作成する際に回答率の高いアンケートを作成するために『どんな項目があるばべきか』『回答率の高いアンケートの特徴』など、実例を交えながら解説しいます。
アンケート作成でお悩みのある方は、下記の資料を参考にしながら効果的ななアンケートの作成方法を確認してみてください。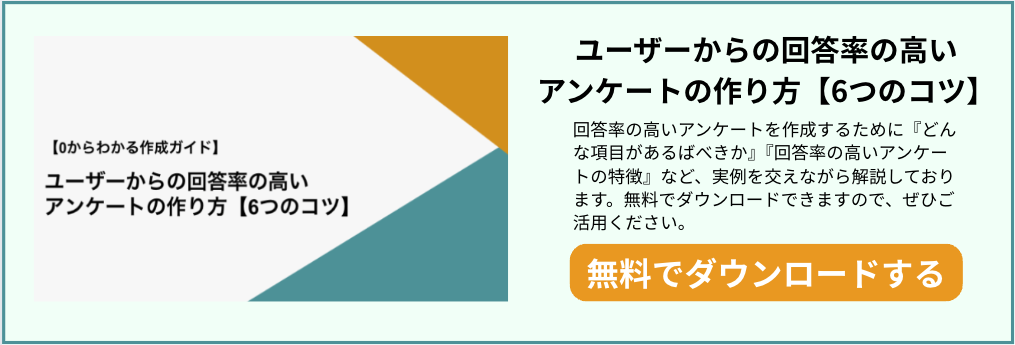
展示会ヒアリングシートの主な質問事項5つ

展示会のためにヒアリングシートを用意する際には、質問事項を決めておく必要があります。
ヒアリングシートの主な質問事項は以下の5つです。
- 来場目的
- 観覧したブース
- 悩みや課題
- 現在の導入状況
- 来場者の情報
今回の記事で紹介しているヒアリングシートのテンプレートに、上記の質問事項を入れて利用することをおすすめします。
1.来場目的
来場目的では、来場者がなぜ展示会に訪れようと思ったのか理由を聞きます。
想定できる回答には、「興味のある商品があったから」「サービスの乗り換えを検討しているから」などがあるでしょう。文字を記入する手間を省くために、あらかじめ想定できる回答を選択肢として設けておくこともおすすめです。
2.観覧したブース
観覧したブースでは、今回展示会で設けたブースの中で観覧したものを聞きます。
展示会のブースがいくつも分かれている場合は、このような質問事項を設けると良いでしょう。来場者がスムーズにどのブースなのか答えられるように、各ブースに番号を振り分けることもおすすめです。
3.悩みや課題
悩みや課題では、来場者が抱えている悩みなどを聞きます。
来場者の中には、展示会にある商品やサービスへの乗り換えを検討している方がいれば、情報収集を目的に来場する方もいます。どのような目的で来場したのか見極めるためにも、悩みや課題を具体的に聞く必要があるでしょう。
また来場者との会話の中で悩みや課題を聞き出すことで、課題を解決できる商品やサービス提供に自然とつながる可能性があります。
4.現在の導入状況
現在の導入状況では、来場者の方が既に別のサービスを導入しているのか、もしくはこれから導入を検討しているのか聞きます。
特に現在既にサービスを導入している場合は、導入しているサービスを導入して来場者の課題が解決できているのか確認しましょう。
もし、別のサービスを導入していても来場者の抱える課題を解決しきれていない場合は、自社サービスを提案する余地があります。
自社サービスでできることや今導入しているサービスとの比較をした上で、乗り換えを勧めるのも良いでしょう。
ただし、強引なサービス勧誘をしてしまうと来場者に不信感を与えてしまい、悪い口コミを広められる可能性があるので注意しましょう。
5.来場者の情報
来場者の情報では、来場者の所属している部署や抱えているタスクについてヒアリングします。
BtoBの展示会の場合、来場者がどの部署に所属しているのか、抱えているタスクはどのようなものか知っておくことで話を進めやすくなります。
来場者の情報を知るには、名刺交換がおすすめです。
名刺には来場者の役職などが記載されている可能性が高いため、スムーズに来場者の情報を把握できます。
▼ビジネスにおいて「ヒアリングの質」は、その後の提案の精度や成果を大きく左右します。しかし、実際の現場では以下のような悩みがよく聞かれます。
- 「何をどこまで聞けばいいのかわからない」
- 「毎回ヒアリングの内容が属人化していて、標準化できない」
- 「新人や外注メンバーにヒアリング業務を任せにくい」
- 「案件ごとに内容が違うため、毎回シートをゼロから作ってしまう」
下記のヒアリングシートテンプレートでは、上記のような現場の課題を解決するためにWeb制作・採用・営業・ブランディングなど、用途別・目的別にヒアリング項目が体系立てられており、誰でもすぐに使えるフォーマットになっています。
さらに、テンプレートには診断ノウハウやチェック項目も付属していますので、ヒアリングを通じて「課題の構造化」や「次のアクション提案」まで自然に導けます。
展示会で役立つヒアリングシートのテンプレート
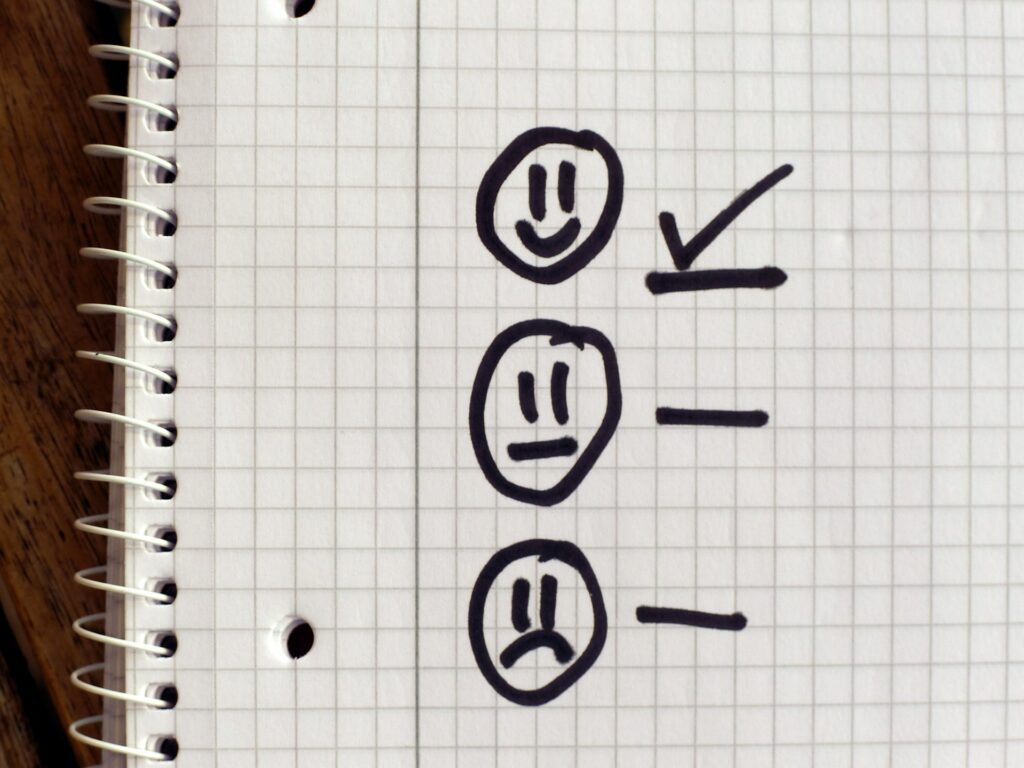
以下では、展示会ヒアリングで役立つテンプレートを紹介します。
| 項目 | 記入内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 来場者情報 | 会社名 / 業種 / 役職 / 氏名 | 企業規模や担当者の立場を把握 |
| 訪問目的 | 情報収集 / 導入検討 / 競合比較 | 展示会訪問の目的を明確に |
| 現在の課題・ニーズ | 具体的な課題や改善点 | 企業が求めるソリューションを把握 |
| 関心のある製品・サービス | 興味を示した製品・機能 | 営業提案の参考に |
| 導入検討の時期 | すぐに導入 / 半年以内 / 1年後 | 商談の優先順位を決定 |
| 予算感 | 具体的な予算 / 未定 | 提案内容の調整に活用 |
| 意思決定者 | 社内での決裁者 / 決裁フロー | 営業アプローチの計画に活用 |
| 展示会後のフォロー希望 | 資料送付 / デモ希望 / 商談希望 | フォローアップ方法を明確に |
企業によってヒアリングしたい内容が異なる場合や質問事項を付け足したい場合は、上記をカスタマイズしてお使いください。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
展示会でヒアリングを行う際のポイント

展示会でヒアリングを行う際には、ただ質問をするだけではなく、上手にヒアリングを行うためのポイントも把握しておくと良いでしょう。
展示会でヒアリングを行うポイントは主に以下の4つです。
- 予算と導入時期のヒアリングを控える
- 来場者独自の課題を聞く
- 回答を誘導しないようにする
- シンプルでわかりやすい言葉で質問する
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
1.予算と導入時期のヒアリングを控える
1つ目に紹介するポイントは、予算と導入時期のヒアリングを控えることです。
予算や導入時期などの売り込みを目的としたような質問は、アンケートよりもヒアリングで聞き込むほうが良いでしょう。しかしヒアリングとはいえ、踏み込んだ質問ばかりをすると、来場者からの評判を下げてしまう恐れがあります。
また予算や導入時期をヒアリングしたい場合には、来場者の導入状況や本当に自社サービスを検討したいのかを見極めた上で、ヒアリングを行いましょう。
2.来場者独自の課題を聞く
2つ目に紹介するポイントは、来場者独自の課題を聞くことです。
悩みや課題を聞く質問項目を設ける際、来場者すべてがこちらが想定している回答をするとは限りません。来場者の悩みから新たな発見をするケースもあり、中には独自の悩みや課題を抱えている方もいます。
また来場者独自の課題を聞き出すには、相手の気持ちを理解しながら話を進めましょう。まずは相手の心を開く必要があります。
3.回答を誘導しないようにする
3つ目に紹介するポイントは、回答を誘導しないようにすることです。
こちらが求めている回答を引き出すために、無理やり回答を誘導しないように注意しましょう。無理に回答を誘導した場合、有益な情報とはいえません。
またヒアリングを行う際には、基本的に話を聞く側の立場でいましょう。はじめにヒアリングを行うときには、来場者が「はい」か「いいえ」で答えられるような簡単な質問からしてみてください。
4.シンプルでわかりやすい言葉で質問する
4つ目に紹介するポイントは、シンプルでわかりやすい言葉で質問することです。
言葉自体がシンプルでわかりやすくても、文章が長くかえってわかりにくくなってしまう恐れがあります。相手が経営者であったりビジネスに携わったりしている方でも、ビジネス用語を多用しないように注意しましょう。
また展示会を何度も行う機会がある場合には、開催するたびにヒアリングシートの見直しを行うことをおすすめします。よりシンプルでわかりやすい言葉にできないか、他の部署の方にも確認してもらうと良いでしょう。
▼以下の資料は、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較した資料です。ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。 類似サービスの比較を行いたい方は、ぜひ参考にしてください。
展示会後のアフターフォロー手法3つ

展示会でヒアリングを行った後は、アフターフォローを行うと商談成立や案件獲得につながる可能性があります。ヒアリング内容をもとに、アフターフォローを行うべきか見極めましょう。
展示会後に行うアフターフォローの手法は主に以下の3つです。
- 電話
- メール
- 手紙
それぞれの手法の特徴について詳しく解説します。
1.電話
展示会でのヒアリングの後は、ヒアリング時に直接話を伺っていることもあり、電話でのアフターフォローがしやすいです。
会場でのヒアリングでは、短時間でしか対応できないので、来場者一人ひとりのニーズを把握するのは困難です。電話でのアフターフォローをきっかけに、よりヒアリングの延長として深い話ができると考えられます。
ただし、すべての来場者に電話をかけるのは時間や手間がかかるので、すぐに商談が成立しそうな顧客を見極めて電話をかけると良いでしょう。
2.メール
展示会後のアフターフォローで時間や手間がかからない手法として、メールでのフォローがおすすめです。
メールでのアフターフォローは、電話よりもスムーズに実施できる、多くの方に対して一斉送信できる、人手がいらないなどのメリットがあります。効率的にアプローチできるので、アフターフォローに時間をかけたくない方におすすめです。
ただし、メールを送信してすべての方が開封するとは限りません。ヒアリングの際に少しでも案件につながると感じた顧客には、メールではなく電話でのアプローチをおすすめします。
3.手紙
展示会後のアフターフォローとして、手紙を送る手法もあります。
メールよりも手紙のほうが丁寧に対応していると感じてもらいやすく、丁寧な印象から自社のイメージアップにもつながるでしょう。手紙はメールよりも開封率が高く、メールのように見逃してしまう恐れも低いです。
ただし、顧客一人ひとりに手紙を送信する際には、電話やメールよりもコストがかかってしまいます。さらに手紙が手に届くまで数日かかってしまうので、最新情報を提供する際には電話またはメールでのアプローチがおすすめです。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。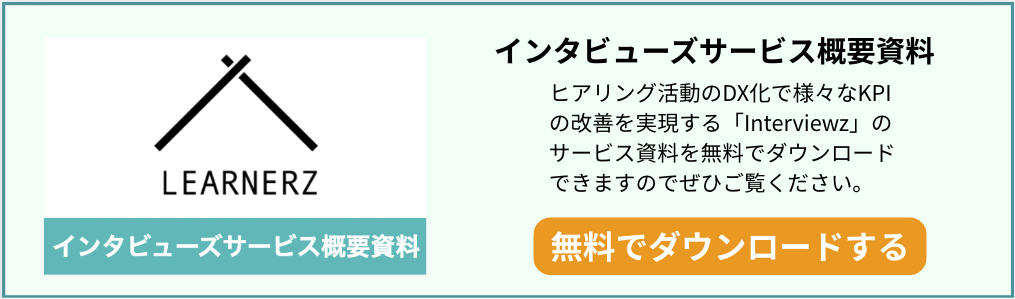
展示館のヒアリングはインタビューズのヒアリングシートがおすすめ!
インタビューズのヒアリングシートは、展示会での情報収集を効率化し、商談の成功率を高めるために最適なツールです。
まず、事前に質問事項を設定できるため、来場者のニーズや課題を的確に把握できます。また、調査員が記入する形式のため、来場者は回答の手間がなく、スムーズなヒアリングが可能です。
さらに、ヒアリングデータをデジタル管理できるため、展示会後のフォローアップが容易になり、営業活動の精度が向上します。アンケートよりも売り込み感が少なく、自然な会話の中で情報を収集できる点も大きなメリットです。
展示会での成果を最大化するために、インタビューズのヒアリングシートを活用してみてはいかがでしょうか。
▼Interviewz(インタビューズ)に新機能が追加され、CSSカスタマイズとHTMLタグ埋め込みが可能となりました。これにより、自社ブランドのデザインに合わせた診断・ヒアリングページを最短1日で構築できます。
フォントやカラーの変更、アニメーション追加、外部ツールや分析コードの設置も簡単で、SEO対策やCVR向上、データ活用がスピーディーに行えます。さらに、プレビュー機能で事前確認し即時反映できるため、マーケティング施策の自由度と実行スピードが大幅に向上し、リード獲得や効果測定改善を加速させることが可能です。
ぜひ下記の資料から、インタビューズの詳しい機能をご確認ください。
また、インタビューズは14日間のトライアル期間中もすべての機能を無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。