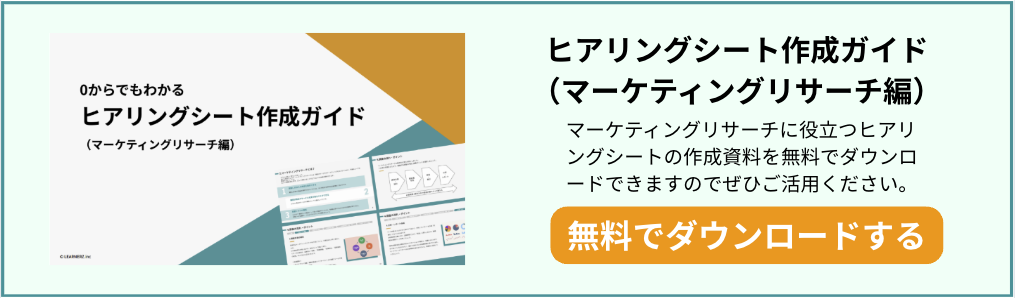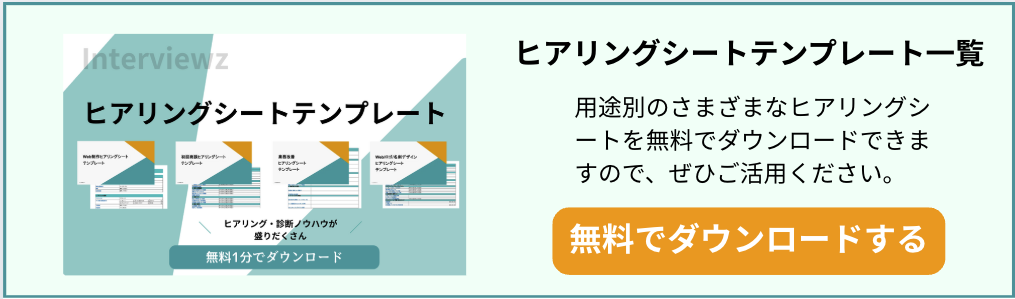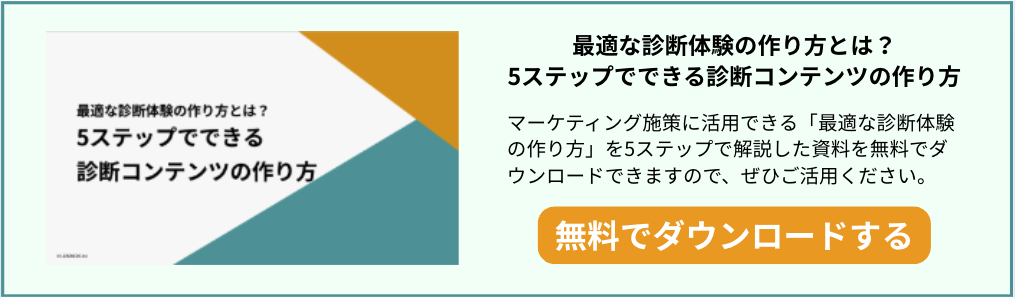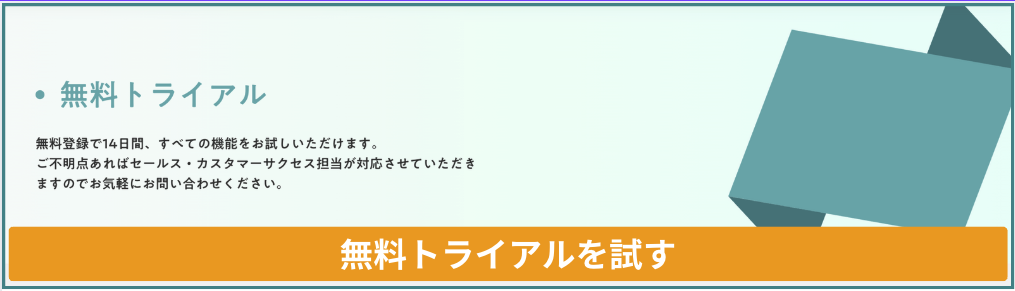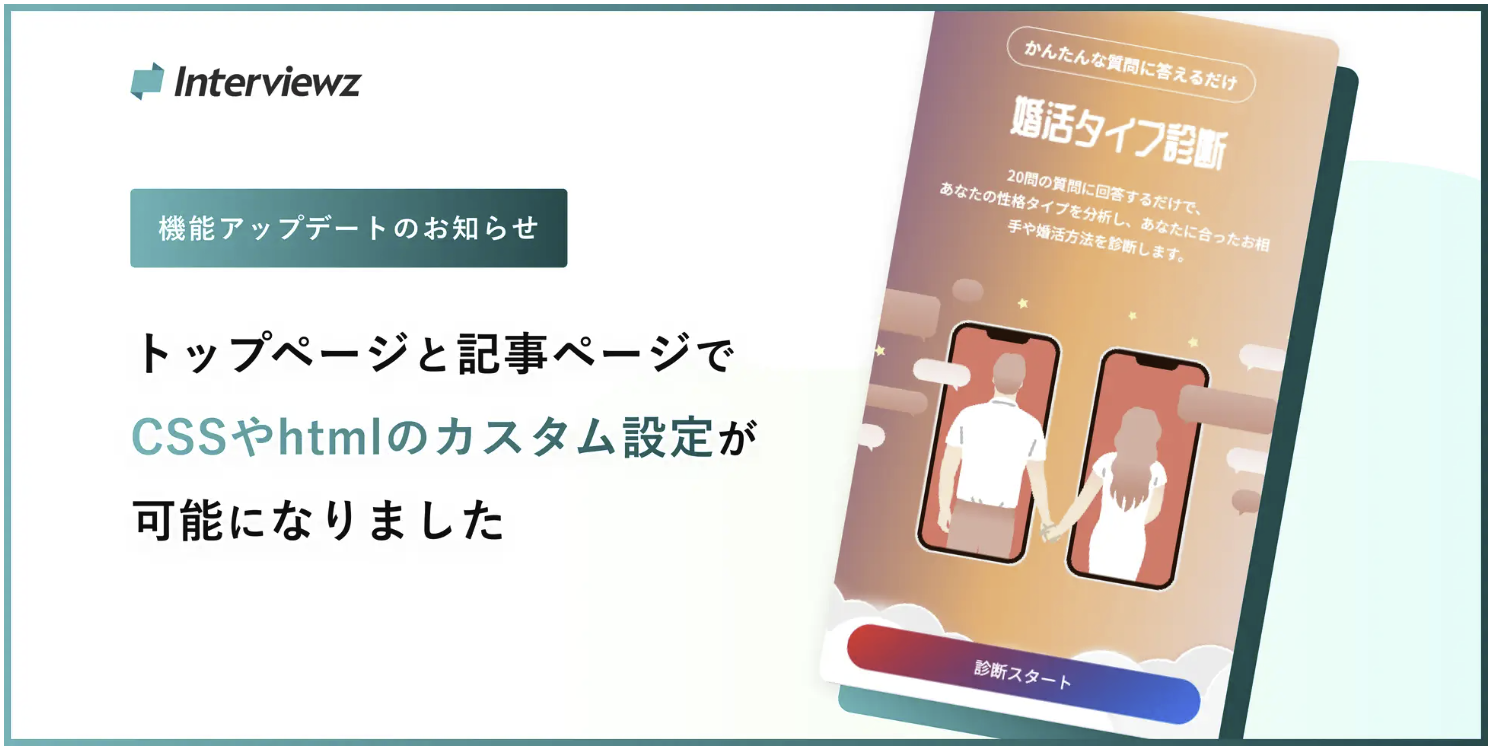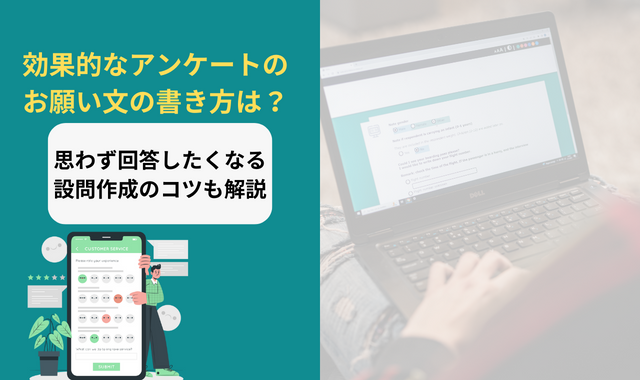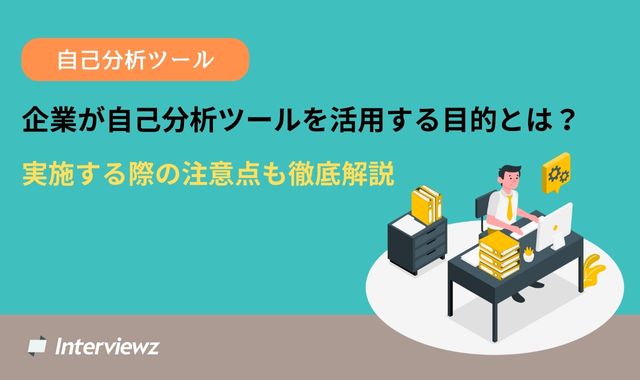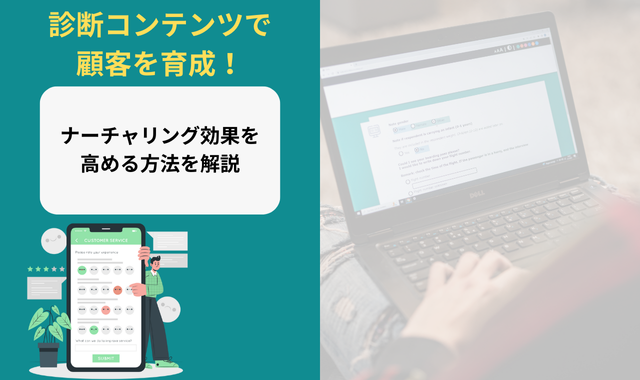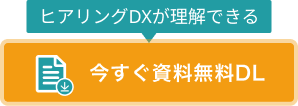利用者アンケートのテンプレートと作り方|診断ツールのメリットと活用法も解説
- 2025/09/27
- 2025/09/27

目次
利用者アンケートは満足度や改善点を把握し、サービス向上や新たな施策を検討する上で欠かせない要素となります。
効果を最大化するには目的を踏まえたテンプレートの活用と回答しやすい設計が重要です。
さらに診断ツールを組み合わせることで精度の高いデータを収集でき、分析や改善施策に直結します。
この仕組みを取り入れることで効率的かつ継続的な改善につながります。
そこで今回は、利用者アンケートのテンプレートと作り方はもちろん、診断ツールのメリットと活用法も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
利用者アンケートとは?目的と必要性を整理

利用者アンケートは、サービス利用者の体験、満足度、課題を数値と自由回答で把握する調査手法です。
利用者アンケートの目的は、「現状把握」「原因分析」「改善案の評価」の3点に大別でき、短期的な満足度の把握から長期的なサービスの方向性検討まで幅広く活用できます。
重要なのは、目的に応じて設問を絞り込み、回答時間を短く保つことです。
インタビューズの診断機能と連携することで、回答データの集計・可視化を即座に実現し、施策の優先度を明確化できます。
利用者アンケートの基本的な役割
基本的な役割は、主に次の3つです。
第一に「現状把握」で、利用者がどの点で満足しているか、どの点が不満かを把握します。
第二は「原因の特定」で、不満の背景や利用状況、利用シーンを掘り下げ、改善の軸を特定します。
第三の「改善の検証」では、施策を実施した後の効果を測定し、次のアクションを決定します。
インタビューズを使えば、設問設計のガイドラインや回答の組み合わせ、診断連動のテンプレートを活用して、これらの3つの役割を効率良く達成できます。
顧客満足度調査との違い
利用者アンケートは、「特定のサービス体験や利用状況に焦点を当てる」点が顧客満足度調査と異なります。
顧客満足度は総合的な評価を示す指標になりがちですが、利用者アンケートは特定の機能、場面、導線、サポート体験など、要素別の満足度や課題を深掘りします。
インタビューズでは、診断ツールと連携させることで、全体像と要素別の詳細を同時に把握できるため、改善の優先順位付けがより現実的になるのが強みです。
サービス改善につながる活用のポイント
利用者アンケートを活用するコツは、「設問の目的を設計段階で明確化すること」と「データを実行可能なアクションに落とし込むこと」です。
回答率を高める工夫、偏りを避ける設問設計、回答時間の短縮など実務的な工夫が重要です。
インタビューズのテンプレート機能や自動生成機能を活用すれば、業種や目的に合わせた設問セットを素早く作成でき、改善案の優先度付けにも診断連動のデータを活かせます。更に定期的なデータ収集と継続的改善サイクルを組み込むと、組織の成長につながります。
利用者アンケートの作り方と基本手順

利用者アンケートの調査手順は、「目的の明確化→対象の決定→設問設計→回答形式の選定→実施→集計・分析→改善案の作成・実行・評価」という流れです。
まず目的を1〜2項目に絞り、対象を絞ることで回答データの質を高めましょう。
設問設計では、選択肢は具体的で漏れのないように作成し、自由回答は深掘りの余地を残します。回答形式は、定量と定性のバランスをとると洞察が深まります。
インタビューズの設問テンプレートを活用すれば、素早く設計を開始できるためおすすめです。
調査目的を明確にする重要性
目的が不明確だと集計軸がブレてしまい、施策の優先度が曖昧になります。
例えば「新機能の受容性を測る」「使い勝手の課題を特定する」など、具体的な指標を設定します。
インタビューズの診断連動と組み合わせると、目的に沿った評価軸が自動生成・提案されるため、設計の迷いを減らせるでしょう。目的が定まっていれば、設問の数量は最小限に抑えつつ、必要な情報を漏れなく得られます。
回答対象とタイミングの決め方
回答対象は、利用者セグメント(新規・リピーター、年齢、地域、利用頻度など)を明確に設定しましょう。
タイミングは、利用後すぐ、一定期間後、サービス改修直後など、データの意味が最も高い時点を選びます。
インタビューズではイベントトリガー設定が可能で、特定の行動を取った直後に自動でアンケートを送ることが可能です。これにより、記憶の新鮮さを活かし、回答の信頼性を高められます。
設問内容の作り方と回答形式の選び方
設問は、自社の目的に合わせて定義しましょう。
定量的な評価にはリッカート尺度を、頻度や重要度には5段階を活用します。自由回答では、「体験の具体例」「改善してほしい点」「原因の仮説」など、掘り下げの糸口になる質問を配置します。
回答形式は、回答の負担を減らすために必須性を設けずオプションを分けることが有効です。
インタビューズの機能を使えば、診断連動の設問セットを自動生成し、設計ミスを防げます。
インタビューズで効率的に設計する方法
効率的な設計の要点は、「テンプレートの再利用」と「診断連動の活用」です。
業種別テンプレートを基に、目的に合わせて微調整するだけで高品質な設問が完成します。
また、回答データをリアルタイムで可視化するダッシュボードや、セグメント別の比較機能を活用すると、改善点が見えやすくなります。
さらに、回答率向上のための誘導文・案内文の最適化や、回答時間の短縮にも注意しましょう。
▼下記の資料は、自社のマーケティング戦略の立案を効率化するためのヒアリングシートの作り方をステップ別に解説した資料です。この資料では、マーケティングの課題や調査目的、今回の調査で明らかにしたい事柄を明確にできますので、ぜひご活用ください。
利用者アンケートのテンプレート|業種別3選

以下では、利用者アンケートのテンプレートを業種別に3つ紹介します。以下はいずれも簡潔な質問群の骨子です。
ITサービス
- どのような方法で当サービスを知りましたか?(Web広告、口コミなど)
- サービスの利用頻度は?(毎日、週に数回、月に数回、初めて)
- サービスの使いやすさを5段階で評価してください。
- 機能やサポートに関して改善してほしい点はありますか?(自由回答)
- 今後追加してほしい機能やサービスは?
- 総合的な満足度をお聞かせください。
- その他ご意見があればお書きください。
ITサービスに関するアンケートのコツ
ITサービス向けテンプレートは、機能利用・導線・サポート体験の3軸で構成するのが基本です。導入前の期待感、初期設定の難易度、安定性、障害時の対応、長期的な満足度を測る設問を組み込みます。自由回答には「改善してほしい機能」「運用のコツ」などを入れ、技術的な観点での改善案を引き出します。
小売・消費財
- 商品をどこで購入されましたか?(店舗、オンラインなど)
- 購入の決め手を教えてください。(品質、価格、ブランドなど)
- 商品のデザインや使い心地に満足していますか?(5段階評価)
- 商品を友人や家族に薦めたいと思いますか?
- 改善してほしい点やご意見があれば教えてください。
- 購入後のリピート意向はありますか?
- ご利用頻度について教えてください。
小売・消費財に関するアンケートのコツ
購買体験、店舗・ECの使い勝手、配送・返品体験、カスタマーサポートの応対品質を重点に置くのが基本です。リピート意向やブランド推奨意向を測る指標を組み込み、季節・イベント時の需要変動を捉える設問も設計します。自由回答では「商品ラベルの見やすさ」「サイトの検索性」など具体的な改善要望を集めます。
医療・ヘルスケア
- 商品やサービスをどのように知りましたか?
- 利用目的を教えてください。(健康維持、症状改善、美容など)
- 効果を感じた点、不満に思った点をお聞かせください。
- 使用方法や説明書の分かりやすさはどうでしたか?
- 今後も継続利用したいですか?理由もお聞かせください。
- サポート対応の満足度を5段階で評価してください。
- その他、ご意見やご希望があれば自由にお書きください。
医療・ヘルスケアに関するアンケートのコツ
医療・ヘルスケア分野では、利用者の安全感・信頼感、情報提供の適切性、アフターサポートの充実度を評価するのが基本です。法令遵守や個人情報の取り扱いに配慮した設問設計が重要です。難解な専門用語を避け、理解しやすい言葉で設問を作成します。自由回答には「医療情報の追加欲求」や「サービス利用時の不安点」を取り込みます。
これらは業種それぞれの利用者特性に合わせて、顧客満足や改善点の把握に適した質問例です。それぞれの業界ごとに商品やサービスの特性や顧客体験の確認ポイントが異なるため、アンケート設計時には目的に合わせてアレンジするのがおすすめです。
▼ビジネスにおいて「ヒアリングの質」は、その後の提案の精度や成果を大きく左右します。しかし、実際の現場では以下のような悩みがよく聞かれます。

- 「何をどこまで聞けばいいのかわからない」
- 「毎回ヒアリングの内容が属人化していて、標準化できない」
- 「新人や外注メンバーにヒアリング業務を任せにくい」
- 「案件ごとに内容が違うため、毎回シートをゼロから作ってしまう」
下記のヒアリングシートテンプレートでは、上記のような現場の課題を解決するためにWeb制作・採用・営業・ブランディングなど、用途別・目的別にヒアリング項目が体系立てられており、誰でもすぐに使えるフォーマットになっています。
さらに、テンプレートには診断ノウハウやチェック項目も付属していますので、ヒアリングを通じて「課題の構造化」や「次のアクション提案」まで自然に導けます。
利用者アンケートのテンプレート活用法

よく使われる定番テンプレート項目例
回答者属性、利用頻度、総合満足度、機能別満足度、課題点、改善要望、NPS、自由回答の具体要望、今後の利用意向、推奨意向などを基本項目として組み込みます。
業種別には、導線体験・サポート・価格満足度、品質・信頼性などの指標を追加します。
業種別に活用できるアンケート設計例
ITサービスは「導入前の期待・設定の難易度・障害対応・長期満足度」、小売は「購買体験・配送・返品・ブランド推奨」、医療は「情報提供の分かりやすさ・安全性・アフターサポート」を軸に設問を組み立てます。設問数を絞りつつ、自由回答で深掘りを行う設計が有効です。
選択式と自由回答式の効果的な組み合わせ
定量の選択式は傾向把握に適し、自由回答は原因の仮説・具体的改善案の抽出に活用します。組み合わせのコツは、選択式で得られたデータを自由回答で補足する構造です。
インタビューズの診断連動テンプレートは、この組み合わせを標準化してくれるため、設計の手間を大幅に削減できます。
診断コンテンツと連動したテンプレートの強み
診断コンテンツと連動させると、回答者の属性・進行状況に応じて最適な設問セットを提示できます。これにより回答の精度が向上し、分析の信頼性も高まります。
インタビューズは診断連動機能を活用して、利用者の現状認識と改善の優先度を同時に提示する設計が可能です。
▼下記の資料では、自社のマーケティング施策に活用できる最適な『診断体験』の作り方を5つのステップで解説しています。
診断コンテンツはユーザー自身の潜在的なニーズを深掘り、自分が求めるサービスや理想像をより明確にできるため、CVRの向上や診断コンテンツを通じてLTVを向上させることが可能です。
自社のサービスで診断体験を通じたユーザー獲得や認知拡大をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
利用者アンケート設計のチェックポイント

回答率を上げるための工夫
回答率向上には質問数を絞り、わかりやすい言葉で簡潔に設計することが重要です。
初めは答えやすい質問から始め、徐々に難しい設問に移る流れを作ると心理的負担を軽減できます。また、選択肢は重複や抜け漏れのないMECEを意識し、シンプルにまとめることが効果的です。
インセンティブや回答時間の目安明示も効果的です。
偏りや誘導を防ぐ設問設計
誘導的な文言や偏りを避けるため、中立的で客観的な表現を心掛けましょう。「~と思う」「~に違いない」といった断定的な表現は避け、フラットな質問文にすることが重要です。
選択肢もバランス良く揃え、どの選択でも偏らない配慮が必要です。複数視点から質問を組み立てることでバイアスを減らしましょう。
短時間で回答できる工夫
アンケートの質問数は必要最低限に絞り、自由記述は特に重要な1~2問に限定します。選択式を多用し、回答操作の手間を減らすのがコツです。
また、スマホやPCいずれでも操作しやすいUI設計や途中スキップ機能を入れることで、回答途中の離脱も防げます。
回答時間の目安を明示し、意欲的に答えてもらう工夫も有効です。
ツール連携による設計精度向上
アンケートツールの連携機能を活用し、CRMやBIツールと結びつけることで属性情報の精度が上がり、より的確なターゲティングが可能となります。さらに、回答状況のリアルタイム確認や回答漏れのチェックが容易となり、修正や改善を迅速に行うことが可能です。
インタビューズなど高度な設問カスタマイズや分析支援機能付きツールの活用も設計精度向上に貢献します。
▼下記の資料では、実際にアンケートを作成する際に回答率の高いアンケートを作成するために『どんな項目があるばべきか』『回答率の高いアンケートの特徴』など、実例を交えながら解説しています。
アンケート作成でお悩みのある方は、下記の資料を参考にしながら効果的ななアンケートの作成方法を確認してみてください。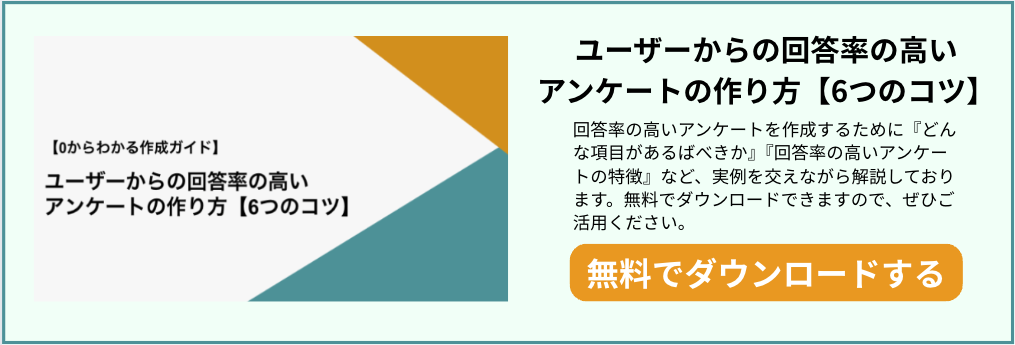
利用者アンケート結果の分析と活用方法

分析の基本ステップと集計方法
データの前処理として、欠損値の扱い、回答時間の検証、セグメント別の集計を行いましょう。
定量データは平均値・中央値・分布を把握し、傾向を可視化します。一方、定性データはテキストマイニング的に要点を抽出し、自由回答の共通テーマを抽出します。
インタビューズのダッシュボード機能を使えば、セグメント別・時系列別の比較が直感的にできるため、効果的です。
サービス改善への反映の仕方
分析結果を具体的な改善アクションに落とし込むことが大切です。改善は優先度の高い項目から着手しましょう。
施策案は、実現可能性・影響の大きさの観点で評価します。改善の効果を測るための指標(KPI)を事前に設定し、定期的に再評価することが重要です。
インタビューズのテンプレート連携機能を使えば、施策案とKPI、責任者、実施時期を一元管理でき、実行の漏れを防げます。
データをマーケティング施策に活用する方法
利用者アンケートデータは、顧客理解を深める宝庫です。
セグメント別のニーズを把握して、ターゲット広告、コンテンツ戦略、パーソナライズされた提案に活用しましょう。診断データと組み合わせれば、潜在的な機会の特定にも役立ちます。
インタビューズの連携機能を使えば、分析結果をそのままマーケティングワークフローに取り込み、施策の実行までのリードタイムを短縮できます。
定期的なデータ活用で継続的改善を実現
定期的なデータ収集と分析を組織文化として根付かせると、改善サイクルが回りやすくなります。
年間・半期・四半期などのタイムボックスごとに分析テーマを設定し、成果を可視化するのがおすすめです。
インタビューズの自動レポート機能や定期配信設定を活用すれば、関係部署へ最新データをタイムリーに共有でき、意思決定のスピードが上がります。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
利用者アンケートでよくある課題と解決策

回答率が低い場合の対応策
回答率向上の基本は、回答の負担を減らすことと、回答者にとって価値を伝えることです。短時間で完結する設問設計、明確な回答の動機づけ、適切なリマインドのスケジュール設定が有効です。
インタビューズのリマインド機能や回答時間の通知設定を活用することで、回収率を安定させられます。
設問数が多すぎる場合の改善方法
設問の絞り込みがポイントです。目的に直結する設問だけを厳選し、自由回答の余地を残す設計に変更しましょう。
設問の順序を見直し、最重要設問を先頭に置くと回答完了率が向上します。
インタビューズのテンプレート機能を使えば、冗長な設問を自動的に削除・再配置して、短時間回答を実現可能です。
集計・分析の属人化を防ぐ工夫
データの標準化とガバナンスが重要です。共通の設問定義、回答形式、セグメント定義を事前に組織内で共有しましょう。
自動集計・レポート機能を活用して、個人の分析能力に依存せず、組織内の誰でもデータを使える状態を作ることが重要です。
インタビューズの共有ダッシュボードは、チーム全体で同じデータを見られるため、共通理解の形成に役立ちます。
インタビューズで課題解決を支援する仕組み
インタビューズは設問テンプレートの自動生成、診断連動、データ連携、リアルタイム分析といった機能を備えています。これにより、設計工数を大幅に削減し、分析の精度を高め、改善サイクルを速く回すことができます。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。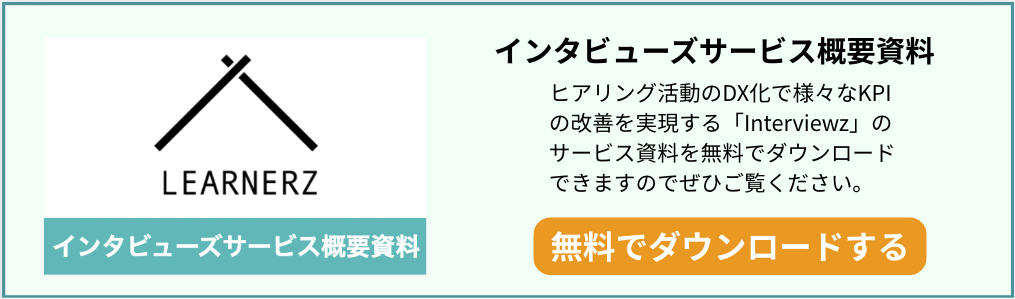
インタビューズのヒアリングツールで利用者アンケートを進化させるメリット

テンプレート自動生成で作業効率を向上
テンプレート自動生成機能を活用すると、業種・目的に応じた設問セットを短時間で作成できます。過去のデータと比較・組み合わせることで、再現性の高い設計が可能です。
これにより、設計フェーズの時間を節約し、現場はデータに基づく迅速な意思決定に集中できます。
顧客理解を深める診断連動の強み
診断連動は、回答者の属性や現状の把握に合わせて設問を適切に出し分け、深層の理解へと導きます。複数の診断パスを用意することで、特定の課題に対する洞察を強化し、施策の適用範囲を広げられます。
回答精度を高める設問設計支援
設問設計支援機能により、曖昧さを減らし、回答の取りこぼしを減らします。適切な誘導表現を避け、中立な表現で選択肢を並べ、自由回答には具体的なガイドをつけることで、回答者の理解度を高め、回答の信頼性を高めます。
改善サイクルにつながるデータ分析機能
データ分析機能によって、施策の効果を定量的に評価できます。KPIの追跡、セグメント別の差異分析、時系列での傾向把握など、改善の効果を可視化します。これにより、継続的な改善サイクルを組織に根付かせ、サービスの競争力を高めることが可能です。
インタビューズは14日間のトライアル期間中もすべての機能を無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。
▼Interviewz(インタビューズ)に新機能が追加され、CSSカスタマイズとHTMLタグ埋め込みが可能となりました。これにより、自社ブランドのデザインに合わせた診断・ヒアリングページを最短1日で構築できます。
フォントやカラーの変更、アニメーション追加、外部ツールや分析コードの設置も簡単で、SEO対策やCVR向上、データ活用がスピーディーに行えます。さらに、プレビュー機能で事前確認し即時反映できるため、マーケティング施策の自由度と実行スピードが大幅に向上し、リード獲得や効果測定改善を加速させることが可能です。
ぜひ下記の資料から、インタビューズの詳しい機能をご確認ください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。