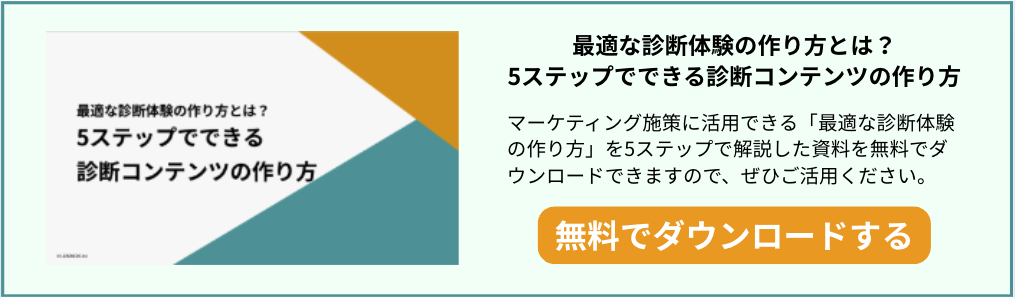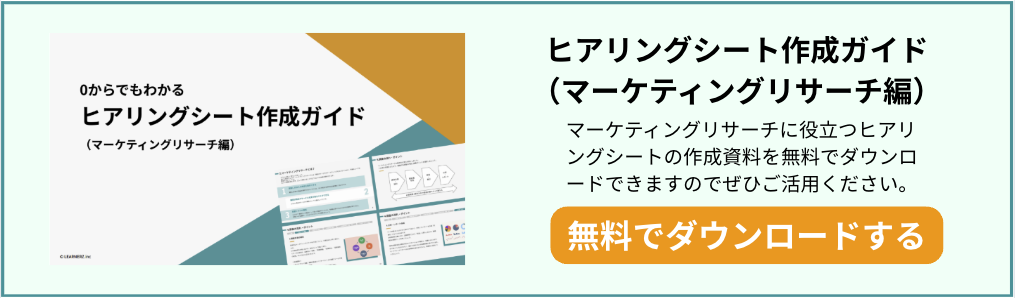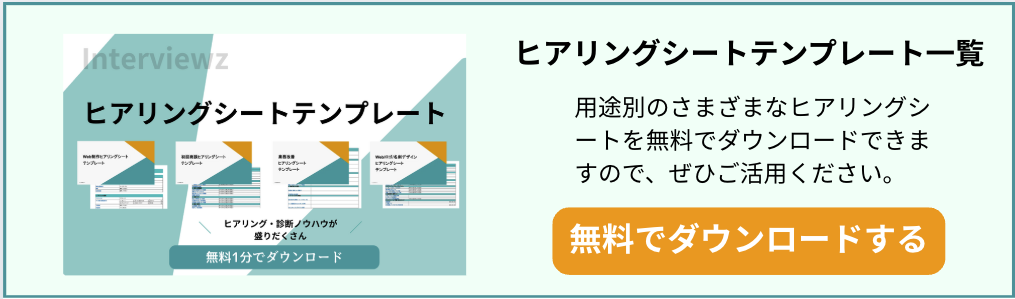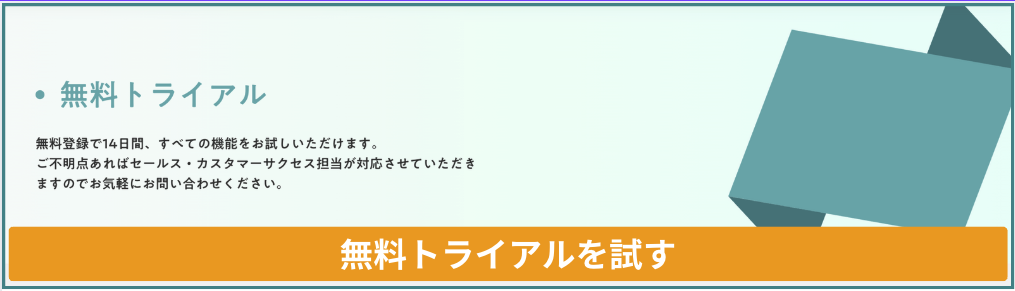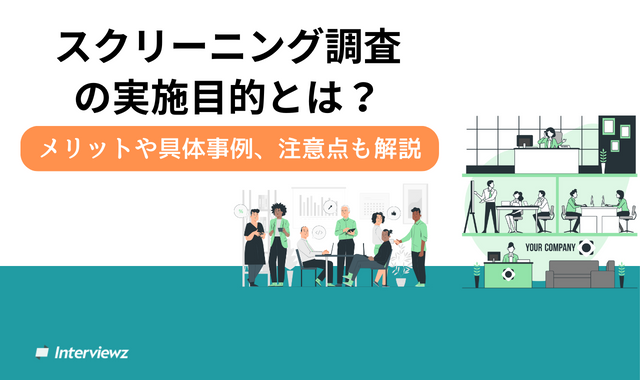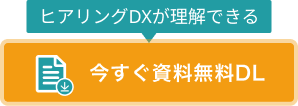顧客満足度調査に効果的なアンケートの作り方をテンプレート付きで解説
- 2024/04/24
- 2025/07/29
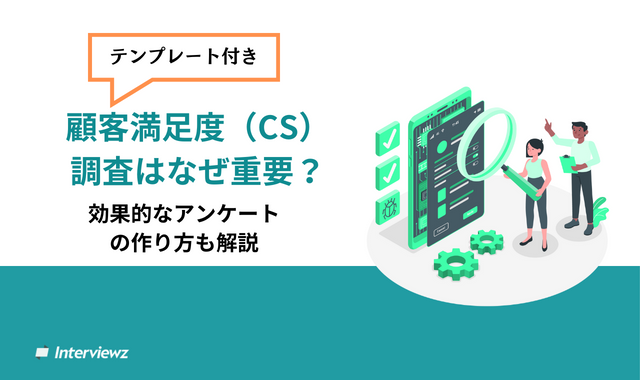
目次
顧客が本当に求めているものは何か。その答えを見つけるためには、顧客満足度調査(CS調査)が欠かせません。
しかし、ただ単にアンケートを配布するだけでは、顧客の心の声を聞き出すことは不可能です。なぜなら、効果的なアンケート作成は、顧客の隠れたニーズを掘り起こし、ビジネスの改善点を明確にするための鍵となるからです。
また、どのような質問が顧客の真の感情を引き出すのかや、どのようにして回答率を上げるのかについては、さまざまなテクニックやコツがあります。
そこで今回は、顧客満足度調査に効果的なアンケートの作成方法をテンプレート付きで解説します。これから顧客満足度調査を実施しようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
顧客満足度調査とは?効果を高めるアンケート設計の基本原則を解説

顧客満足度調査(CS調査)は、商品やサービスの利用者がどの程度満足しているか、またその理由を把握するための調査です。満足度を数値化し、顧客の率直な意見や不満点を収集することで、現状の課題や改善ポイントを明確にできます。
主な目的は、既存商品・サービスの改善、競合比較、信頼性向上、顧客ロイヤルティやリピート率の向上などです。
調査結果は、業務改善や経営戦略の見直し、新規顧客獲得にも活用でき、企業の成長に直結する重要なマーケティング施策となります。
顧客満足度調査の重要性
顧客満足度調査は、企業の成長や競争力強化に直結する非常に重要な施策です。調査を通じて顧客が商品・サービスに対して抱く率直な意見や潜在的なニーズを把握できるため、業務改善や新たな価値提供のヒントを得ることができます。顧客満足度が高まると、リピーターやロイヤルカスタマーの増加、顧客離れの防止につながり、安定した売上やLTV(顧客生涯価値)の向上が期待できます。
また、満足した顧客による口コミや紹介がブランド力や信頼性を高め、新規顧客の獲得や知名度向上にも寄与するでしょう。調査結果をもとにPDCAサイクルを回すことで、効率的かつ継続的にサービス品質を向上させることができ、競合との差別化や独自性の強化にも役立ちます。このように、顧客満足度調査は単なる現状把握にとどまらず、事業成長のための戦略的な基盤となるのです。
顧客満足度調査における効果的なアンケート設計の基本原則8つ

効果的なアンケート設計にはいくつかの基本原則があるため、以下にその主要なポイントを紹介します。
1.調査目的を明確にする
アンケート設計の出発点は、調査の目的を具体的に定めることです。「顧客の満足度を知りたい」だけでなく、「どのサービス要素がリピートに影響しているか」など、施策につながる目的を設定しましょう。目的が明確になることで、必要な設問や分析方法が見え、実用的なデータが得られます。
2.適切な調査対象の選定
調査目的に応じて、回答してもらうべき顧客層を明確にします。例えば新規顧客とリピーターでは聞くべき内容が異なります。ターゲットを絞ることで、信頼性の高いデータが集まり、分析精度も向上します。
3.質問の順序を工夫する
アンケートは「全体→詳細」や「過去→現在→未来」といった自然な流れを意識して設計しましょう。冒頭は答えやすい質問から始め、徐々に深掘りすることで、回答者の負担を減らし、回答率も高まります。
4.質問を簡潔で明確にする
設問は一文一意でシンプルにし、曖昧な表現や複数要素を含む質問は避けましょう。例えば「価格とデザインに満足していますか?」ではなく、それぞれ分けて聞くことで、正確なフィードバックが得られます。
5.回答者の属性を把握する
性別・年齢・利用頻度などの属性情報を設問に加えることで、セグメントごとの満足度や傾向を分析できます。属性設問は冒頭や最後にまとめて配置すると、全体の流れがスムーズになります。
6.回答形式を工夫する
選択式・5段階評価・自由記述など、内容に応じて最適な回答形式を選びましょう。選択式は集計しやすく、自由記述は具体的な意見や改善点を拾うのに有効です。バランスよく組み合わせることで、質と量の両面をカバーできます。
7.質問数は必要最小限に抑える
設問が多すぎると回答者の負担が増え、途中離脱や雑な回答の原因になります。10~15問程度を目安に、目的に直結する質問だけを厳選しましょう。自由記述は特に必要な場合のみに限定します。
8.バイアスを抑える設計を心がける
質問の順序や表現、インセンティブの有無などで回答が偏らないよう注意が必要です。中立的な言い回しや、先入観を与えない設問設計を心がけることで、より正確なデータが集まります。
顧客満足度調査の目的と効果

1.既存商品・サービスの改善のため
顧客満足度調査の最大の目的は、既存の商品やサービスに対する顧客の満足点・不満点を明確にし、現状の課題を把握して改善策を講じることです。調査を通じて顧客の声を直接収集することで、品質や機能、対応などの具体的な改善ポイントが明らかになります。これにより、商品やサービスの質を高め、顧客満足度の向上や新規顧客の獲得につなげることができます。
2.競合と自社を比較するため
顧客満足度調査は、競合他社と自社のサービスや商品がどの程度評価されているかを把握し、競争力を分析するためにも活用されます。業界のベンチマークや3C分析などを通じて、自社の強みや弱みを客観的に評価できるため、差別化戦略や市場でのポジショニングの見直しにも役立ちます。
3.商品・サービスの信頼性向上のため
調査結果をもとに業務改善を行い、顧客からのフィードバックを反映させることで、商品やサービスの信頼性を高めることができます。顧客の期待に応え続ける姿勢は、ブランドイメージや企業の信用力向上にも直結し、長期的な顧客ロイヤルティの醸成にもつながります。
4.顧客ロイヤルティやリピート率の向上
顧客満足度調査を通じて顧客の期待や要望を把握し、継続的な改善を実施することで、リピート率や顧客ロイヤルティの向上が期待できます。満足度の高い顧客は、再購入やサービスの継続利用、さらには口コミによる新規顧客の紹介など、企業の成長に大きく貢献します。
5.経営戦略やマーケティング施策への活用
調査で得られたデータは、経営戦略やマーケティング施策の立案にも活用されます。顧客視点での課題やニーズをもとに、商品開発やサービス設計、プロモーション活動の方向性を決定できるため、より実効性の高い施策展開が可能となります。
6.顧客との長期的な関係構築
顧客満足度調査は、重要顧客やリピーターとの長期的な関係を維持・強化するためにも重要です。顧客の声を継続的に収集し、改善を重ねることで、顧客との信頼関係が深まり、解約や離反のリスクを低減できます。
7.サービス品質や従業員対応の評価
調査を通じて、サービス提供の現場や従業員対応に対する評価も明らかになります。これにより、現場のモチベーション向上や教育・研修内容の見直し、サービス品質の均一化など、組織全体のレベルアップに役立ちます。
8.顧客体験(CX)の最適化
顧客満足度調査は、顧客が企業との接点でどのような体験をしているかを可視化し、CX(カスタマーエクスペリエンス)の最適化に直結します。顧客体験の質を高めることで、ブランド価値や市場での競争力強化にもつながります。
顧客満足度調査の効果

1.商品・サービス改善の加速
顧客満足度調査を実施することで、顧客の不満や期待を具体的に把握でき、商品やサービスの改善点が明確になります。例えば飲食店では、アンケート結果から「料理提供の遅さ」などの課題を発見し、スタッフ教育やオペレーション改善に取り組むことで、待ち時間短縮と顧客満足度向上を実現しています。このように調査結果をもとに迅速な改善策を講じることで、顧客体験の質を高められます。
2.リピーター・ロイヤルカスタマーの増加
調査結果を活用してサービスや商品を改善すると、顧客の信頼感や愛着が増し、リピーターやロイヤルカスタマーの増加につながります。再春館製薬の事例では、顧客満足度調査をもとにアフターケアを強化し、リピート率が向上しました。満足度の高い顧客は継続利用や口コミ紹介を通じて、企業の安定成長に大きく貢献します。
3.売上・LTV(顧客生涯価値)の向上
顧客満足度向上は、最終的に売上やLTVの増加にも直結します。例えばセイコーマートは、地域ニーズに合わせたサービス設計と顧客視点の徹底により、顧客満足度とLTVを最大化しています。満足度の高い顧客は再購入や高単価商品の利用に積極的になり、事業の収益性向上につながります。
4.ブランド価値・企業イメージの向上
顧客満足度調査を通じて顧客の声を反映し続ける企業は、ブランドへの信頼や好感度が高まります。スターバックスのように、従業員が自発的に顧客満足を追求する文化を醸成することで、ブランドの独自性や地域社会への貢献度も評価され、企業イメージの向上に結びつきます。
5.新商品・サービス開発のヒント獲得
顧客満足度調査は、顧客の潜在ニーズや新たな要望を発掘するきっかけにもなります。カフェチェーンでは、新メニュー開発時にアンケートを活用し、顧客の嗜好や期待に応じた商品を投入することで、売上増加や顧客満足度向上を実現しています。調査データは市場ニーズに即した新規事業やサービス設計にも役立ちます。
▼下記の資料では、自社のマーケティング施策に活用できる最適な『診断体験』の作り方を5つのステップで解説しています。診断コンテンツはユーザー自身の潜在的なニーズを深掘り、自分が求めるサービスや理想像をより明確にできるため、CVRの向上や診断コンテンツを通じてLTVを向上させることが可能です。自社のサービスで診断体験を通じたユーザー獲得や認知拡大をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
顧客満足度調査に効果的なアンケートの質問リスト

顧客満足度調査において効果的なアンケートを作成するためには、以下のような質問が推奨されます。これらの質問は、顧客の経験や意見を深く理解するために役立ちます。
効果的なアンケートの質問9つ
- 全体的な満足度に関する質問:「当社の商品/サービスに対する全体的な満足度を教えてください。」
- 具体的な評価に関する質問:「商品/サービスの品質、価格、カスタマーサービスについてどのように感じますか?」
- 改善点に関する質問:「当社の商品/サービスを改善するために、どのような点を改善すべきだと思いますか?」
- 再購入意向に関する質問:「将来的にもう一度当社の商品/サービスを購入する意向はありますか?」
- 推薦意向に関する質問:「友人や家族に当社の商品/サービスを推薦する可能性はありますか?」
- 利用頻度に関する質問:「当社の商品/サービスをどの程度の頻度で利用していますか?」
- カスタマーサポートに関する質問:「カスタマーサポートに対する満足度はどの程度ですか?」
- 購入動機に関する質問:「当社の商品/サービスを購入した主な理由は何ですか?」
- 競合比較に関する質問:「他社の同様の商品/サービスと比較して、当社の商品/サービスの優れている点は何ですか?」
これらの質問は、顧客の真の感情や意見を引き出し、企業がサービスや製品を改善するための貴重なフィードバックを得るために設計されています。
このように、アンケートは顧客の声を直接聞くための重要なツールであり、顧客満足度を高めるための改善策を導き出すために不可欠です。
▼下記の資料は、自社のマーケティング戦略の立案を効率化するためのヒアリングシートの作り方をステップ別に解説した資料です。この資料では、マーケティングの課題や調査目的、今回の調査で明らかにしたい事柄を明確にすることができますので、ぜひご活用ください。
効果的な顧客満足度アンケートの設問例とテンプレート

回答率が上がる基本情報・属性の質問例
顧客満足度アンケートの冒頭では、回答者の属性や基本情報を簡潔に尋ねることで、セグメントごとの分析が可能になります。回答率を上げるためには、選択肢を具体的かつシンプルにし、任意回答も活用しましょう。
- 氏名(任意)
- 性別(男性/女性/その他/無回答)
- 年齢(10代/20代/30代/40代/50代以上)
- 職業(会社員/自営業/学生/主婦・主夫/その他)
- 居住地(都道府県名)
- 利用頻度(毎日/週1回/月1回/初めて)
上記のような設問は、負担感を与えない範囲で必要なものだけを盛り込むのがポイントです。
サービス・商品満足度を測る設問テンプレート
満足度を測る設問は、5段階評価や選択式を中心に構成すると集計・分析がしやすくなります。
- 当社のサービス全体にどの程度満足していますか?(非常に満足/満足/普通/不満/非常に不満)
- 商品の品質についてどのように感じますか?(1~5段階評価)
- 価格設定についてご意見をお聞かせください(満足/普通/不満)
- カスタマーサポートの対応はどうでしたか?
- 使いやすさや利便性についての評価
上記のような設問を各項目ごとに設けることで、具体的な満足度の内訳を把握できます。
継続利用・推奨意向を把握する質問例
継続利用や推奨意向は、今後の顧客行動やロイヤルティを予測する上で重要な設問です。
- 今後も当社の商品・サービスを利用したいと思いますか?(利用する/きっかけがあれば利用したい/どちらともいえない/あまり利用したくない/利用しない)
- 当社の商品・サービスを友人や知人に勧めたいと思いますか?(はい/いいえ)
- 他社サービスと比較した際の再利用意向
このような設問はNPS(ネットプロモータースコア)にも活用されます。
自由記述・意見収集のための設問例
自由記述欄は、顧客の率直な意見や具体的な要望を収集するのに役立ちます。
- 当社の商品・サービスについてご意見・ご要望があればご記入ください
- 改善してほしい点や、今後期待することをお聞かせください
- ご利用時に印象に残ったエピソードや体験があれば教えてください
自由記述は必須にせず、回答しやすい雰囲気を作ることが重要です。
業界別・用途別テンプレートの活用法
業界や用途に合わせたテンプレートを活用することで、より的確なフィードバックが得られます。
例えば飲食店なら「料理の味」「店内の清潔さ」、ECなら「配送の速さ」「商品説明の分かりやすさ」など、業種特有の設問を追加します。医療や教育、BtoBサービスなどでも、それぞれの顧客体験に合わせた設問設計が効果的です。
テンプレートをベースに自社の目的や課題に合わせてカスタマイズすることで、実用性の高いアンケートが作成できます。
▼ビジネスにおいて「ヒアリングの質」は、その後の提案の精度や成果を大きく左右します。しかし、実際の現場では以下のような悩みがよく聞かれます。
- 「何をどこまで聞けばいいのかわからない」
- 「毎回ヒアリングの内容が属人化していて、標準化できない」
- 「新人や外注メンバーにヒアリング業務を任せにくい」
- 「案件ごとに内容が違うため、毎回シートをゼロから作ってしまう」
下記のヒアリングシートテンプレートでは、上記のような現場の課題を解決するためにWeb制作・採用・営業・ブランディングなど、用途別・目的別にヒアリング項目が体系立てられており、誰でもすぐに使えるフォーマットになっています。
さらに、テンプレートには診断ノウハウやチェック項目も付属していますので、ヒアリングを通じて「課題の構造化」や「次のアクション提案」まで自然に導けます。
顧客満足度調査に効果的なアンケートのテンプレート

以下では、顧客満足度調査に効果的なアンケートのテンプレートの一例を紹介します。ぜひ参考にしてください。
基本情報
- 名前:
- 年齢:
- 性別: (男性 / 女性 / その他)
- 職業:
製品・サービスに関する評価
- 当社の製品・サービスにどの程度満足していますか? (1: 非常に不満、5: 非常に満足)
– [ ] 1
– [ ] 2
– [ ] 3
– [ ] 4
– [ ] 5
- どの機能やサービスに満足していますか?(複数回答可)
– [ ] 製品の品質
– [ ] 価格
– [ ] カスタマーサービス
– [ ] 使いやすさ
– [ ] その他 (具体的に記述してください):
購入動機
- 当社の製品・サービスを選んだ主な理由は何ですか?
– [ ] 口コミ
– [ ] 広告
– [ ] 価格
– [ ] ブランドの信頼性
– [ ] その他 (具体的に記述してください):
改善点
- 当社の製品・サービスで改善してほしい点はありますか?(自由記述)
その他のコメント
- その他、当社に対してご意見・ご感想があればお聞かせください。(自由記述)
上記のテンプレートは、顧客からのフィードバックを効率的に収集するための基本的な枠組みを提供しています。必要に応じて質問を追加したり、特定の項目をカスタマイズしてご活用ください。
▼下記の資料では、実際にアンケートを作成する際に回答率の高いアンケートを作成するために『どんな項目があるばべきか』『回答率の高いアンケートの特徴』など、実例を交えながら解説しいます。
アンケート作成でお悩みのある方は、下記の資料を参考にしながら効果的ななアンケートの作成方法を確認してみてください。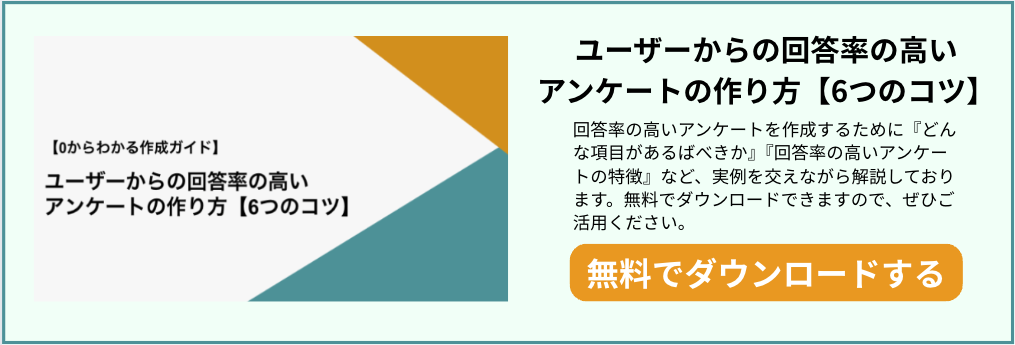
アンケート結果から顧客満足度の改善策を立案する方法

顧客満足度の改善策を立案するためには、アンケート結果を分析し、具体的な行動計画を作成する必要があります。そこで以下では、そのプロセスについて解説します。
1.データの集計と分析を行う
顧客満足度アンケートの結果を活用する最初のステップは、データの正確な集計と多角的な分析です。
まず、設問ごとに集計し、満足度・不満度の分布や平均値、中央値などの基本統計量を算出します。5段階評価やNPS(ネットプロモータースコア)などの定量データはグラフやヒートマップで可視化し、傾向を把握しましょう。
自由記述などの定性データは、テキストマイニングやキーワード抽出を行い、頻出ワードや感情の傾向を分析します。属性ごと(年代・性別・利用頻度など)にセグメント分析を加えることで、どの層で満足度が高いか・低いかも明確になるはずです。これにより、全体傾向と個別傾向の両面から現状を把握し、次のアクションにつなげるための基礎データが整います。
2.満足度の高い項目を特定する
集計・分析結果から、顧客が特に高く評価している項目を抽出します。
例えば「スタッフ対応」「商品の品質」「価格」など、5段階評価で4以上が多い設問や、自由記述でポジティブなコメントが多い箇所をピックアップします。これらの強みは、企業の差別化ポイントやブランド価値の源泉となるため、今後も継続・強化するべき領域です。
また、満足度の高い項目はプロモーションや営業活動で積極的に訴求することで、顧客ロイヤルティや新規顧客獲得にもつながります。
さらに、満足度の高い理由を深掘りすることで、他部門や他サービスへの横展開や、成功事例の社内共有にも活用できます。
3.改善が必要な項目を特定する
一方で、満足度が低い項目や不満の声が多い設問を明確にします。
例えば「納期」「サポート体制」「サイトの使いやすさ」など、評価が低い項目やネガティブな自由記述が集中しているポイントです。重要なのは、単に平均値が低いだけでなく、属性別に見て特定の顧客層で不満が顕著な箇所や、リピート意向に直結しやすい課題を抽出することです。
さらに、重要度×満足度の2軸でマッピングすることで、顧客が重視しているが満足していない「改善インパクト大」の項目を特定できます。このプロセスにより、施策の優先順位付けや具体的な改善テーマの明確化が可能となります。
4.優先順位を設定する
改善すべき項目が複数ある場合、リソースやインパクトを考慮しながら優先順位をつけることが重要です。満足度と重要度、事業への影響度、改善コスト、実現可能性など複数の観点で評価します。
例えば、顧客が最も重視しているが満足度が低い項目は最優先で改善対象とします。また、短期で成果が出やすい施策と中長期的な課題解決策を分けて整理し、PDCAサイクルで段階的に取り組むと良いでしょう。
優先順位付けは一度決めたら終わりではなく、市場や顧客の状況変化に応じて定期的に見直すことも大切です。
5.行動計画を作成する
優先順位が決まったら、具体的な行動計画(アクションプラン)を策定しましょう。各改善項目ごとに、目標(KPI)、担当者、実施スケジュール、必要なリソース、進捗管理方法を明確に設定します。
例えば「サポート体制の強化」であれば、FAQの充実、スタッフ研修の実施、チャットサポート導入など、具体的な施策を洗い出します。行動計画は関係部門と共有し、責任の所在を明確にすることで、実行力を高めることが重要です。また、施策の進捗や成果を定期的にモニタリングし、必要に応じて柔軟に修正できる体制を整えましょう。
6.実施とモニタリングを行う
策定した行動計画に基づき、改善施策を実行します。実施後は、事前に設定したKPIやCS指標(NPS、CSAT、リピート率など)を用いて効果測定を行いましょう。数値目標との比較だけでなく、顧客からの新たなフィードバックや自由記述の内容も分析し、施策の効果を多角的に検証することが大切です。
モニタリングは一度きりではなく、定期的に実施することで、改善の進捗や新たな課題の早期発見につなげます。成功事例や成果は社内で共有し、他部門への横展開や全社的なCS向上活動に活かしましょう。
7.フィードバックの再収集を行う
改善施策の効果を検証し、さらなる向上を目指すためには、顧客からのフィードバックを継続的に収集することが不可欠です。アンケートやインタビュー、NPS調査、ソーシャルメディアの声など、複数のチャネルを活用して顧客の意見を定期的に集めましょう。
再調査のタイミングは、施策実施後の一定期間後(例:3か月後、半年後など)が効果的です。再収集したデータをもとに、PDCAサイクルを回し続けることで、顧客満足度の持続的な向上と競争力強化が実現します。フィードバックの内容は組織内で共有し、次の改善策の立案やサービス品質のさらなる向上に役立てましょう。
上記の一連のプロセスを繰り返すことで、顧客満足度を継続的に向上させることが可能です。また、顧客とのコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、長期的な顧客ロイヤルティを確保することが重要となります。
このように、顧客満足度の向上には、単発な取り組みではなく、継続的な努力が必要なのです。
▼以下の資料は、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較した資料です。ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。 類似サービスの比較を行いたい方は、ぜひ参考にしてください。
アンケート集計・分析と改善アクションの進め方

データ集計・分析の基本手順
アンケート集計・分析は、まず単純集計で全体の傾向や分布を把握することから始まります。各設問ごとに回答数や割合、平均値などを算出し、全体像をつかみます。次に、クロス集計を用いて性別や年代、利用頻度などの属性別に満足度や傾向の違いを分析します。こうした多角的な視点でデータを深掘りし、仮説の検証や新たな発見につなげることが重要です。最後に、分析結果をまとめて結論を導き、次の施策に活かします。
顧客満足度スコア(CSAT・NPS等)の活用法
CSAT(Customer Satisfaction Score)やNPS(Net Promoter Score)は、顧客満足度を定量的に把握する代表的な指標です。CSATは「満足」「不満」などの評価を数値化し、平均値や割合で現状を可視化します。NPSは「他者への推奨意向」を測定し、ロイヤル顧客の割合を把握するのに有効です。これらのスコアを定期的にトラッキングし、時系列で変化を追うことで、改善施策の効果や顧客ロイヤルティの推移を評価できます。
回答内容をサービス改善・施策に反映する方法
分析で得た知見は、サービスや業務フローの改善に直結させることが重要です。満足度の高い項目は強みとして訴求し、低い項目や不満点は優先的に改善策を検討します。具体的には、改善が必要な項目ごとに担当者や期限を設定し、アクションプランを策定します。また、自由記述の意見も参考にし、現場の声を反映した柔軟な施策立案を行うことで、顧客体験の質向上につなげます。
効果測定とPDCAサイクルの回し方
改善施策を実施した後は、再度アンケート調査やCS指標の測定を行い、施策の効果を数値で検証します。改善前後のスコアや顧客の声を比較し、目標達成度や新たな課題を明確にします。結果をもとに次のアクションを計画し、継続的なPDCAサイクルを回すことで、顧客満足度の持続的な向上とサービス品質の進化を実現します。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
顧客満足度調査アンケートのよくある質問Q&A5選

Q1.顧客満足度調査とNPS調査の違いは?
顧客満足度調査(CS調査)は、商品やサービスに対する全体的な満足度や各項目ごとの評価を把握するものです。一方、NPS(ネットプロモータースコア)は「自社を友人や同僚に薦めたいか」という推奨意向を数値化し、顧客ロイヤルティや再利用意向を測定します。両者を組み合わせることで、満足度の現状と将来の顧客行動の両面を分析できます。
Q2.アンケートの設問数はどのくらいが最適?
設問数は10問前後が目安とされています。質問が多すぎると回答者の負担が増え、途中離脱や回答の質低下につながるため、目的に直結する項目だけを厳選しましょう。属性や基本情報、満足度、理由、自由記述など、必要最小限に絞ることで高い回答率と有用なデータが得られます。
Q3.満足度を回答した理由も聞くべき?
満足度の数値評価だけでなく、その理由も質問することで、具体的な改善点や強みを発見できます。自由記述形式にすると顧客の本音や想定外の意見が集まりやすいですが、分析には手間がかかります。選択肢式や記述式を目的に応じて使い分けるのが効果的です。
Q4.どんな項目をアンケートに入れるべき?
基本情報(属性)、全体満足度、推奨意向、利用のしやすさ、品質、価格、サポート対応、改善希望点などが代表的な項目です。業種や調査目的ごとにカスタマイズし、顧客体験全体を網羅できるよう設計することが重要です。
Q5.個人情報の取り扱いで注意すべき点は?
顧客満足度調査で個人情報を取得する場合は、利用目的や管理体制を明示し、必要最小限の情報だけを収集しましょう。プライバシーポリシーの提示や適切な管理体制を整えることで、顧客の信頼を損なわずに調査を実施できます。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。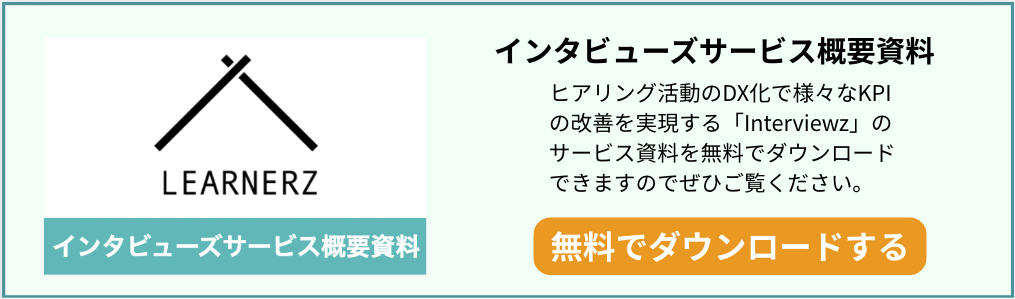
顧客満足度調査には「Interviewz(インタビューズ)」のヒアリングツールがおすすめ
上記のように、顧客満足度調査は、企業の成功に寄与する重要な要素です。そこで、より効果的な顧客満足度調査を行うために、「Interviewz(インタビューズ)」のヒアリングツールがおすすめです。
Interviewzが顧客満足度調査におすすめな理由は、以下の特徴があるからです。
直感的な操作性
Interviewzはタップ操作による診断を可能にし、テキスト入力の手間を省くことができます。これにより、ユーザーはスムーズにアンケートに回答できます。
シンプルな管理画面
管理画面がシンプルであり、専門的な知識がなくても容易にヒアリングシートを作成し、改善を即座に反映させることが可能です。
外部ツールとの連携が容易
Google AnalyticsやSlack、Salesforceなどの外部ツールとの連携が可能で、既に利用している分析ツールと併用することで、より効果的に運用できます。
リアルタイムでデータを収集・分析できる
ヒアリングした内容がスプレッドシートでリアルタイムに登録されるため、データの集計と分析が迅速に行えます。
カスタマイズ性が高い
独自ドメインの導入など、カスタマイズ性が高く、企業のブランディングに合わせたアンケートの作成が可能です。
これらの特徴により、Interviewzは、顧客満足度調査を効率的かつ効果的に行うためのツールとして多くの企業で採用されています。
Interviewzを活用することで、顧客のニーズを的確に把握し、サービスや商品の改善に迅速に反映させることができるため、顧客満足度の向上に大きく貢献するでしょう。
インタビューズは14日間のトライアル期間中もすべての機能を無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。