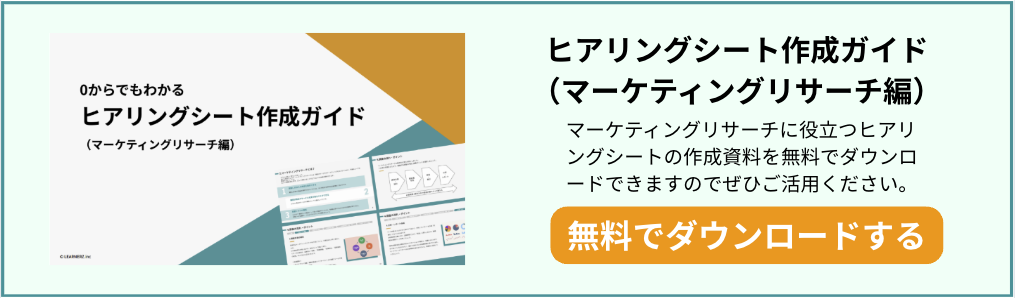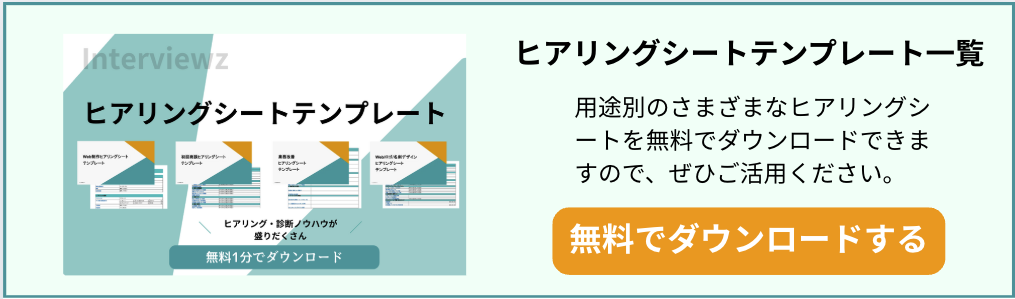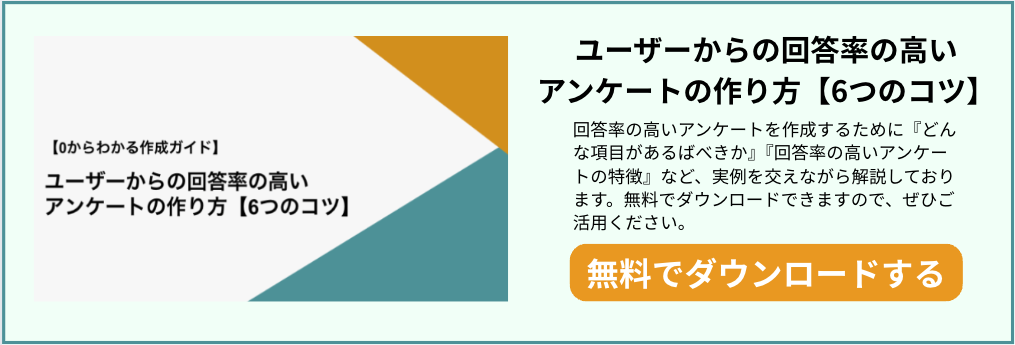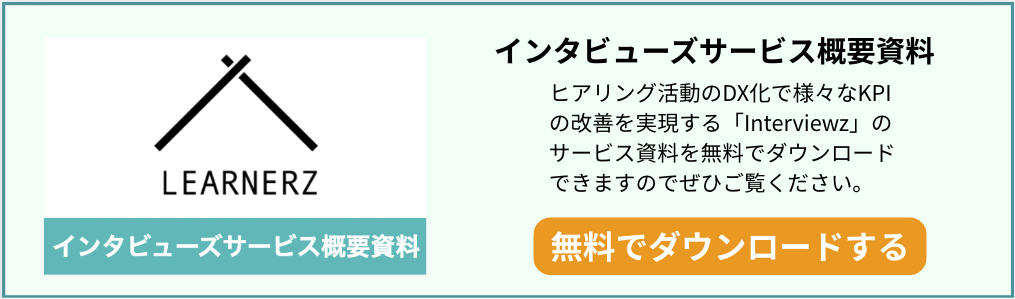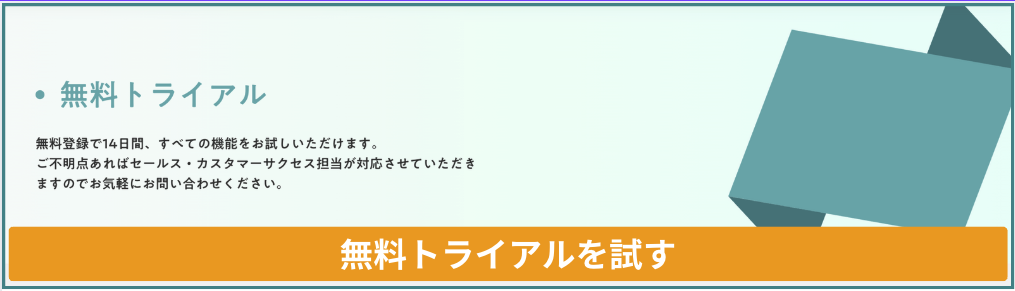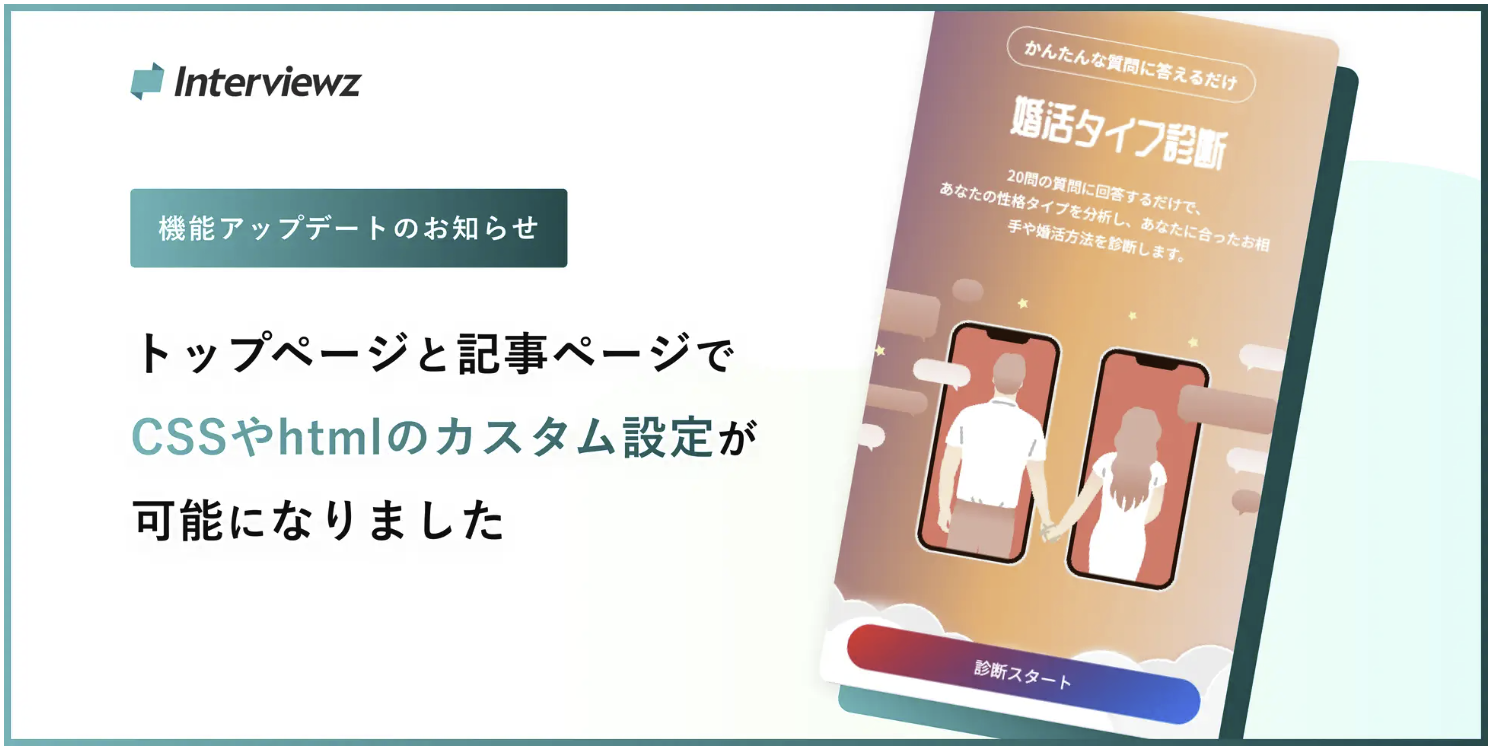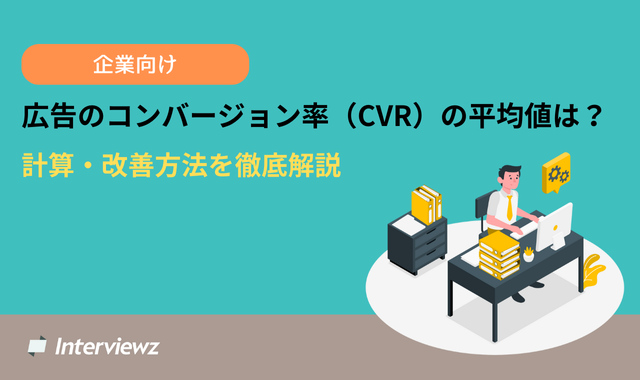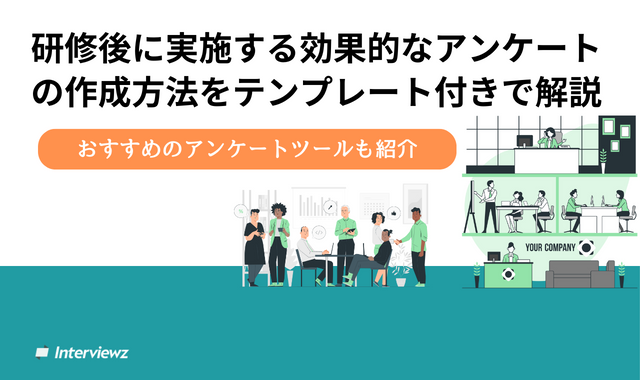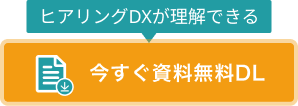アンケートとは?目的や役割、主な種類と活用法、作り方のコツも解説
- 2025/10/29
- 2025/10/29
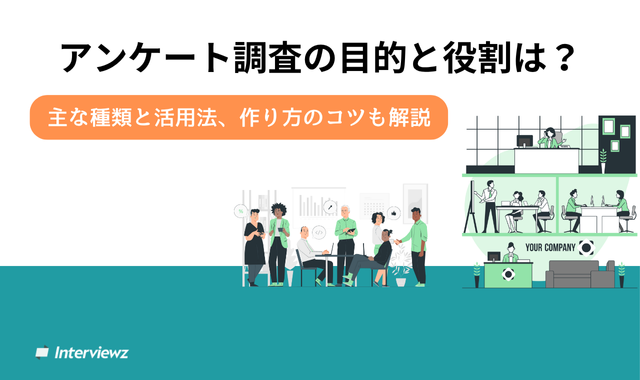
目次
事業活動においてアンケートは、顧客や社員の声を的確に把握し、課題解決や意思決定に欠かせない情報源となります。
目的に合わせた種類の選定や、実務に即した作成方法を理解することで、データの有効活用や業務改善の幅が広がります。
そこで今回は、アンケートの目的や役割、主な種類と活用法、作り方のコツも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
アンケートの基本概念と重要性

アンケートの定義と特徴
アンケートとは、多数の対象者に同じ質問を行い、回答を集めて分析する調査手法です。複数人から定型的な意見や行動データを収集することで、比較が可能となります。
アンケートは、紙や電話、インターネットなど様々な手段で実施されます。定量的な数値データ収集が主体で、意思決定やマーケティングに広く使われる基本的な情報収集方法のひとつです。
法人利用における課題解決力
法人でのアンケートは顧客満足度向上や製品改善、人事施策など明確な課題解決のために活用されます。大規模にデータを集め、実態を把握・分析しやすい点がメリットです。
課題抽出から施策立案までの意思決定を効率化し、経営判断の質を向上させる重要なツールで、適切な設問設計が成功の鍵を握ります。
業務改善につながる役割
アンケートは問題点やニーズを定量的に把握し、改善点を明確化する役割を担います。定期的な調査により、顧客や社員の声を継続的に収集することで、データドリブンな業務改善を促進可能です。
このように、アンケートはフィードバックを活かすPDCAサイクルの一環として、組織の成長やサービス向上に欠かせない手段です。
調査データの信頼性向上
信頼性の高いデータを得るためには、適切なサンプル設計とバイアスを減らす設問設計が不可欠です。
回答者のプライバシー尊重や匿名性確保も重要で、誠実な回答促進につながります。
正確な集計・分析手法を用いることで調査結果の裏付けが強まり、意思決定の質を支えられます。
アンケートの主な目的と役割

顧客満足度調査での活用例
顧客満足度調査は、商品やサービスの利用後に顧客がどの程度満足しているかを把握するために行います。アンケートで顧客の意見や感想を収集することで、改善点や強みを分析することが可能です。
例えば、飲食店では料理の味や接客態度についてのフィードバックをリアルタイムに反映し、サービス向上や顧客維持につなげています。
このように、アンケートは経営改善の重要な指標として活用されています。
社内意識調査による課題発見
社内の意識調査では、従業員の満足度や組織風土、業務上の悩みを把握できます。
アンケート結果から部署間のコミュニケーション不足や業務プロセスの問題点が明確になるため、改善策を検討・実行するきっかけとなります。
定期的に実施することで、職場環境の向上や離職率低下に効果的な施策を打つことが可能です。
商品やサービス改良の指針
アンケートにより、顧客ニーズや使い勝手の声を収集することで、商品やサービスの改良点を具体的に抽出できます。
例えば不満点が多い機能の改善や、新たな要望への対応策を構築し、開発や営業戦略に活かせます。
データをもとにした改善は顧客満足度の向上だけでなく、市場競争力の強化にもつながる重要なプロセスです。
市場分析における利用目的
市場分析では、ターゲット層の属性や購買傾向、競合商品との比較を明らかにできます。
アンケートから得た定量情報により、新商品の開発方向性やプロモーション戦略の立案が可能です。
消費者動向を把握し、市場環境の変化に迅速に対応するのに不可欠な手段です。
経営意思決定の支援効果
アンケートで得られる定量的・定性的データは、経営判断の根拠となる重要な情報です。
顧客満足度や市場ニーズの変化を数値化し、リスクを低減しつつ、事業戦略を最適化できます。従業員の声を反映すれば、人材マネジメントや組織改革の指針にもなります。
このようなデータに基づく意思決定は、経営の透明性と効率性を高める重要な要素です。
▼下記の資料は、自社のマーケティング戦略の立案を効率化するためのヒアリングシートの作り方をステップ別に解説した資料です。この資料では、マーケティングの課題や調査目的、今回の調査で明らかにしたい事柄を明確にできますので、ぜひご活用ください。
アンケートの主な種類とその特徴

Webアンケートの特徴と運用ポイント
Webアンケートは、インターネット上で実施する調査で、時間や場所を問わずに回答を得られます。
回答データは自動集計やリアルタイム分析が可能で、コスト削減にもつながります。
ポイントは回答者にわかりやすい設問設計と、スマホ対応のレスポンシブデザイン、回答率を上げるためのリマインド配信など運用面の工夫です。
紙アンケートのメリット・デメリット
紙アンケートは、対象者のパソコンやスマホ環境に依存せず実施可能で、来店客や高齢者に有効です。しかし、集計や分析に時間と手間がかかり、コストも比較的高いのがデメリットです。
入力ミスや回収漏れのリスクもあるため、効率性重視の法人調査ではWebアンケートに移行が進んでいます。
回収方法による分類
アンケートは、郵送回収、対面回収、電話調査、Web回収などがあります。
郵送は広範囲に配布できる一方、回収率が低いです。対面は回答率が高いですがコストがかかります。電話は迅速で、即時確認が可能です。
近年主流となっているWebアンケートは、コスト効率が非常に高く、多数の回答を短期間で得られるため法人では最も人気があります。
選択肢・記述式の設問構成
選択肢形式は集計が簡単で、統計的な傾向把握に適しています。複数選択やリッカート尺度など多様な形式があり、目的に合わせて使い分けます。
記述式は具体的な意見や詳細な情報を得られますが、集計が複雑になるため必要最低限にとどめるのが一般的です。両者を適切に組み合わせるのが効果的です。
法人向けオリジナル調査例
企業の法人向け調査では、顧客ニーズ調査、社員満足度調査、サービス改善アンケートなどが代表例です。業種や目的に応じて設問や選択肢をカスタマイズし、ターゲットに最適化された調査を実施しましょう。
オンラインツールと組み合わせてリアルタイムで効果を測定すれば、迅速に改善策を打つことが可能です。
▼ビジネスにおいて「ヒアリングの質」は、その後の提案の精度や成果を大きく左右します。しかし、実際の現場では以下のような悩みがよく聞かれます。
- 「何をどこまで聞けばいいのかわからない」
- 「毎回ヒアリングの内容が属人化していて、標準化できない」
- 「新人や外注メンバーにヒアリング業務を任せにくい」
- 「案件ごとに内容が違うため、毎回シートをゼロから作ってしまう」
下記のヒアリングシートテンプレートでは、上記のような現場の課題を解決するためにWeb制作・採用・営業・ブランディングなど、用途別・目的別にヒアリング項目が体系立てられており、誰でもすぐに使えるフォーマットになっています。
さらに、テンプレートには診断ノウハウやチェック項目も付属していますので、ヒアリングを通じて「課題の構造化」や「次のアクション提案」まで自然に導けます。
無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
アンケート作成のコツと実践ノウハウ

目的設定から設問設計までの流れ
アンケート作成はまず「調査の目的」を明確にすることが基本です。何を知りたいか、結果をどう活用するかを決め、次に必要な情報を洗い出しましょう。
設問は目的に直結する内容に絞り、回答者の負担を減らしながら必要なデータを集めます。
回答しやすい言葉を使い、一つの質問に複数の内容を詰め込まないことがポイントです。
分かりやすい設問の作り方
設問は誰にでも理解しやすい平易な言葉を選び、あいまいな表現や専門用語は避けましょう。
質問文は簡潔で一つの質問で一つの内容を問う形にします。選択肢は漏れや重複を避け、偏りのないバランスの良い構成にすることが重要です。
自由回答は必要最小限にとどめましょう。さらに、多すぎる質問数は回答者の離脱を招くため注意が必要です。
回収率を高める工夫
回答率向上には、アンケートの長さを適度に抑え、スマホ対応のレスポンシブ設計が効果的です。
シンプルで分かりやすい導入文やゴールの説明を加え、回答のメリットや所要時間を伝えましょう。
リマインドメールやSNSで丁寧に促進し、入力エラーのやさしい指示や選択肢の工夫で心理的負担を下げる仕組みも重要です。
バイアスを防ぐ設問例
設問のバイアスは、質問文の中立性を保つことで防止できます。誘導的な言い回しや答えを限定する表現を避け、回答者が自由に意見を表明できる設計を心がけましょう。
選択肢も偏りなく、公平で網羅的なものにし、質問の順番も後続の回答に影響を与えないよう工夫します。これにより信頼性の高いデータ取得が可能です。
分析につなげるデータ項目設計
設問設計は、分析を意識して行います。数値化しやすい選択式を基本とし、クロス集計や相関分析が可能な質問構成を目指しましょう。
自由回答はテキストマイニングを前提に、必要最低限の設定にすることが大切です。回答の一貫性や回答漏れを減らすための工夫も必要で、後の集計・分析工程をスムーズにすることがポイントです。
▼下記の資料では、実際にアンケートを作成する際に回答率の高いアンケートを作成するために『どんな項目があるばべきか』『回答率の高いアンケートの特徴』など、実例を交えながら解説しています。
アンケート作成でお悩みのある方は、下記の資料を参考にしながら効果的ななアンケートの作成方法を確認してみてください。
アンケート結果の活用法と効果的な運用

集計・分析の基本手法
アンケート結果の分析はまず、「単純集計」で各質問の回答数や割合を算出し全体傾向を把握します。次に「クロス集計」で属性別の回答傾向を比較し、性別や年齢などの属性で差異を探ります。
自由記述では、カテゴリ分けやテキストマイニングを活用し、意見の代表例を抽出しましょう。これらの手法を組み合わせることで、データの特徴を多角的に理解できます。
現場業務へのフィードバック方法
分析結果は現場で活かせる形に噛み砕くことが大切です。具体的なアクション推奨や課題点を箇条書きにし、部署別や担当者別のフィードバックレポートを作成します。
定期的なミーティングや掲示板、イントラネットで共有し、現場感覚で理解できるようにしましょう。結果を元に具体的な改善施策を検討・実施することが重要です。
レポート・提案資料の作成ポイント
資料作成では、要点を簡潔にまとめ読みやすさを重視します。グラフやチャートを使い視覚的に理解しやすくしましょう。
調査目的に沿ったストーリー構成にして、仮説検証や課題発見の流れを示すと説得力が増します。結論では、提案や改善策を具体的に明示し、意思決定層が迅速に判断できる資料作成を目指します。
ヒアリングツールでの自動化活用
ヒアリングツールは、設問作成から回答収集、集計・分析までを自動化できる便利なツールです。例えば、AIを使ったテキスト分析や、条件分岐による柔軟な回答誘導などが可能です。
データをリアルタイムでダッシュボードに表示し、問題点やトレンドを即座に把握できます。これにより、時間短縮と精度向上を両立し、運用の効率化を実現します。
運用改善のPDCAサイクル
アンケート分析結果を基に改善計画を立て(Plan)、新しい設問や運用を実践(Do)します。結果を評価(Check)し、効果を検証。問題があれば再度改善案を策定(Act)し、サイクルを継続することで常に最適な運用が可能となります。
継続的なPDCAサイクルの構築は、アンケートの質を高め、組織課題の解決に繋がる重要なポイントです。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
導入事例から学ぶアンケート活用の成功例

法人プロジェクトでの実績紹介
あるカフェチェーンでは、新メニュー開発でWebアンケートを活用し、顧客ニーズを的確に反映しました。公式アプリやQRコード配信で多くの回答を集め、分析結果に基づく仕入れや商品構成の見直しで売上10%増を達成しました。
さらに、回答者に割引クーポンを提供したことで、回収率が大幅に向上したのも成功のポイントといえるでしょう。
これは、実データの活用による成功例のひとつとして参考にできる事例です。
業種別の活用シーン
飲食業界は顧客満足度調査、製造業は商品改良や品質向上のための技術的フィードバック収集、IT業界はユーザビリティ調査、金融業界は顧客信用調査やニーズ把握にアンケートが幅広く活用されています。業種固有の課題に合わせた設問作成と、多様なデータ活用が成功のポイントです。
ヒアリングツール「インタビューズ」の事例
インタビューズは多段階設問や条件分岐、データの自動集計が可能で、企業のマーケティング調査や人事アンケートに活用されています。
特に多様な属性を持つ対象者から精緻な回答を収集し、課題の構造化やアクション提案までスムーズに繋げる運用を実現しています。
インタビューズを活用することで、効率的かつ質の高い調査が可能です。
成功要因の分析と応用方法
成功要因は「調査目的の明確化」「設問の適切な設計」「回答者負担の最小化」「回答率向上施策」「データ分析と現場反映の連携」に集約されます。
これらを満たすことで調査の信頼性・有効性が高まり、他業種や異なる調査テーマにも応用可能です。さらに、継続的な改善を続けることが、成果拡大につながる重要な要因です。
継続的運用のポイントとノウハウ
継続運用では、定期的な調査実施とPDCAサイクルが不可欠です。調査結果の共有と改善策実行を現場に落とし込み、関係者の理解と協力を得ることが重要です。
ツールの使いやすさの向上や、回答者インセンティブ設定も、継続的な効果を生み出す要素となります。さらに、社内外でのフィードバック体制を強化することも成功のポイントです。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。
アンケート調査の実施には「インタビューズ」がおすすめ!
インタビューズは、誰でも簡単に高品質なアンケートやヒアリングを作成できるノーコードツールです。
テキスト入力を最小限に抑え、タップ操作でストレスなく回答できるUXが評判で、回答率向上に貢献します。
条件分岐や詳細な自動集計機能で多様な設問設計や複雑な回答分析が可能で、迅速な意思決定を支援。強固なセキュリティ対策により法人利用も安心で、マーケティングや人事調査、顧客対応の効率化に最適です。
14日間の無料トライアルもあるため、導入前に効果を体験できる点も魅力です。
インタビューズは14日間のトライアル期間中もすべての機能を無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。
▼Interviewz(インタビューズ)に新機能が追加され、CSSカスタマイズとHTMLタグ埋め込みが可能となりました。これにより、自社ブランドのデザインに合わせた診断・ヒアリングページを最短1日で構築できます。
フォントやカラーの変更、アニメーション追加、外部ツールや分析コードの設置も簡単で、SEO対策やCVR向上、データ活用がスピーディーに行えます。さらに、プレビュー機能で事前確認し即時反映できるため、マーケティング施策の自由度と実行スピードが大幅に向上し、リード獲得や効果測定改善を加速させることが可能です。
ぜひ下記の資料から、インタビューズの詳しい機能をご確認ください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。